|
1 桜
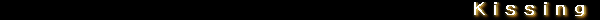
青く澄んだ空に向かって満開を少し過ぎかけた桜が、春の少し強い風にあおられて飛んでいく。
「井名里先生っ きょろきょろ誰を探してるんですか。あなたです、あ・な・たっ」
「え? あっ……あー……すいません、つい」
先ほどから何度も聞きなれた名前が呼ばれていて、思わず辺りを見回し視界の端に留まった桜吹雪に目を奪われていた夏清が、やっと自分が呼ばれていたことに気づいて、呼んでいた教師の元へ走る。
「『つい』って……田中や鈴木じゃないんだから。他にいないですよ、井名里先生なんて」
頼まれていた押しピンをひとつずつ渡す夏清に脚立の上の教師が呆れたように言った。
「すいません。『井名里先生』っていうと、ウチのヒトみたいで」
「は?」
「どこかにいるのかと思って。いろいろ心臓に悪いんで、名前の『夏清』ほうに先生つきで呼んでいただけたらうれしいです。子供たちはもう了解してくれたんですけど」
それと校長先生も、と付け足して、なおもあたりを見回す夏清。場所はこの春、教師になって初めて赴任した小学校の校門で、これから行われる入学式のための最後の飾りをつける作業中だ。こんなところにいないとわかっていても、なんとなく見回してしまう。
「身内に先生がいらっしゃるの?」
「ハイ。ダンナさんが高校の先生で」
「ダンナ!? 井名里先生結婚してるんですか!? 今年大学卒業されたって……」
「高校卒業してすぐ結婚して、在学中に子供産んだりいろいろしてたから、卒業するのに七年もかかっちゃったんですよねー ホントは今年も冬に下の子がまた入院しちゃったので、単位一つ落としそうだったんですけど、さすがに二年続けて採用辞退はマズいだろうからって教授に特別講習組んでもらってなんとか。裏口卒業しました」
気楽そうに笑いながら、押しピンを差し出して夏清が言う。差し出された手に条件反射のように相手も手を伸ばすが、距離が中途半端だ。
「……子供?」
「ハイ。上が今年小学校入学で、下が五才……っ! あぶなっ!!」
目の前の脚立がぐらりと動きかけて、夏清が慌てて押さえる。落ちかけた当人も短い悲鳴のような、うめきとも聞こえるような声をあげたあと、大げさに深呼吸をして手早く作業を仕上げて黙って脚立から降りてきた。
「……失礼ですけど、井名里先生おいくつですか?」
「え? わたしですか」
「……ああ、もう、えーっと」
「夏清です、井名里夏清。ついひと月ほど前二十五になりました」
「いー……カスミ先生、身長は何センチ?」
「え!? 身長のこときかれてたんですか!?」
ローヒールのパンプスを履いている夏清より、降りてきた教師のほうが若干、背が低い。性別も違う。そして彼が履いているのは底の厚い運動靴だ。
「違います。さっきのは年。ついでに身長」
「あ、百七十五……でしたっけ、採用のときの健康診断で。びっくりです、子供産んで、ハタチ超えても伸びるんですねぇ 身長って。子供のことでばたばたしてて、大学の健康診断ここ数年受け忘れてた間に伸びてたみたいで」
三つも若いとか、五センチも高いじゃないかとブツブツつぶやく目の前の教師の事を気にせず、夏清が笑いながら言う。
「じゃあ、子供育てながら大学に行って、教員採用試験も受けたの?」
中学や高校の教師になるより、小学校の教師のほうが倍率が低いとはいえ、子供の減少にともなって採用人数も徐々に減って来ている。今さらりと、二回合格したようなことが聞こえたような気がするが、気のせいと言うことにしたほうが心身ともに楽でいられそうだ。
彼自身が教員試験に付いては一年浪人をしているのと、何度受けても合格せず、臨時採用で食いつないでいる人間を何人も知っている。教員になるための、その試験勉強に割かなくてはいけない時間も半端ではなかった。そして、教育学部を出たものの、採用試験に合格することができず結局教師になることをあきらめた人間も知っていた。
「でも別に、私一人で子供育ててたわけじゃないですし、過ぎてみたらそんな大変じゃなかったかもって。むしろこれからかなーって、思うんですけど」
傍らを、おはようございますと挨拶をしながら集団で登校してきた子供たちが通り抜けていく。
「そしたら、お子さん今日入学式? 行かなくていいの?」
何を聞いてもお気楽な答えしか返してこない夏清に観念したのか、彼が話題を変えた。
「行きたいですけどしょうがないです。ま、大勢行ってくれるみたいですから」
「うん、ムダに多いよね、父兄って。一人の子供見るために両親とそのまた両親来るから、全部で六人なんてザラだもんなぁ ビデオ撮るのにヘイキで通路に陣取るし、やめさせたら他の迷惑顧みずに保護者席のいすの上に立って撮影はじめたり」
脚立を片付けながらぼやくように言われて夏清が苦笑する。
「ウチの人たちも……他に迷惑かけてなかったらいいんですけど……」
周囲からの視線が痛い。
背が高い、だけの理由かどうかは別にして、昔からじろじろと見られることには慣れているのだが、今日感じるそれは質が異なる。ひそひそと周波数が違う声で行われている情報交換のノイズも五感のうちの何かに障る。
たった一人の子供の入学を見届けるために、決してヒマではないはずの大人が五人とおそらくヒマな子供が一人。
しかも自分を除く大人たちは、それぞれ微妙に各方面に対して有名人だ。
なにが悲しくて自分の長男の入学式でこんなに居心地の悪い思いをしなくてはならないのか。
全ての元凶は付属品のそのまたオマケにあるのだが、おそらく本人は気づいてもいなければ、現状の異様な空気についてまったくカケラほども気にしていないはずだ。
手持ち無沙汰でもタバコを手にしていい場所ではない。時間的にも立ち上がってどこかで一服する余裕はないだろう。整然と並んだパイプ椅子に身を沈めて目を閉じ、息を吸って吐く動作を意識して行って、始まってもいない式が終わることだけ考えていると、横からスーツの袖を引かれて井名里礼良はゆっくりと横を見た。
「ねえ」
何も言わずに首だけ向けると、隣にべったりと女の子を……礼良の娘、ちいをくっつけた氷川実冴と視線が合う。
一体どんな術を使っているのかは不明だが、この十年ほどの間、彼女の容姿に変化がないどころか逆に若返っている気がする。そんなことを面と向かって言えば十倍返しでこちらの姿かたちについて返ってくるので考えるだけにとどめておく。
「ケンちゃんほんとにここでいいの?」
私は不満だわと言わんばかりの実冴に礼良が嘆息する。
「……ホントもウソも、健太(けんた)が友達もいるこっちの学校がいいっつーんだから」
実冴が言いたいことはわかっている。小学校の選択については、家から程近いこの公立の小学校にするか、北條の機関が経営している学校にするか、何度も話し合ったのだ。入学する本人はもとより、夏清や北條響子も一緒に。それで、この学校に行く本人がこの学校に行くことを決めたのなら親がどうするわけにもいかない。
「本人の意思に任せるのはいいけど、あの子絶対、勉強楽しくないわよ。いまさら『あいうえお』や数字の書き方習ってどうするの」
どうするのと言われても、現行の教育システムの中では公立の学校はどうすることもできない。公立の学校を選ぶ以上、保護者にもどうすることはできない。
そう言われて、実冴の向こうに座る人物を見る。
「……響子さん……北條の学校に入れたくないとか、そういう訳じゃねぇよ。みんなそっちのほうがお前に向いてるって言っても、学校ってもん自体知らねぇんだから、みんなと同じがいいと思っても仕方ないだろ。チビのほうはそのまま行く気みたいだし」
「うん、おばあちゃんとこがいい」
お気に入りのよそ行きのワンピースを着て、子供特有のくせっ毛をフェイクファーでできた髪留めで二つに括ってもらい、本人曰く『うさぎさんみたい』でかわいいくてうれしい格好ができて、そう答えたちびっこは朝からとてもご機嫌だった。
その上に、事前の約束どおり『ものすごーく、逢いたかった実冴』がいたので、絶対に騒がないこと、と父親に言われた通り、おとなしく抱かれていた井名里家の長女、ちいが響子をみて笑う。
「それに、一度入ったら変われないわけじゃないだろ。通ってみて違うと思ったらいつでも編入できるんだから好きにさせときゃいいんだよ」
二年前から、北條響子が代表をつとめる教育団体が日本国内でも学校の経営をはじめた。教育研究機関の付属校で、年齢による横割りの学年制ではなく、フリースクールのような形式の授業を行うのだが、四才から十八才までの子供をあつめて一貫教育を行うれっきとした学校法人だ。
ちいについてはさまざまな理由から通常の保育園などに行かせることができなかったので、学校ができたときからそちらに通わせているので、本人の選択肢としても一つしかない。しかし健太は先に市の保育園に預けていたこともあって同じ年の子供と遊んでいたほうが楽しいのか二年前も頑として施設を変わる事を拒んだ。
「ケンちゃんも塾だけしか行ってないのにカリキュラム、中学の数学まで行ってるんでしょ? 国語だって……」
「実冴」
さらに言い募ろうとした実冴を響子が止めた。
「だって、どうしてわざわざ回り道させるの?」
「いいのよ。正しい道なんてないんだから。求めていたものと違ったとき、それをどう正すかが大事でしょう。周りが寄って集って押し付けてもなんにもならないわ」
柔らかくそう言われて、さすがの実冴も黙り込む。
「それに……北條の施設じゃこんな風に入学式はやらないもの」
やらないというより、できないが正しい。まとめて入学することはほとんどなく、年中編入者があるためだ。
北條総研の学校への編入は入試はない。現在は系列の塾で顕著な成績を修めている子供を学校側がスカウトしている。
「しっかし……」
響子のおかげで実冴の『どうして?』発言から逃れることのできた礼良が、さらに渋い顔をする。
「アレがついてきてこんなことになるなら、無理にでも北條に入れときゃよかった……」
入学式の雰囲気を純粋に楽しんでいる響子とは逆に、げんなりとした様子で礼良がつぶやいた。コレについては実冴も異論がないようで、一緒にため息をついている。
「どうでもいいから、アレをなんとかしてくれ」
「ムリ」
礼良が視線で『アレ』を指す。
みただけで、相当上等なものだとわかるスーツに身を包んで、他の保護者と一緒になってビデオを構えている人物は氷川公だ。そしてその回りや、入学式が行われる講堂の出入り口には、晴れやかな式にそぐわない黒やグレーのスーツに身を包んだ男たちがうろうろしている。
「最初から他人のフリしておいたらよかった」
「それもムリよ。何にも考えないで話しかけてくれるほうに持ってる地域通貨全部かけてもいいわ」
「曲がりなりにも旦那だろう。ちゃんと紐つけてどっかにくくっとけよ」
実冴と公は、現在戸籍上、再び夫婦になっている。
どうせ変わらないからという実冴の意見はどうせ変わらないならと却下された。
「仕方ないでしょ、自分の子たちのときできなかった分やりたいらしいのよ」
「五重くらいの罠張って阻止したんだろうが」
自分の子供たち、慶(けい)と逢(あい)の入学式に行きたかったこと。そしてトラブルに見まわれていけなかったことをトラブルの内容まで説明し、健太の入学式にはどうしても行きたいと言う公に夏清が根負けした。公が偶然重なった言った複合的な厄災が、どう考えても実冴の差し金としか思えなかったので聞いているうちにかわいそうになってしまったのが理由なのだが、夏清はここにいなくていいからOKしたのではないかとさえ思えてくる。
「だって、騒ぎ起こされたらいやだったんだもん。一応すごく気遣いな名門だったのよ。芸能人の子供とかもいて行事は一切撮影禁止だったけど、公ちゃんにそんなこと言っても通じないもん」
ゴリ押し半分で無理やり子供たちをねじ込んだ手前、あまり騒ぎを起こしたくなかったらしい。ただし、そうまでして入れた小学校だが一年生の二学期半ばで転校させているので、そのくらい許してもよかったのではないかと思うのだが。
「今日だってやりたいって言ったこと十のうち一つくらいしか許さなかったんだからね」
来させるのはかまわなかったが、こんな派手になるのなら他人のフリをしておけばよかったと後悔しても遅い。いっそ違う日を教えておけばよかったと思っていたら、考えていたことがわかったのか実冴が首を横に振る。
「教えなくても勝手に調べて勝手に来るわよ。違う日を教えるって方法はもう私が逢の中学の入学式で使ったから通用しないわよ。絶対来るわ。もっと派手な方法で。あのころより逆に融通は利くみたいだから。身動き」
あのころ、とは『副社長だった』ころのことだろう。確かに、そのころより生き生きしている。いろいろと。
しかし。
黒くて大きくてリアフロントにレースのカーテンが付いているような装甲車並みの装備をつけた車が一台、プラスSPの車が三台だ。当然一番注目を集めたのは言うまでもなく、十分派手だった。
「頼むから今自分がどういう立場か理解させろ。教え込め」
「馬の耳に念仏だもん。一応、今年の選挙も出馬したりしたら今度は私から勝手に離婚するからって言っといたのに……」
六年前の参議院選挙のとき、誰が井名里数威の後継になるのかギリギリまでもめていたが、誰が言い出したのか何がどう転んだのか、気がついたら公が出馬、そして当選してしまっていた。
選挙期間中、公の選挙運動にカケラも協力しなかった実冴だが、どうせ当選するわけが無いのだからと『当選したら戸籍上も復縁する』という約束をしてしまい、現在に至っている。
内心実冴がどう思っていたのかは別にして、何かあるごとに公の隣で笑っていなくてはならないらしい。今でもまだ不受理届けでも出しておけばよかったとブツブツ文句を言っていたが、書類上の扱いが変わっただけで生活はあまり変化していない。
当選してただの議員になることについては、衆参合わせれば議員など六百人を超える。それこそピンからキリまでうじゃうじゃいるので、いいことにしろ、悪いことにしろ、さしあたってなにかやらない限り、一生地元の人間にしか名前を覚えてもらえない議員も多い。
だが。
「ほんっとーに、私にもわからないから。総理が公ちゃんを大臣に選んだ理由。そんなことしたら嫌いな納豆山ほど官邸に送りつけてやるって脅しても、実行しても折れなかったからねぇ なぜか公ちゃん身近に置きたかったみたい」
当選一期目、議員になって四年目のときいきなり、よくわからない名目で作られた役に立たなさそうなポストとはいえ内閣入りをした公は、一躍日本中の人々に顔と名前を覚えられた。
もともとはじめての資産公開の時、いきなり上位に食い込んでアレは誰だと騒がれていたのだ。
本当は絶縁状態であっても、誰もが氷川グループとつながっていると思っているだろう。
離婚してやると実冴が言えば公はそれなら議員を辞めると言うが、最終的に響子が止めれば実行されないことが前回バレてしまったので、この二人が離婚しないことも公の出馬も半ば決定している。よほどのことが無い限り今年の選挙で公は再選されるだろう。
男前で人当たりがよく、いつもへらりと笑っていて一見人畜無害な外面と、そのまんまの表裏無く同じ内面なので、おおむね良好な印象で人々の記憶の中に彼は住んでいるらしく、ここでも大きな騒ぎにならないものの視線と興味が公と自分たちに向かっている。
当の本人は周りにはべるSPなど気にも留めず、にこにことちいに負けないくらい上機嫌でデジタルビデオカメラをいじっている。もしかしたら、このくらいの注目を集めることなど慣れてしまって、大したことはないと思っているのかもしれない。
「どっちがメインか判らねぇぞ。それ見込んであの服か?」
誰かがフラッシュを光らせたことをきっかけに、他愛の無い動作をしていた公が被写体になっている。
「どうだろ。あのブランドは若いときからお気に入りだったから。似合ってきたのは最近だけど」
着るものについてはアレでこだわりがあるらしく、さらにそれなりにセンスも悪くないので実冴は口を出さないことにしている。
写真を撮られていることに気づいた公がにこやかに対応する様を、こちらは眺めているだけだ。
「それより私は親父様まで同じブランド着てるからちょっとびっくりしたよ」
黙って入学式のしおりに目を通していた数威が、聞こえなかったフリをしている。
「そうよ。今朝早く呼ばれるから何事かと思って屋敷に行ったら、継森といっしょになってクロゼットの中を右往左往してるの。後援会のパーティのときも継森に適当にスーツ選ばせていた人が、本気で悩んでるのよ。仕方が無いから目に付いた一番よさそうなのを私が選んだの」
大きな灰色熊と小さな白熊が洋服の森をうろうろしてるみたいでかわいかったわという独特の表現をして響子が笑う。いっしょになって実冴が笑い、ワケがわかっているのかいないのか、ちいも一緒になって笑っていたが、居心地が悪そうにしている数威を見ているとまるで自分のことのようで、礼良は唇が少し開いて端が少し上がったものの、笑ったわけではない。と言うより、笑えない。
親になってやっと親の気持ちがわかるというが、わかっても楽しいことはあまりない気がする。
ため息をついたとき、式の進行役らしき教師のアナウンスが入り、ピアノで奏でられるかわいらしい入場行進曲が始まって、場内のざわつきがぴたりと止まった。
「あ、おにいちゃんだ」
てけてけと歩いてくる子供たちの中から、ちいが真っ先に健太を見つけて指をさす。
「ちい」
「ごめんなさい」
礼良が伸ばされた手をつかむ前に、ちいがすばやくひっこめて、さらに実冴と自分の体の間に腕ごとすっぽり隠す。
大きなたれ目が上目遣いに礼良に向けられて、言外に謝ったからいいでしょう? と問い掛けている。
にらめっこに似た感覚だが、このごろ先に目を逸らしたり、閉じたりするのは礼良のほうだ。ほっておいたら延々じーっと見つめられつづける。
これまでも何度も注意してきたし、本人も『人を指差す』行為が相手に不快な思いをさせることがあるのでしてはいけないことだと理解している。ただ、考えるより先に体が動くのだろう。
すぐに謝っているが、最近開き直ってきている。
「わかってるなら気をつける」
「うん」
このやり取りをこれまでに何度してきたか知れない。健太のほうは、一度教えたことはちゃんと守って、同じ失敗を繰り返すことはあまりないのだが、ちいは何度も繰り返す。学習していないのではなくて『ついうっかり』やってしまうことが多い。
健太のような子のほうが珍しく、子供なので仕方がないといえばそうなのだが、どうにも見ていていらいらする。
勉強という範囲だけなら物を覚えたり、理解したりと言うことについて二人にそう違いはない。
ただ、健太は一を教えるとそれを忠実に覚えて理解し、二へ進もうとするのに対して、ちいは突然二を飛ばして三を思いついたりする。
兄弟だろうが別の人間なので、個性は会って当然なのだがわかりやすい比較対象があるので『つい』比べてしまう。
「お兄ちゃん一番?」
謝って、注意も受けて了解したので許されたと解釈したらしいちいが、入学生の名前のなかで健太がはじめに呼ばれたことに反応して実冴を見上げている。親の気も知らないでそのすっかり立ち直った様子に、ぐるぐると考えていたのがばかばかしくなる。
結局、毎回同じことを思い悩んでいる自分も同じなのだと気づいて、礼良はまた、今日何度目か知れないため息をついた。
小学校の駐車場を囲むように咲いた桜が春の空まで淡い暖色に染めているようだ。
やっと式が終わり、それと同時に公が秘書に引きずられるようにしながら帰っていった。本人の希望としては教室での様子もビデオに撮り、昼食もいっしょに摂りたかったらしいのだが、みんなで昼食をと提案した実冴に同調しようとしたところを止められた。
今日これからのスケジュールを告げられて、へらりと笑ってこともなげに言い放ったのだ。
「自分のヘリ飛ばすから」
もちろんこの提案は、即座に満場一致で否決された。近くに空港があったら自家用飛行機で乗り付けられたかもしれない。
公にとってはヘリだろうが飛行機だろうが車だろうが、同じ乗り物としてひとくくりなのだろう。少し前に自家用の電車がほしいと言い出して、それも周りにいた人間に止められていた。
「夏清ちゃんも来られるって。ちょっと遅くなるかもしれないから現地合流。で、ナニ食べる?」
「ちい、すぱれっきーたべたい!」
髪がゆれるのが楽しいのか跳ねながら自作の歌らしきものを歌っていたちいが実冴の言葉に真っ先に答える。というより、なにを食べたいのか尋ねたら、十回中九回はスパゲッティが食べたいと答えるのだが。
先ほどまで『さくら』と言う単語を延々節を付けて歌っていたのが、オートで『スパゲッティ』に切り替わる。ただし、舌が足らないので、夏清曰く『ちい語』で発音している。くるくる動き回る我が子をひょいと抱き上げて、礼良がまた低い声でその名前を呼んだ。
「ごめ……」
「なにが悪くて謝るかわかってて謝るのか?」
咄嗟にごめんなさいと言いかけたちいの言葉をさえぎって礼良が尋ねる。
「……ぴょんぴょんしてた」
「そう。お前ははしゃぎすぎたら熱がでるだろう。それから?」
「…………すぱれっきー?」
「それはいえなくていい」
子供の発音など気にしていたらきりがない。すぱれっきーくらいなら意思の疎通もラクだが、本当に何を言っているのかわからないときがまだまだある。
「ほかはわかんない」
「何かを決めるときは年長者の意見が優先」
「ごめんなさい」
小さい手を礼良の胸について、降りる意思を伝えるちいをかがんで降ろす。
「わたしは何でもいいのよ。ちいちゃんが食べたいもので」
足が地面に着くと同時に早足で数威の元に行ってスラックスをはいた足にしがみつく。
「おじいちゃんは、すぱれっきーいや?」
必死な様子で見上げられて、数威が苦笑する。どう見ても子供しか持っていない武器をちらつかせての脅迫だ。
当然、数威もそのままちいに同意する。
「ちい、おじいちゃんだいすき」
両手を上げて抱っこを要求するポーズに緩みっぱなしの表情のまま今度は数威がかがみこんでちいを抱き上げる。めがねの奥の目が絶対に他では見られない形で笑っている。
「それから、自分のことを呼ぶときに名前を言わない」
「……だって、ちいはちいだもん」
せっかく機嫌がなおりかけたところに礼良にいつも言われつづけていることを言われ、ちいの唇の端が下がる。泣いてやるぞという顔をした後、しっかりと数威のスーツにつかまって顔をうずめてしくしく泣き出す。
「アンタうるさすぎ。そんなのそのうちなおるんだから放っときなさいよ」
「そうねぇ 本人が恥ずかしいと思うようになったら自然にやめるんだから、そんなに神経質にならなくても」
抱いている数威はもちろん、女性陣二人も加わって全員で慰めにかかっている。
泣いていないほうにかけてもいいのだが、こうなったら負けだ。観念して悪者になるしかない。周りにいるのが礼良と夏清だけなら、ちいは絶対に泣かない。泣きまねが通用しないからだ。
逆にこのメンバーならば、泣けば味方になってくれることをわかっているのですぐに泣く。しかも、大声で泣くよりも自分のほうさえ見ていてくれればしくしくと泣いたほうが効果があることも知っている。
さらに、この三人にだけは父親である礼良が敵わないと言うことも知っていての所業だ。
「タチ悪……」
あさっての方向を向いて心の中でつぶやくよりほかにない。子供は小さいだけで優遇される生き物だ。それに、自分の子供なのだから、甘やかされてうれしそうにする様子を見るのが本当にいやだと言うわけではない。
「ちい……またなんか買ってもらうよね」
何気なく目を向けた昇降口から子供が溢れ出してきて、すぐに自分の父親を見つけたらしい健太が、登校時上履きだけしか入っていなかったほとんど空と思われるランドセルを揺らしてやってくる。そして状況を見た健太が、礼良にだけ聞こえる声でそう言った。
「あら、ケンちゃん終わったの?」
「うん。みんなも待っててくれたの?」
入学式が終わって教室に戻っての最初の二十分こそ父兄がいたが、大人はすぐに追い出された。そうしないと子供たちが前を向いて先生の話を聞くよりも、後ろの自分の親のほうを気にするからだというのが建て前だが、実際のところ親のほうがうるさいと言うのがその理由だろう。
健太のクラスだけ見てもざっと子供の四倍近く大人がいるのだ。教室に入りきれない分は当然廊下にはみ出していた。内と外で会話をしだせば、やかましいことこの上ない。
子供たちだけ集められていた時間も十五分程度のもので、待っていたと言うほどの時間ではない。ただ、忙しい人たちだとわかっているので待っているのは父親と妹だけだろうと思っていたのに、健太の予想外に、消えていたのは公だけだった。
「そうよー みんなでいっしょにご飯食べに行こうと思って。大勢のほうが楽しいでしょう?」
「うんっ」
子供たちが現れたせいでにわかに駐車場の中が親子たちの会話で騒がしくなる。自分の車のエンジンをかけて、ナビで店の検索を始めた実冴の背中に健太が声をかける。
「あのね、実冴さん。お昼、パスタ以外のものがあるとこがいいな。昨日の晩も三日前も、うちの晩御飯スパゲッティーだったから」
|