|
5 楓
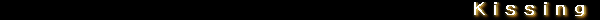
「ここがどこかわかっていたらそんなにやかましく走らない!!」
病院の廊下をダッシュするように走っていたちいに、廊下にいた年配の看護婦が注意する。
「あ、ハイ。ゴメンナサイ」
減速して口先で謝罪し、ネジがゆるくなったのか、走りながら引くとがたがたと音をたててしまうキャリーを抱きかかえて、それでも目指す病室に向かって走ってしまう。今度はブーツのかかとが鳴ってやっぱりうるさいのだが、はやる気持ちは抑えられない。
目的の部屋のドアをノックもなしに開くと、荷物をかばんに入れ終わったらしい夏清の後姿が目に入る。
「お母さんっ!!」
「おかえり」
「え、あ。だだいま」
振りむいていつも家に帰ったときと同じように声をかけた夏清に、抱いていたキャリーをおろしてちいが答える。
「もしかしなくても、今日退院とか?」
「そうよ。ちいは今日帰ってきたのね」
かかとが高いブーツを履いたちいと、歩きやすいスニーカーをはいた夏清では、もともとの身長差にプラスアルファでちいの方が見下ろすような高さだ。
「うん。成田について、久しぶりにメッセージ見て、急いできたんだけど、スタートの時点で駄々遅れだったね」
「そうねぇ ちいが行っちゃって、二日後だったかな。それより髪、切ったのね」
母親を見下ろすのがどうも苦手なちいがキャリーに腰をかる。ちょうどいい高さにあるちいの頭に夏清が手を伸ばして、やわらかいくせっ毛をなでる。
「え? あー……うん」
グラビア写真撮影の前にバッサリ切って、そのまま映画の試写会に行かされて、その後大学の友人に誘われるまま旅行に行ってしまったのだ。
仕事はその日から年始まで休むと決めて何も入れないようにしていたので、ちょうどよかった。
いったん家に帰ったが、誰もいなかったので置手紙だけ残して。
「肩より短くするのは初めてじゃない? それも似合ってていいわよ」
「ほんと? でもなんか、またお父さんに言われそうでヤダ」
「春みたいに、いきなり髪をまっ白にしたりしたんじゃないから大丈夫だと思うけど?」
「あれはー……」
ちいがごにょごにょと言わけをする。大学に入学した自分へのお祝いということでこれまで染めたことのない色にしようとしたら白になってしまっただけなのに、一週間毎日毎日小言を言われつづけて、最後はちいが折れて無難な色にまた染めなおした。
「それに、夏のときみたいに何もいわれなくても怖いでしょう?」
夏は夏で、左耳に七つと、右耳に四つピアスをあけて帰ったら、だまってはさみを目の前にかざされて、そんな風にするのなら耳を切ってやろうかといわんばかりの目でにらまれて、ちいは黙ってその場で全てのピアスをはずして渡した。
「あれもー……」
友人が三つあけていて、じゃあ片方でどのくらいまでできるかと挑戦してしまった。夏場にピアスを開けると化膿するのですぐはずすつもりだったが、どうしてはずして家に帰らなかったのだろうと後悔しても遅い。
「それより、ひとり?」
「ひとりって、他に誰が?」
きょろきょろする夏清につられてちいもつい後ろを振り向くが誰もいない。
「誰って、お父さんと健太」
会話がかみ合わない。
「はぁ!? お兄ちゃんイギリスから帰ってくるの!?」
「そうよ。あれ、知らなかった? 迎えに行ってくるって言うからてっきりあなたも一緒に乗せてもらって帰ってきたんだと思ってたのに」
「知りませんでしたっ! って、もしかしてお父さん空港行ったの!?」
「ええ」
「うそー もう、言ってくれたらお兄ちゃんくらいつれて帰ってきたのに。空港に車おいてたから」
通行料が……と、うめきながらちいががっくり肩を落とす。
「もう、昔っからそうだよね、お父さんってお兄ちゃんに甘いよね!? 絶対、お兄ちゃんに逢いたいからすぐ迎えに行ったんだよ。私が昔頼んだときなんか、飛行機見るのも近づくのもヤダって言ってたくせにーっ」
「そうかしら。でもちい、あなた帰ってくる日を言わなかったでしょう」
言われて気付く。そういえば、少し長めの旅行なので帰る日を伝えると途中でいらない小言をいただきそうで、行ってくるとだけ書いて、そのあと日本に帰ってくるまで一度も自分あてのメッセージなどのチェックをしなかった。
「そうだけどっ! でもね!! 私のやることはみーんな、アレもだめコレもだめって言ってたくせに、お兄ちゃんがイギリス行きたいって言ったらわりとあっさりオッケーしたじゃない!!」
「あれは……ただ学校を変るのとは違ったから、すぐに許したわけじゃないわよ」
兄の健太は、公立の小学校を一学期で辞めた。周りの大人たちが危惧したとおり、通いだして二週間で学校がつまらなくなったらしく、親には何も言っていなかったがよくちいに『学校って思ったほど楽しくないよ』とこぼしていた。それでも彼なりに溶け込もうとがんばっていたようなのだが、三ヶ月が限界だった。
本当なのかウソなのか真偽の程はわからないが、周りの子供と合わないのでもう来ないでくれと学校側から言われたと、だいぶ経ってからちいは実冴から聞いた。実冴が笑って『自分より頭のいい子がいると、教師も教えにくわよねぇ』と続けていた。
そのあとはちいとともに北條の学校へ籍を置いていたのだが、ある日突然そちらもやめて外国の学校に行きたいといいだした。
さすがにこちらは、夏清もハイそうかとは言えず、周りも何とか思いとどまらせようとしたのだが、最終的に礼良が許したので健太の留学は決ったのだ。
「でも、私が同じこと言ったら絶対、ダメって許してくれなかったはずだもん」
「それは言えてるわねぇ でもちい、あなた今回勝手に旅行に行っちゃったでしょう? 叱られるわね、絶対」
「カナダに二週間だけだよ? お兄ちゃんなんか十年近くイギリスいて、五回くらいしか帰ってきてないし! 私には大学は通えるから家に帰ってこいって言うしっ!」
どうして私ばっかりとちいがわめく。声が大きかったらしく、ノックの後ドアが開いて、先ほどとは違った看護婦にまた注意された。
「お母さんが大変なときにいなくなっちゃったのは悪かったと思ってるの。でもさ、私がいてもいなくても、お二人らぶらぶですし。深く考えないで行っちゃいました」
口元に手を当てて、ちいが言い訳をする。
「いなくていいとは思ってないわよ。ちいがいてくれて、毎日すごくメリハリが効いて楽しいわ」
「メリハリって」
感情の起伏が激しいちいは、見ているだけで退屈しない。実際ちいが帰ってきてからのほうが礼良と二人で会話をする時間が増えた。もちろん話題の中心はちいなのだが。
「いいのよ、旅行くらい好きに行ってくれたら。それよりあのお屋敷であなたたちが二人っきりってほうが怖い気がするわ」
「そう言われたらそうだけど、逃げたと思われてたらやだなぁ ほんっとーに、すっぱり忘れてたの、ゴメンナサイ」
「だから、いいってば」
ぺこりと頭を下げたちいをみて、これと同じくらいの素直さがあれば衝突することもないのにと、夏清が苦笑する。
「いいんだけど、私はあなたがいつ『こんな家でてってやる』っていなくなっちゃうかって、そっちの方が心配よ。がまんしてるのはよくわかるから」
「んー……なんか、それ言ったら簡単に『二度と来るな』っていわれそうだし。あそこの本は魅力的なんだよね。大学図書館にも国会図書館にもない本がひいじいさまのコレクションにあるとは」
大学の講義のとき、教授が探していると言っていた本が家にあったのだ。引越したとき整理を兼ねた目録作りを手伝わされたので家にどんな本があるのかはほとんど覚えている。
ちいは別に貸してもかまわないと思っていたのだが、礼良が了解しなかった。以前、有名大学の教授に大事な本を貸したところ、そのまま盗られたことがあるらしく、頑として持出しを許可してくれなかったので、教授の方が記録メディア持参で家にやってきた。
そのときはなんてケチくさいと思っていたのだが、その後行った教授の研究室を見て父の意見が正しかったかもと思い直した。ものすごい量の本や資料が山積みされていて、大学図書館の本でさえいつから返していないのか大量にそこにあった。
「敷地の半分が本に埋ってるような家だから、広くても管理しやすいといえば、そうなんだけどねぇ」
亡くなる数年前からガンであることがわかっていた数威の財産は、実冴がうまく処理してくれたおかげで彼の死によって発生する相続税などのために不動産を物納しなくてはならないような事態は避けられたのだが、今住んでいる東京の井名里の屋敷は厳密には礼良のものではない。
維持費に人件費を足すと年間七桁ではおさまらないような建物を個人で管理することは難しい。そのためにほとんど架空の名義だけの法人を立てて自分たちが間借するような格好だ。選挙の関係上地方にある本家の屋敷だけは公が相続したが、彼についてはそんな心配は要らない。
「ま……別にお父さんのことキライって訳じゃないし。うるさいし鬱陶しいけど、最近、なんていうか、やっぱり正しいのはお父さんかなとも、思う。ときどき」
小さく肩をすくめて、たまにだけどねとちいが笑う。
「やっぱり。うん、家族は一緒の方がいいんだろうなと、思うんだけど」
大きなかごのなかを覗き込むと、むーっと眉間にしわを寄せるようにしながら小さな物体が手足を動かしている。
「だからって、コレ?」
「……コレとか言わないで。どうしてあなたはそういうところばっかりお父さんに似るのかしら」
「そういうとこって、似てないよ全然っ」
「似てるわよ。ドアを開けるときノックしないとか、赤ちゃんみて開口一番で『コレ』っていうところとか。あの人ねぇ 健太のときもちいのときも言ったのよ『コレ?』って」
「……知らないよそんなの」
さすがに、生まれたてのときのことなど覚えていない。
「だって、名前知らないもん。女の子なんだよね、名前は? もう決めたの?」
「ええ『みあ』ってつけようと思ってるの」
「……みゃー?」
「言うと思ったわ」
みゃーという言葉に反応したのか、そのとおりの音でみあが泣き出す。はいはいと返事をして、夏清が抱き上げるとぴたりと泣き止んだ。
「ちーとみゃーか……」
「かわいいでしょ?」
「かわいいけど。わたしに『ちい』ってつけたのは絶対間違いだよ。この間大学の健康診断で測ったら、また伸びてた。これ以上はもういらないわ。でもみゃーならサイズ関係ないからよかったねー みあ。でも私とこの子、十八ちがうんだよね、十八歳と十ヶ月」
先月の十一月に誕生日を終えている健太とは、二十歳違う。
「お母さんはともかく、お父さんだよ、モンダイは。自分が今何歳か知ってるの? この子が二十歳になったときあの人幾つよ? とうより生きてるつもり? 平均余命は今や下降の一途よ?」
「言わないであげてよ。あなたたちがさっさと親元からいなくなっちゃうから、お父さんなりに寂しかったらしいんだから」
「うそくさー」
特に寂しかったというあたりが。
成長するにつれて断片的に、けれど鮮明に思い出す小さいころの記憶の中の父親は、とにかくなにをするにもダメダメと言っていたことと、幾度となくひっかけられた低レベルゆえに抗えなかったいたずらの数々だ。
「わたしも寂しかったわよ」
「さらに輪をかけてうそくさいです。お母さんって、お父さんがいたらよくない? ほんとに。一緒に暮らして、お二人観察してて思うんですけど。まあね、いいけど」
この両親は、怖いくらい仲がいい。ちいがいようがいまいが、べたべたと仲良くやっている。
「子供は人生の不確定要素なんですって」
「わたしらは余興かい」
たしかに、ひょんなことから芸能という世界に入ってしまったちいは七つからほとんど親元を離れて暮らしていたし、兄の健太も九才になるかならないかの時にイギリスに行ってしまったので、こちらもすでに親とすごす時間よりも離れている時間のほうが長いだろう。
「そういえば、またカナダなんて、何しに行ってたの?」
「大学の友達とスキーしてくるって……書いてなかったっけ、置手紙」
「なかったわよ『ちょっとカナダに行ってきます』ってそれだけ書いて二週間もねぇ……でも最近の大学生ってお金もちなのねぇ」
「そうだよ。みんなすげーお嬢とかぼんぼんだよ。私は私のお金で行ったからね。ほら、おばあちゃんのところが出してた笑える調査結果。一目瞭然証明してるよウチの大学」
おばあちゃんのところ、とは、北條総合教育研究所のことで、教育に関しての調査研究については国内で他の追随をゆるさぬ最大手研究所だ。
その北條総研が二十年程前から行っている調査の一つに『子供の学力値と保護者の所得の対比』と言う一見かかわりのなさそうなものを調べたものがある。
過去にもさかのぼり、調べられたその調査では、過去においてはさほど接点の見られなかった両者が、現代においてはほぼ比例するしている。
「ちいはちいがお金持ちだものねぇ」
その調査を裏付けるかのように、ちいの通う大学にはお金持ちがあふれている。当然そう言った人種ばかりではないのだが、どうしても同じ環境で育ったものたちがグループを形成するため、本人も自覚するくらい金使いの荒いちいは、気づいたときには周りは親が金持ちの、金遣いの荒い友達しかいなかった。
「金持ちっつーか。気がついたら貯まってただけだもん。んー……でも、まぁ、たぶん、これからは使うばっかりになりそうだし」
ちまちまと出ていた北條の塾のローカルCMが、コンペティティブで優秀賞を獲得したことがきっかけで、全国ネットで放映されるようになり、気がつけば有名人になってしまった。
本人とその家族の意思に関係なく巻きこまれていく井名里家の面々をみて実冴が私にまかせておきなさいと、ちいをプロモートするだけのために会社を作り、嬉々としてマネージメントに精を出してくれたおかげで、ちいはあっという間に押しも押されぬ子役に仕立て上げられていた。
もちろん礼良は子供を売るほど生活に困っていないと大反対だったが、なってしまったものは仕方がなく、響子にも説得されてしぶしぶ了承した。
もともと趣味と言い切ってしゃしゃりでた実冴がピンハネすることもなく、ちいが稼いだお金はほとんどすべてちいのものになった。おそらく普通に暮らす限り、一生かかって使い切れるかどうかもわからないので、なるべくお金は使う方向で、というのがちいの個人的方針だ。
CMのイメージからか、最初はバラエティなどで数学などの問題を解かされていたが、気がつけば子役としてドラマにも出るようになっていた。
最初のころこそ加減がわからずに暴走しては熱を出していたが、それも次第に減っていって今では少々のことでは風邪もひかないまで健康になってしまった。薬は生きている間ずっと飲みつづけなくてはならないが、体力がついてきたので病気らしい病気もしない。
子役としてデビューしたが、十五歳になったころから徐々に仕事は減ってきていた。両親に似たのだとしか思えないのだがすくすくというよりどんどん育って、現在身長も百七十八センチ。旅行に行く前に久しぶりにグラビア撮りをしたときのカメラマンに『でっかいちいちゃんだね』と言われたときはやかましいわと殴りかけた。
雑誌に載るのは年が明けてからだが、その一言でかなり気が立っていたのでおそらくものすごく不機嫌で怒った顔をした写真に仕上るだろう。
子役から人の目に触れすぎていたこともあるのだろうが、目新しいアイドルがわんさかと横並びになる年頃には、中心の場所は彼女たちのものになっていた。
背が高すぎて他の男優と釣り合いが取りにくいのでドラマの仕事はほとんど端役だし、写真のなかのキレイに作り上げられた自分をみるのはあまり好きではない。
舞台の仕事は、体力がついてきたとはいえ練習の時点でちいがついていける世界ではなかった。
かといってテレビの仕事も特番やバラエティが重点になってきてなんだか違ってきたなぁと思ってきたころに、転機は訪れた。
昨年の九月初め。
ドラマの端境(はざかい)にあるクイズ番組の特番の収録直後、全問正解して旅行など豪華商品を総取りしたちいに、ほとんど答えられなかったアイドルが喧嘩を売ってくれた。
『天才天才って言われてるけど、どうせヤラセなんでしょ? 子役で売れてたけど最近落ち目だからってやることせこいわよ』
という言葉を、言い値でちいが買った。
『わたしはほんとにアタマがいいの。そっちこそ、先に誰か買収して答え教えてもらわなかったの? ああそっか。教えてもらっても覚えてられなきゃ意味ないわよね。あんなバカ丸出しじゃファンも引くんじゃない? ごめん、引くほどいないか、これも』
売られた喧嘩は倍にして売り返せ。利子と熨斗(のし)までつけて、きっちり耳をそろえて返すのが礼儀だと実冴に教えられて育ったのだ。他にも『礼には礼を、無礼には無礼で返せ』『受けた礼は対等返し、ただし一生忘れるな』というのも教わった。
倍の言葉を同タイムで言いきられた相手が本当に口に出して『キー』という反応をしたので、反論しようとしているのをさえぎるように、自分の頭を指差しながらちいがたたみかけた。
『私、ココにはちゃんと人間の脳ミソ詰ってるから、今のコトバわからないんだけど、もしご希望なら英語でも口論してあげるわよ。あ、もしかして今のはサル語? アナタの脳ミソはサル? それともその軽そうな頭の中にはカニミソが詰まってるのかしら。首から上についてるのはインテリア? 趣味悪いののせてるのね。ああ、話逸れたけど、なに言ってたか覚えてるわよね? 悪いけどせめて日本語をちゃんと喋ってねってこと』
それならば証明して見せろというのでひとしきり悪口を英語でまくし立ててやった。覚えたての別の外国語でもよかったのだが、そちらは俗語まで全て覚えているわけではなかったのでやめた。
早口の英語の意味を訳せない相手の『適当なこと言ってんじゃないわよ!』という叫び声で言うのをやめてあげた。外国語で意味がわからなくてもバカにしていることは伝わるものだということは経験上知っている。
ちなみに内容についてはわかっても公衆の面前では訳せないようなものばかりだったので、訳せと言われたらさすがに困ってしまったのだが誰もそれは求めてこなかった。
『そんなに頭がいいって言うのなら、もっとわかりやすく証明しなさいよ』といわれて『それなら東大に受かってやるわよ、それならあんたでもわかるでしょ』と返してしまったのは、本当に口が滑ったのだが。
『法学部にはいりなさいよ』という相手に『東大は入ったときは教養学部しかないんだよバカ。法学部に入りたかったらまずは文科一類をうけるんだバーカ』で。
あとは怒鳴りあいとつかみ合いの大喧嘩になり、更なる売り言葉と買い言葉が続く。
実冴によって二人とも頭から水をかけられてやっと離れた。
マネージャに引きずられて帰っていく相手に『その代り私が合格したら脱ぎなさいよ!!』と、こちらばかりやらされるのはむかつくので怒鳴ったら『脱ぐどころかアダルトにだってでてやるよ! そのかわり合格しなかったらアンタが脱げよ!!』と捨て台詞を残された。
大喧嘩の一部始終は局の機転(?)によってすべて記録され、合格するまでをドキュメンタリで追わせてくれというディレクタの申し出を実冴が二つ返事で受けてしまった。
大学受験の必要書類は夏清にこっそり揃えてもらうつもりだったが、この夫婦に隠し事を求めるのが間違っていた。あっさりと事情まで礼良の耳に入って、呼び出されてこっぴどく叱られた。
かくして。
合格してしまったわけだが。
「勉強って、面白かったんだね」
しみじみとやっと実感していた。発端はどうあれ、生れてこの方こんなにまじめに勉強をしたことはないと言うくらいがんばってみて、初めて勉強がおもしろいと感じた。
これまでの人生学んできたものは多かったが、勉強をする、ということではちいは他の子供より時間が短かったことは否めない。
週の四日を仕事に費やせば、学校にいけるのはせいぜい二日。北條の学校が特別な授業を組んでくれていたとはいえ必要なムダさえ省いての勉強は何の余裕もなくおもしろいと感じることもなかった。
「楽しいでしょう?」
「……うん。四月くらいまではさすがにいくつか仕事もあるんだけど、二年生からは仕事いれずに勉強だけやろうと思ってるの。とりあえず、大学生の四年間は勉強が中心で行きたいって社長……じゃなかった、実冴さんにも言ってある。もしかしたらそのあとの専門教養とかもとるかも」
仕事中は社長と呼びなさいと言われつづけたせいで、プライベートでもそう言いかけてしまう。
ただし、ちいのいる実冴が興した会社所属のタレントはちいを入れて現在三人で、事務の人間を含めても総勢八人しかいない。
ちなみに、どうして名前ではなく社長なのかと言うと、そっちのほうが『らしい』からなのだそうだ。
「それでいいって?」
「私がそうしたいならそれがいいからって」
「最初に言っただろうが。お前には両立できないから中途半端になるくらいなら両方やめちまえって」
突然別の声が背後から聞こえて、ちいが振り返ると、見上げなくてはならない数少ない人が立っていた。
「だからっ どうして両方やめなきゃならないのよ」
「おかえりなさい。健太は?」
「ああ、下の売店で買物してから来るって」
「ちょっと!!」
ちいの問に答えずに礼良がすたすたと奥に行き、簡易ベッドになるソファにかけて夏清と話をしている。
絶対ないがしろにされている。先ほどまで娘の相手をしていた夏清が、もう礼良のほうしか見ていない。
「ちくしょー ばかっぷるがっ」
「いつもいがみ合いされてるよりいいんじゃないの?」
「うわあっ」
わざと聞えるように悪態をついたちいの背後から、また声が降ってくる。
「そんなに、おどろかなくても。僕はノックはしたからね。返事聞かずに入ったけど」
「その体勢でどうやってノックしたのよ?」
「足」
両手にアレンジメントされた花を持って立つ健太を見てちいが聞き返すと、にっこり笑って言いながら片足を上げている。
「おかえり、ひさしぶりね健太。あなたまたやせたんじゃない?」
「ただいま。やせてないと思うけど、背は伸びたよ。そういえば体重計にはしばらくのってないかなぁ お母さんとは一年ぶりくらいかな。ちいとは今年の夏に逢ったけど、お父さんとは五年くらい逢ってなかったって話を車の中でしててねー」
喋りながらベッドに近づいて、健太がかごを覗き込む。
「で、コレ?」
一瞬静かになった室内に夏清とちいの笑い声が広がる。
「だめだ。お母さん、やっぱり私たち、言われたこと言い返してるんだよ。だってお兄ちゃん、顔はともかく性格は全然お父さんに似てないもん」
なぜ笑われているのかわからない様子の健太がきょとんとした顔をした後、まあいいやと再び笑顔になって、ハイと夏清に花を渡す。
「オメデトウゴザイマス」
「あら、ありがとう」
「こっちはちいにあげよう」
「なんで?」
「なんでって、うれしくない? 理由がいるなら、そうだなぁ 僕があげたいだけなんだけど、ちいがいらないなら、みあにあげよう」
くるりと身を返した健太の手をつかんで妹に回りかけた花を奪う。
「いや、いりますっ ちょうだい。お兄ちゃんっていろんな意味で日本人の感覚とズレてていいよね」
ちいとしては、出産なので病気ではないと言ってしまえばそれまでだが、退院する母に花を渡すのはともかく、自分の分まであるとは思っていなかったので口をついて出てしまったのだ。
ものをもらうのはうれしい。花やぬいぐるみはいくらもらってもいらないことはない。
「ちい、髪の毛切っちゃったんだ。シシ丸みたいでかわいかったのに」
「シシマルってなによ? 染めたりパーマかけたりで、痛んでたから切っちゃったの。また伸ばすよ」
夏に逢ったときは、ちいの方が髪が長かった。くせっ毛に輪をかけるようにしてくるくるとパーマをかけてボリュームをだしていた髪を、ばっさりとショートカットにしたちいと、くせのない髪をそのまま伸ばして一つにしばっている健太。
「そうだっ 私、みあにお土産買ってきたの。めちゃくちゃかわいいんだよ。ちょっと高かったけど衝動買いしちゃった。あとね、お母さんには山ほど楓汁買ったよ。一個だけ持って帰ってきたけど残りは来週中には届くと思う」
自分の頭に注がれる父親の視線から逃げるように、しゃがみこんでキャリーのファスナをあけて、ちいがいそいそと中からビンに入った薄茶色の液体とと白い何かをとりだす。
「ああ、メイプルシロップか」
ビンに貼られたシールにある三つに分かれた葉っぱのマークをみて楓汁が何のことなのかわかったらしい健太が独り言のように言う。
「うん。はちみつよりこっちのほうが赤ちゃんのいるお母さんにはいいんだって。帰ったらホットケーキ焼いて食べようね」
「僕の分も」
「お兄ちゃんにもたくさん焼いてあげる。昔お母さんがしてくれたミッキーみたいな形にするのよ」
大きな丸に、小さめの丸を二つくっつけて世界で一番有名なネズミと同じ形にするのが一時期井名里家で流行っていた。病気がちな箱入り娘で人が多いところに連れて行ってもらえないちいのためのものだったのだが、大人にも好評でいつもその形だった。
「で!! コレコレっ 耳がついてて、尻尾がついててふかふかなの。ナントカ白キツネとかいうやつだから、フェイクじゃないよ、本物っ」
広げて見せた毛皮は、新生児をくるむのにはすこし大きめだ。
「かわいい。おくるみ?」
「ううん。犬用だっ……っぃたー」
犬用、と言いきる前に礼良がちいにげんこつを落した。
「……買ったあと気付いたのよ!!」
見た瞬間に一目ぼれをして買ってしまったのだ。タグを見ると『for dogs』と書いてあったのだが、そのときはすでに日本に帰ってきていた。
「ほらほら、かわいい。いいんじゃないの? 似合ってて暖かそうで」
全く気にする様子もなく夏清がみあにそれを着せて抱きあげた。確かに本人もタイミングよく至極満足そうにふにゃふにゃと笑うような顔をしていた。不思議なことにそれだけで、周りがふんわりとまるくなる。
「抱いていい?」
機嫌のよさそうなみあをみて健太が両手を出している。
「お兄ちゃん、チャレンジャだね……」
こんな危なげなものは抱けないと思っていたちいの横で、小さな物体が手渡しされている。
「そうそう、首の後ろ持って、包み込むみたいに」
「包み込むって……」
好奇心で抱いてみようと思ったものの、腕の中の芯がないような、やわらかくて心もとないのにずっしりと重い感覚にやめておいたら良かったと健太が後悔する前にみあのほうが泣出した。
「うわ。どうしよう。ちい!!」
「な、なに!?」
名前を呼ばれてみあを差出され、反射的に手を出してしまった。さらにどうしようもない抱き方をされたみあが、小さな体のどこから声が出るのかというくらいの音量で泣いている。
「いやーっ! お母さん笑ってないで助けてっ めちゃめちゃ泣いてるよ」
「がんばりなさい」
わけもわからず……いや、抱かれ方が不満なのだと言うことはわかるのだが、どうやったら泣き止むのかがわからずに、ちいまで泣きそうな顔をして夏清に助けを求める。対する夏清は手を差し伸べるでもなく泣きそうな上の娘と、泣いている下の娘を笑ってみているだけだ。
がんばれと言われても、なにをどうがんばればいいのかわからない。そうしているうちにますますみあが必死な様子で、踏ん張るように手足に力を込めて、顔を真っ赤にして泣き続ける。
「うわーん。こっちが泣きたいよぅ」
「かしてみろ」
声より腕のほうが早かった。
つまむようにしてひょいとみあが持ち上げられて礼良の腕の中に入っている。ちいがぽかんとしている間にふごふごという余韻も短く泣き止んでしまった。
「あ、お父さんスゴイ」
「ほんとだ。見た感じお兄ちゃんの抱き方と変らないのになんで?」
「ぜんぜん違うだろうが。だいたいなぁ 恐る恐る抱かれて安心できるわけないだろう。それしか頼るもんがないのに、支えるもんが不安定なら怖いって言われて当然。お前らだって立ってる足元がいつ崩れるかわからないようなところに長く居たくないだろう」
「なるほど。ゴメンネ」
まだ少し難しそうな顔をしたままのみあを覗き込んで健太が謝っている。
「赤ちゃんは泣くのが仕事みたいなものだから、別に謝らなくていいのよ。それに覚えてないんだから。みあなんか、健太に比べたらまだ泣き方もかわいいほう。健太は本当に、寝てるとき以外はいつも泣いてるような子だったからねぇ 逆にちいは全然泣かなくて。ほとんど病院だったから、いつもいつもいっしょに居られたわけじゃなかったけど。子供って本当に一人一人違ってて、一人一人初めてなのよね。あなたたちはいまじゃこんなにでっかくなって」
立ちあがって夏清がみあを抱く。
「一人ででかくなったような顔してな」
「悪かったです、態度も図体もでかい娘でっ 少なくともお父さんのおかげなのは体のでかさくらいだから」
ああ言えばこう言う、という見本のようなやり取りと、両手が空いた礼良が出した手をちいが避ける。
「んじゃ、私は自分の車で帰るから」
「待って。僕もちいのほうで帰る。久しぶりに日本語みたらどうしても本屋行きたい衝動を抑えきれなくて」
「また本? お兄ちゃん本ばっかり買ってないで服とかご飯とかに使おうよ、お金。まぁ夏に比べたらちょっとだけお肉ついたみたいだけど」
「あの時は大学が休みで学食にいけなかったからやせてたけど、今はちゃんと食べてるよ。機内食おかわりしたし」
「しないで、そんなもんのおかわり。って言うか、普通食べきれないからあんなもの」
呆れたようにちいが健太のハラの辺りを叩いたあと、後ろでひとつに束ねてある肩よりも長い髪をひっぱる。
「それから、髪の毛切るとか。鬱陶しいから切るって言ってなかったっけ?」
「言ってたけど、気が変ったの。それに僕、ちいみたいに染めたりしてなからつやつやだよ?」
切ることが面倒で伸ばし始めて、徐々に洗髪が面倒になって自分で適当に切るというのがパターンだったが、この秋入って来た女の子がやたらと健太の髪を気に入ってしまい、健太が髪を切ったら自分も切ると泣いて抗議されて断念した。
健太にしてみれば彼女の長い髪の方がよっぽどきれいだと思ったので、その髪を切られるくらいなら、洗うくらいの手間は仕方がないかという結論になってしまった。
「勿体無いでしょ」
「これのどこが」
男の髪を勿体無がってどうするのとさらにぐいぐいとちいが髪を引く。
「これじゃなくて、ちいの髪。似てたんだよね、くるくる具合とか、やわらかさとか」
「はぁ?」
「ちいは短くても似合っててかわいいけどね。女の子の髪は長い方が個人的にはいいなってこと。錯覚って人生に必要だよね」
「なにそれ。わけわかんない」
自己完結している健太に、ちいがいう。
「うん。ほら、自分自身にだまされてナンボのものってあるのかなぁって」
「……お兄ちゃんってときどきわかんないよね」
「そうかな」
ちいがしゃがみこんで開けっ放しだったキャリーのファスナを閉めると、健太がそれを引きうけてくれた。花を両手で持ったちいと二人がじゃあと出て行きかけたのを礼良が止める。
「さっきの金だけじゃたらないだろ」
何枚かの札を健太に向けて差出す。
「アリガトウ」
「お父さんっ 私には私には? 私にもお小遣いっ」
見ていたちいが私も頂戴と花を片手に持って、空いた手をだす。
「お前は俺より金持ってるから小遣いなんかいらないだろうが」
軽くその手を叩くように、それでも健太に渡したものと同じ額がちいに渡される。
「うわーい」
「それでついでに晩飯買ってきてくれ」
「………喜んで損した。いいもん、これでホットケーキミックス買占めてやる……」
ちいの車で健太の要望どおり、書店に立寄って、ふたりそろって棚の本を端から物色しながらカゴにどんどん本を入れていく健太にちいが尋ねる。
「ねえねえお兄ちゃん。すっごく聞きたかったこと聞いていい?」
「ドウゾ」
「なんでいきなりイギリスだったの? 私、ある日家に帰ったらお兄ちゃんもういなくてさ、次の日ドラマの仕事あったのも忘れて大泣きしたんだよ」
健太が居なくなることは聞いていたけれど、まさか自分に何も言わずに消えてしまうとは思ってもいなかった。逢いに行きたくてもほとんど地球の裏側のその国は遠くて、仕事をしていたせいもあって、何度か帰ってきたときにはどんなに忙しくても家に帰っていたが、ちいは夏に初めて逢いに行ったのだ。
「あーそれ」
少し前にベストセラーになった小説の文庫版を手にとって見ていた健太が、本棚からその作家の本をまとめてカゴに入れてから顔を上げて、苦笑してちいのほうを見る。
「別にイギリスじゃなくても、ちいがいないとこだったらどこでもよかったんだけどね」
「ええ!?」
聞き捨てならない言葉に、ちいが健太のコートをつかんでしがみつく。
「考えてもみてよ、どこに行ってもちいちいちいちい。ちいちゃんのお兄ちゃんだよ? 子供だったからいやだったなぁ それ」
「あ……うん」
健太なりにがんばってやって見せても『ちいちゃんのお兄ちゃんだもん、そのくらいできるよね』で済ませられてしまうのが本当にいやだった。
ちいはどこまでも天才というか、持って生れたカリスマ性の高さもあって常に勝者であり優者だった。比べられることの残酷さに全然気づいていなかったのだと思うのだが、健太は逆に頭のいい家族たちに囲まれて、五歳くらいのときすでに自分が回りに比べて平凡だと気づいてしまった。
そんなことに気付く子供の方が非凡なのだが、いかんせん健太の場合は回りの環境が特殊だった。
そこにきて、いきなり妹が有名人になってしまって、なぜか自分まで『できてあたりまえ。できなかったらブーイング』という理不尽極まりない状況をうけ入れろと言う方が無理だろう。
さらに健太が嫌だったのが『ちいちゃんと全然似ていないのね』という無遠慮な問いかけだった。健太にしてみれば、家族の中で似ていないのがちいだ。父親の本当の母親からの隔世遺伝だろうというその顔は、両親や自分に似ていなかった。
それでも他人は、ちいを基準にして話をしようとする。そんな他人にそのころの健太はうんざりしていた。
「じゃあ、お兄ちゃんがいなくなったのって私のせいだったの?」
そう聞かれてどきりとする。あのころはちいのせいだと思っていた。今でこそ違ったのだとわかったけれど。
自分ではどうしようもないことで比べられたりするのがとても嫌だったけれど、離れて眺めてみたら、結局ちいのその容姿も病気も、ちいにはどうしようもないことなのだ。
「だから、うーん。とにかくココから逃げたかったんだ。ちいのいないところにいけば、自分の好きなことができるはずだと思って」
両親は、ちいをひいきするようなことも、ちいのために我慢しなさいといったことも一度もなかった。家に居るときは絶対にどちらかが自分のことを気にしていっしょにいてくれたことも知っていた。
それはやはり、どうしてもちいに何かがあればちいを優先してしまう結果だった。
二歳になるまで入院生活をしていたちいに母はずっとつき沿っていた。その後もちいは何度も体調を悪くして入退院をくり返していたので、小さいころの健太の記憶の中には母親と一緒にいた記憶が少ない。
夜中に高熱を出したちいを両親が病院へ連れて行くのを何度も一人で見送った。
いっしょに行っても、何もない病院の廊下かロビーで待っているしかないのだから、それなら一人で家に居た方がよかった。
構ってほしいと思っていても、子供からみてもちいのことだけで大変な様子にわがままを言うことができなくなっていった。そしてそのうち本当に、健太は自分から何かを両親に求める方法がわからなくなってしまった。
でもどうしても気を惹きたくて、保育園で仲のよかった子がカベにらくがきをして親に叱られたと言っていたのでやってみたけれど叱られなかった。
ちいが毎日のように、性懲りもなくなにかやっては叱られている様子をみて、健太も同じようにしてほしかっただけなのに。
そう言えばそのとき、なんで怒らないのと泣いた健太にビックリしていたのは両親のほうだったか。
さすがに全部覚えていられたわけではないけれど、泣く自分に父親は理由をちゃんと説明してくれた。健太もわからなかった泣き出した理由も理解してくれて、もっとやりたいようにしていいと、あの人たちは言ってくれたのに。
あのころの自分は、まだそれを理解できなくて。
弱くて守るべきものだったはずのちいのほうが先に、親離れしてしまったことが悔しくて。
ちいのようになんでも、何度反対されようとも自分の意志を両親に伝えることが、健太にはできなかった。
なんでも好きなことが言えるちいがうらやましかった。上手く願いが伝えられない自分がもどかしかった。
ちいのようになりたいと思いながら、それでもちいのようにはなれない自分がいて。
「僕は僕が一人でちいに嫉妬してるのを認めるのもいやなくせに、全部ちいのせいにしたら楽だったんだから、うん。逃げてたんだろうなぁ うまくいえないんだけど、たぶんこれはちいのせいじゃなかったよ。ゴメンネ。バイバイも言わないで居なくなって」
「だって……」
どう聞いても自分のせいだとしか思えなくてちいが下をむく。ちいがちやほやされることに気をよくして芸能界になんかに入らなかったら、健太はずっと家に居たかもしれないのだ。
「だれも僕が居なくなったのはちいのせいだって言わなかっただろ? ウチの大人たちはだれもそんなこと思ってなかったんだよ。それに僕、ほんとあっちの水が合うって言うか、誰にもまだ言ってないけど、僕が継続的に落ち着く場所はここじゃないって思ってるんだよ」
細い指でちいの頭をぐしゃぐしゃになでて健太が笑う。
「すごいわがままだってわかってたから、どきどきしたけど、お父さんはちゃんと聞いてくれた。でも離れてから考えたのはやっぱり家族のことばっかりで、僕はちいのこと好きだったんだってわかったよ」
あの時の自分の決定が本当に正しかったのかどうかは、今でもわからないけれど、絶対に正しいものはないことがわかった。
その代わり、絶対に自分の中で消えない何かもゆっくりと掴むことができた。
「こう言うことを言っても平気だってわかってるから、ちいが本当の事を聞きたいと思ったから僕は答えたんだよ。僕が家族と暮さないのは、嫌いだからじゃなくて、やっぱり離れてても家族だって思ってるから」
「私はー……」
放っておいたらいつまでも髪を触られつづけそうで、両手で健太の手をどける。けれど視線はまだあわせられなくて、ちょっとした向きのままでちいが言葉を続ける。
「私はさ、ほんと、今まで家族と離れてて、今いっしょにいて、いっしょがいいなってやっとわかったの。お兄ちゃんもう、なんていうか、こう言う一時帰国じゃなくて、帰ってこないの?」
「え? 今回はすぐイギリスに帰ったりしないよ。言ってなかったっけ?」
「は?」
「二年くらいいるつもり。そのあとのことはまだきめてないけど、夏にちいに逢ったらなんだか、日本が無性に恋しくなっちゃって、即申請して、年明けからちいと同じ大学に通うんだよ? お父さんたちには言っといたんだけど。あ、そっか、僕自分で言うから言わないでって頼んだんだ。そう言えばちいとメールやり取りしててもそれは言い忘れてたなぁ」
軽く笑い飛ばす健太をあっけにとられた表情のちいが見つめる。カゴがしなるほど入った本を数えて、健太はこんなもんかなと、呆然としたまま動けないちいをおいてすたすたレジへ向っていく。
「まあでも、学舎が違うからなぁ ちいはスキップとかしないの?」
取り残されたことに気づいて慌ててついてくるちいに、首だけひねってしれっと話題を変える健太に、ちいが追求することを諦める。
「しないつもり。今まで勉強する時間ギリギリ削って生きてきたから、余裕を持ってやりたいの。スキップなんてしたら、全然遊べないわ」
「それもそうかも。僕なんか、勉強以外することなかったから仕方なかったんだよなぁ それに、法学のちいとは全然ちがうから、ちいが来てもあんまり意味ないかな」
言葉の壁をものともせずに、健太はすでに向こうで大学の課程を二つ修了している。目下本人が楽しんでいる学問は教育学だ。
「お兄ちゃんはね、コロコロ志望変えすぎ。結局お父さんたちとおんなじこと勉強しててたのしいかなぁ」
「あの人たちのやってるのは『教育』僕がいまやってるのは『教育学』教育をひたすら学問するんだよ。楽しいよ、どんなに一生懸命考えても考えても、答えがでないのって」
「ああー私、そういうのいや。サクっと答えを出さないと次に進めないもん」
答えが出ないなんて、そんなもののドコが面白いのかわからないらしいちいが頭を抱えて横に振っている。
「ちいの頭って数学向きだよね。僕はすぱっと答えがでるより、ぐるぐる考え続けることのほうが好きみたい。そっちのほうが、可能性がたくさんある気がしない?」
答えがひとつしかないものより、たくさんあったほうが楽しいと健太は思う。いろいろなことをたくさん考えて、一番いい方法を探す楽しさは、なんとも表現しがたい。
「あ、そうだ。おばあちゃんに頼んどこう。日本が終わったらこんどはアメリカかヨーロッパのどっかの国の教育学もやりたいんだ。ウチのおばあちゃんってコネいっぱい持ってるからいいよねぇ」
「それはお兄ちゃんにとって、でしょ。知ってる? 日本の大学の学食は高くて少ないんだよ。あっちみたいにタダで何でも食べさせてくれないんだよ。お兄ちゃんみたいに生活費を全部本につぎ込んでたら餓死するかもしれないじゃん!!」
のほほんとした健太に、一番の心配事を口にする。
「大丈夫、家にいたら何かあるから。あ、そうだ。今日はお寿司がたべたいなぁ」
「お寿司!? 晩御飯はホットケーキだって言ったじゃない。この本少し返してさっきのお金分けてくれたら考えるよ」
もちろんホットケーキにするつもりはないけれど、寿司にするつもりもないちいがそう言うと、健太がこの世の終りを告げられたかのような顔でちいのほうを見つめている。
「………わかったから。スーパーで買ってあげるから。いやそうな顔してもそれ以外はだめだからねっ お兄ちゃんみたいになんでも丸呑みするような人に高いもの食べさせられないもん。イギリスのときもっ あのお店、日本ででてるガイドブックに載るくらいすごいところなんだよ? 三人前のパスタ皿食いして店員さんが笑ってたでしょう!?」
レジを済ませた健太と、持ち手をもったら伸びて切れそうな本屋の袋を、仕方なく持ち手をしばって二人で抱えながら店を出る。
一人で三人前全て食べたわけではないけれど、みんなで少しずつ取分けた分を食べた健太がそのまま大皿を抱えて、他の人間がとりわけた分を食べきる前に香辛料のカケラも残さず平らげてしまった。
「あれはおいしかったなぁ 教授のおごりじゃなきゃあんなお店一生行けないもん。食べとかないと」
「ならもっと味わおうよ、急いで食べないで」
向こうで健太が世話になっているという教授の家族と滞在中何度か一緒に食事をした。といっても、奢ってもらっていたのだが、今食べておかないと三日は何も食べられないぞという勢いで食事を摂る健太に、あっちはもう見慣れたものなのだろうが、ちいはびっくりしてほとんど食べられなかった。
「時間もったいないでしょ」
「食べるものはもったいなくないの?」
「オナカに入っちゃったら一緒。でも、栄養剤とかはキライ。食事は食事だからね」
もともとすごく強情な部分のある性格だったが、イギリスで一人暮らしをして一層磨きがかかったようだ。
「じゃあもっと、規則正しく食べようよ」
駐車場の端にとめていた車の、後ろのドアを開けて荷物を乗せて、ちいが大げさにため息をついている。
「コレはイガイだったなぁ」
ちいの乗っている車をたたきながら健太がつぶやく。急旋回するように話題を逸らす健太にちいがついていけずにナニガ? という顔をする。
「?」
「車。ちい、実冴さんのスポーツカーほしがってたでしょ 小さいころ。だからてっきり、真赤なスポーツカーが出てくると思ったのに」
マシンガンの一点連射さえ防ぎそうなくらい頑丈な鉄の塊と言った感じの車体はクリーム色で、荷台は健太の背丈ほどまでが同じ装甲に覆われ、その屋根には同色の幌までついている。
タイヤはちょっとしたクギくらい刺さってもヘイキそうだし、後部シートはそのまま軍隊で使えそうな進行方向に直列二列のベンチ型で、今は誰も乗らないのでたたまれているためトラックのような状態だ。色さえ緑か迷彩だったら、そのまま戦場でもつかえそうな車に、ちいは乗っている。
「だって、みんな持ってるんだもんそういう車。コレいいでしょ。護送車みたいで。今度後ろに乗ってみる? サス硬いからおしりすれるの」
「護送はちょっとエンリョシマス」
運転席と助手席も、実用を重視されたデザインで、お世辞にも乗り心地がいいとはいえないのに、こんな板にスポンジを張っただけのイスに座るのは、絶対遠慮したい。
「こんなの買って、お父さんになんか言われなかった?」
「ううん。コレ買ったーって見せたら、ふーんって言った後、キー奪われて。お父さん三時間くらい帰ってこなかったよ。あっ! そういえばこの子くらいか!? お父さんにモンク言われなかった買い物」
ドアの上部にある取っ手を掴んで軽がると体を持ち上げて運転席に収まるちいと、まだ少し勝手がわからないらしく這い上がるように助手席に乗り込む健太。
この子といいながらキーをまわして、エンジンをかける。
「うー お父さんの基準がわからないわ」
「わからないけど、スポーツカーだったら怒られてたと思う。なんとなく」
「う」
車も実用的なら、内装も実用的だ。このご時世本当に必要なのかわからないが、無線機までついている。
オーディオもかなりレトロな外装で、最新の記憶メディアに対応しているのか怪しい雰囲気だ。
エンジンが温まるまで待つのか、ちいはまだ車を動かさずに、飾りではないらしいツマミをまわしてラジオの選局をして、健太の知らない、ラジオから流れる日本の流行の歌を口ずさむ。
「ナニ?」
「いや、なんでもないんだけど」
黙りこんで自分を見つめる健太に、ちいが尋ねるが、健太が珍しく歯切れの悪い受け答えをする。
「この歌ね、廉ちゃんが歌ってるんだよ。いまウチの事務所のイチ押しアイドル」
「廉ちゃんって、樹理ちゃんとこの廉ちゃんだよね? へぇ女の子の歌かと思ったけど」
本人がなりたいと言ったから、というある意味当然の理由で廉が父親と事務所にやってきたのが去年の夏。それから歌にダンスにとレッスンを重ねて、デビューしたのが今年の夏。
「うん。女の子のカッコしてアイドルやってるの。面白いよあの子」
ベンチシートになった運転席と助手席の間のシートを上げると、二十世紀の映画に出てくるような車の内観とはかけ離れたオーディオシステムが顔を出す。ストッカーの中から取り出された五枚の記憶メディアは、プラスチックで加工され、白やピンクのかわいらしい衣装を着て笑っている廉の姿がプリントされている。
「……だまされてる?」
「否定はしないけど、本人もアイドルってのはこういうもんだと思ってるから、構わないんじゃないの? ヤだって言うのを無理やりするような人じゃないし。ウチのシャチョウ。廉ちゃんの曲聞いてみる? どれもこれもすっごくカワイイよ」
再生される廉の曲に健太が黙り込んだ。確かにすごくかわいくて車内モニタのなかでくるくる踊っている廉は、歌もダンスも上手だ。
上手だが、廉は男の子だったはずだ。彼に会ったのは五年前に帰国したとき一度だけれど、そのときの廉のイメージはものすごく内気で静かな子、というカンジで、ずっと樹理の後ろにくっついてとうとう健太は一度も口を利いてもらえなかった。
ちゃんと、男の子の服を着ていて、どう見ても男の子だったのに。
「美少年アイドルより、美少女アイドルのほうが受け入れられやすいからってのが、実冴さんの言い分。だから、RENって名前と年以外は全部シークレット。どうせ廉ちゃんは六つまで外国にいたし、学校は北條のところで、しかもほかの習い事の関係で普通の子とは別のカリキュラム受けてたことが多いから、バレないと思う」
それに、学校での廉はいつも下を向いていて、ほとんどしゃべらない物静かを通り越して暗いイメージのある子だった。まさかこんなことをしているとは、ダレも気づかないだろう。
歌っている廉に合わせて、ちいがまた歌いだす。
「ちいって、ちっちゃいころからいつも歌ったり踊ったりしてたけど、あのころからステキ変調変わってないね。あ……ゴメンナサイ」
「いいけど。わかってるから。でもすごいんだよ、廉ちゃん今年だけで四曲シングル出してるんだけど、一曲ダブルミリオンでほかも全部ミリオンなの。この間だしたアルバムもガンガン売れてて。そしたら作詞にちょろっと加わっただけで印税ごっそりはいってくー……るっ……らしいの」
苦しく語尾をごまかして、えへらっと笑うちいに、健太もにっこり微笑む。ムリにごまかしたことで、ちいが両親に内緒で稼ぎを増やしていることを察した健太の、いろいろ複雑に混ぜ込んだ裏のある微笑にちいの顔が唇を上げた形のままひきつる。
「へぇ そんなこともやってたんだ? じゃあホントにお金持ちだね、ちい。僕、おすしはトロとウニとイクラだけでおなかいっぱいになりたいな。みあを連れてはでられないから、前にしたみたいに板前さんウチに呼んでー……」
「いくらすると思ってんのよ、それっ」
五年前に健太が帰ってきたときも、彼は寿司が食べたいと言って、それを聞いた実冴がおごってくれたのだ。四家族居たので仕方ないのかもしれないが、実冴が散財したと苦笑いするほどの事件はちいの中であの時以前も以後もない。いくらかかったか怖くて聞けなかった。
「シラナイ。でも出前だとほら、せっかくのおすしが……やっぱり、握りたてがおいしいよね? おいしいもの食べたら、いらないことなんかわすれちゃうよね?」
「わかったわよっ………高いの食べさせてあげる代わり、一貫食べるのに最低一分は使ってよ。ああそれより、ゆっくり握ってもらえるように頼もう」
廉の歌を流したまま、画面をユーザモードに切換えて、ちいがラインの向うのオペレータに何かを注文した後、車を発進させた。
「すごい。ちい、有人通信使ってるんだ」
レトロな無線機の形をしたオンラインシステムが、一転して最新の通信機になる。オーディオといい無線機といい、妙なところに凝っている車だ。
「機械より人のほうが融通が利くし有能で早いんだもん。慣れたら戻れないよ。あとハッタリにもなる。機械じゃキャンセルされても有人だとオッケーってところもよくあるよ」
一般に普及している個人向けのオペレートシステムは機械による大量処理だ。秘書を一人雇うようなもののような、ムダに人件費のかかる有人システムは、限られた人しか利用していない。余裕を持って対応できるようオペレータ一人の処理上限が低く設定されているので、世界中で空きを待っている状況だから、誰でも使えるシステムではない。
申し込みの早い遅いではなく必要とする人を管理会社が選ぶので、必要度が低いとみなされた人物は一生待っても使えない。予約リストに載るだけでも大変なことらしい。
なので、普通の人は自分の端末に生身のオペレータから通信が入ると、なにごとだろうと身構える。一生縁のない人もいるはずだ。
今回出張を依頼しようとする店は予約さえ有人システムを介しないと取れない。
「有名人って感じだねぇ」
「仕方ないよ。セキュリティの行届かないヤツ使えないもん。げ。通った。断ってくれたら良かったのに」
出張予約が受けつけられたことを知らされてちいが向こう側からの料金設定と今日の食材を聞きながらなるべく安くあげようとしている横で健太があれもこれもと口をはさむ。
「もうっ! お兄ちゃんは黙っててよ」
「やだ。うに。ウニたくさん。さっき言ってた小樽から採れたて空輸のをいっぱい」
「やめてーっ」
登録のときに健太のデータを家族利用者として加えてしまったことが間違いだった。準利用者として健太の質問や意見をオペレータがにこにこ相手に通してしまっている。
『ウニについては取消しされますか?』
「はい!!」
「えー あのさーオネーサン、廉ちゃんって知ってる?」
「ごめん、取消しを取消し。ああもうナニがどうだかよくわかんなくなってきたっ! 画面分割して今までの履歴プリーズ」
オペレータが絶対にプライベートな情報を漏らさないよう教育されていると知っていても、やはり知られるのは拙(まず)い。舌打ちをしながら、ちいが健太をにらむが、健太は軽くさわやかに笑ってごまかしている。
ご注文一覧にステキな品目がステキなお値段とともに表示された。先ほどから同じようなやり取りをくり返しているためか、オペレータは少し前の取引から取消しを通知していなかったらしく、履歴の途中から無駄な通信はない。
「おー」
「げ」
目をキラキラさせてそれを見る健太と、もう見なかったことにするためにセミオートだった運転を手動に切換えて前を見ることに専念するちい。
「もういいかな」
「いいにしといて! だいたい、嬉々として妹に集(たか)る兄なんて、どこにいるってのよっ」
「いるでしょココに。やっぱり持つべきものはお金持ちの妹だよねー じゃあコレでお願いします」
「朝ご飯はぜったい、ホットケーキだけだからね。ホットケーキミックス五キロくらい家に届けて。牛乳と玉子も適当に。いつものお店に注文」
『了解しました。復唱します』
流れるようなオペレータの声を聞きながらちいはアクセルを踏みこんだ。
わずかな停車時間に後部シートの半分以上を使っておかれたベビーシートの中を覗いて、みあが寝ていることを確認した夏清がよっこいしょとつぶやいて前に向き直る。
「ん? なに?」
「……べつに」
じっと見つめられて、なんなのよと夏清が聞き返そうとしたとき、車内に控えめだがそれとわかる電子音が響く。
「ちいだわ。あの子から連絡なんて珍しい」
「珍しいどころかしないだろうが、いつも。あれは。……やっぱりな」
井名里ちい様からご両親へメッセージです、というアナウンスのあと再生された音声は、どう聞いても健太だ。晩御飯はちいのおごりでウチでお寿司だよと浮かれた調子で喋っている。
「肉は明日か」
「わからないよ。明日はホットケーキかもね」
転がらないように気をつけながら足元においていたメイプルシロップのビンをひざに乗せた夏清が、大きなビンを手に持って笑う。
ちいが六つになったころ、病気の状態も安定してきたのでと、初めて行くことになったネズミの国へ、熱を出してしまっていけなくなってしまったことがある。
微熱だったので必死にヘイキだもんと言っていたが、大事を取ってちいは連れて行ってもらえなかった。
礼良と健太が行ってしまうのを見送ったあと、熱が上がるのに大声で泣きながら家の中をうろうろと歩き回っていたちいにつくったのがあのホットケーキだ。それから毎日毎日、ちいが飽きるまでネズミの顔の形をしたホットケーキを焼きつづけた。
ちいは偏食家で、あれが食べたいこれが食べたいと言う割に食が細かった。
「ちいは何かにハマったらそればっかりだからな」
「そうそう。なにかおいしいものにあたるとそればっかり。あの子はなんでもほしいものをほしいって言ってくれたから、今思ったら健太より簡単だったのかも」
思い立ったら手に入るまで駄々をこねつづけるちいにはいつも手を焼かされたけれど、逆に健太は何かほしいものがあっても親の方が聞いてやるまで言いださないタイプだった。
こちらから『どうする?』ときいて、やっと自分がやりたいことやほしいものを言う。しかし大抵の場合自分で決めてしまっているので、こちらが意見しても聞きいれない。
「どっちもどっちだろう」
「……それもそうかも」
他人の中でもまれてきたおかげか、離れて数年で健太は人との距離をちゃんとつかんで、自分の世界を持って、多少のストレスも笑ってかわせるくらい成長していた。
なにかあるとすぐに熱を出して泣いていたちいは、気がついたら少々のことでは折れそうにないくらい丈夫に育っていた。
礼良は何も言わないけれど、自分たちで育てていたら健太もちいも、あんなふうにならなかったと夏清は思う。
自分たちの元から離れていくことに戸惑わなかったわけではない。
二人ともタイプは全く違ったけれど、違うなりに心配事は二人それぞれ、同じようにあって親である自分たちはどんどん守りに入っていた。
子供に何かあったらどうしようと思うのは、おそらくどの親も同じだと思う。自分たちだけが特別だったとは思わない。
子供の可能性までぷちぷちと摘み取っていいものではないと、楽しそうに実冴にくっついて仕事をしているちいをみて反省した。
健太の家出に近い留学も、最初はさすがに反対したけれど、あれだけ『ちいが嫌い、いっしょに居たくない』と言っていたのに、離れて暮らして、会うたびにいつも成長していて、今ではすこぶるご機嫌でちいと喋っている。あのころがウソのように普通のお兄ちゃんで、無理をしている様子もないどころか、ちいといるとおもしろいと日本に帰ってきてしまう始末だ。
やっぱり、本人の希望どおりさせてよかったんだと思う。
でも、自分ひとりだったら、どれも選択できなかった分岐点ばかりだ。
「どうした?」
聞かれて、自分がじっと運転している礼良を見ていたことに気付く。なんでもないといいかけて、言葉を飲みこんで、夏清は改めてはぐらかすように微笑んだ。
道の両脇に建っている家が、大きな屋敷ばかり目立ち始める。病院からは十五分くらいしかかからないので、すぐ、もう見慣れた門が見えてきた。
門と言っても、昔あった鉄の柵はない。自動開閉装置が壊れたとき取ってしまった。ただし、物理的にさえぎるものはないが、門柱には赤外線のセンサーと記録装置が付いているので、物や人の往来については全て管理されている。
その門柱を通り抜けて、玄関に車を止めても夏清は何も言わないでニコニコと笑ったままだ。
「ナニ企んでる?」
シートベルトをはずしながら、夏清がまだ寝ているみあをちらりとみる。
「企んでなんかないよ」
車から降りようとした礼良の袖をこっちを向いてとひっぱる。
「この子はどんな育ち方をするのかなって、思って」
車が止まってもなお眠りつづけるみあを二人で前部シートの間からしばらく眺める。
「育つように成長するだろう。体中に不確定要素がつめこまれてるんだ。こっちの思い通りになんか行かないのは上の二人で身にしみた。ゆっくり構えてないと身が保てるか」
「ちいがね、私たちは余興かい、って。確かに離れてても、子供がいたら退屈しないよね」
「いっしょに居たら退屈どころか」
忙しくて仕方なかった。特にちいが小さい頃は、忙しいどころの騒ぎではなかった。精神的な疲労が肉体を圧迫するような感覚。あってないような睡眠時間。幾度か乗り越えた危機的状況。
過ぎた今だから余裕もあって、客観的にその頃の自分たちを見ることができても、あの頃は毎日が戦争だった。
けれど、二人だったから、なんとかやってこられた。
いい経験だったと思えるのは、やはり今が恵まれているからかもしれない。
「それがいいから、この子産もうと思ったの。そしたら、上の二人も家に帰ってきたでしょう? きっとね、みあが一人じゃ寂しいから呼んだのよ、あの二人まで。家族がみんなそろうの、すごく久しぶりでわくわくしてるの」
夏清が礼良の首に両手をかけて、首を少しかしげて笑う。目が『そう思わない?』と問いかける。
「あらためてね……」
「惚れ直した?」
「ううん。産んでよかったなって」
さえぎるようにかけられた礼良の問いを、夏清が間髪を居れずに真顔で否定したあと、舌打ちが聞える前に言葉を続ける。
「いつもそのとき限界で惚れ続けてるから、惚れ直してるヒマなんかないもの」
「そうか? 俺はいつもその都度何回も惚れ直してるけど?」
モノは言いようだといわんばかりに返されて、夏清がこらえきれずに笑い出す。
「ほんと、先生って」
「お前まだそれで呼ぶか」
「うん。先生が私のことお前って言う限り。で、先生は私が先生って呼ぶ限り。だめよ。もう二人とも無意識なんだもん。子供の前では呼ばないようにしてるんだけどな」
二十センチと離れていない、息がかかるほどの近さで、お互いに聞えるだけのささやき。
「じゃあ、礼良サンって呼ぶの、またやろうかな」
これまでに何度か呼ぼうと試みて毎回大抵三秒で挫折している呼び方。三秒で挫折する理由は、言った後夏清が笑い出してやっぱりダメだと諦めるからだ。
もちろん今も、すでに唇の端を震わせて笑うのをこらえている。
「自分で言って一人でウケてどうすんだよ」
「いや、もう、ダメ。やっぱりムリ」
おでこをくっつけて、夏清が目を閉じる。同じようなセリフをくり返しながら楽しそうに。
「しわ増えたか?」
「わ。それ、自分の顔鏡見てから言おうよ。言っとくけど、私はまだぴちぴちだからね。笑いじわだもの」
顔を離して、夏清が心外だわと言う顔を作る。鏡を毎日見ているとあまり気付かないけれど、家中のいたるところにおかれた家族の写真を見ると、言われなくても礼良の方がさくさくと年齢に比例した外見状況が進行している。
「ハイハイ」
「でもねぇ」
夏清が首に回していた腕を引いて、細い指で礼良の顔を触る。
「どうしてかしら、今目の前にある顔が、やっぱり、今一番カッコいいって思っちゃうのね」
「そりゃあ」
夏清の腰に回された腕が引かれて、心もち、体が前にひき寄せられる。
「惚れてるからだろ」
「惚れてるからかな」
言葉が重なって、どちらからともなく顔が近づく。
こんなに単純で簡単で、でも大事なことがすれ違わないでいられることが、幸せなことだと知っている。
交わす口付けは、初めてのときと変らない温もりと安らぎ。
何度も、何度でも、何回でも。
いつも、いつだって、いくつになっても。
こうしていたいと思えることが、なによりも。
時間は、少しずつ変化を続けながら、いつまでも続く。想いを乗せたまま、とぎれることなく。
2003.3.01=fin. |