|
恋におちたら 1
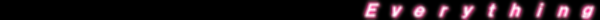
ああ、朝だ。と思う。目を閉じていてもまぶたの後ろにやわらかい光が差し込んできて、あたりがもう明るいのがわかる。
指にかかる柔らかい猫のような毛。猫?
ゆっくりとまぶたを開ける。少し閉め忘れた遮光カーテンの隙間からお日様の光。白とグレーの部屋。ココはドコだろう。腕の中には、黒に少しの茶色を混ぜたような、自分の物とは違う色、質感の髪。人?
広いベッド、肌触りのよいシーツ。軽いけど暖かい羽毛ふとん。指先まで覆う銀にも見えるつややかな光沢の、シルクのパジャマ。
そこまで確認して、頭が一気に覚醒した。腕の中の人物も、目を覚ましたのか、腕の中に埋没していた頭がゆっくりと動いて、顔がこちらに向かう。
目と目があって三秒。
瞬きも忘れて至近距離で見つめあってから。
「おは、ようございます」
さらに三秒ほどの間を置いた後、おはようと答えが返ってくる。
一緒に暮らしていた頃、毎朝顔を合わすたびに樹理が哉に言っていた言葉。言葉達はいつも一方通行だった。それが返ってきたのははじめてだ。
落ち着いていたのもそこまでで、哉が体を動かした瞬間、その両腕が自分の腰あたりから引かれる摩擦に、お互いの体勢を再認識して、一旦止まった思考回路が動き出すと同時にパニックが加速する。
「え? えっ!? ええぇ? あれ?」
ベッドから降りた哉の背中を見ながらバネのように跳ね起きて、ベッドの上にぺたりと座り込んだまま樹理が、何かつぶやきながら広がった柔らかい髪を撫でつけたり、袖丈の合っていないパジャマの長さを確認したり、シーツのしわを伸ばしたりをランダムに繰り返す。
「あああっ!」
最終的に頭を抱えて樹理が大きな声を出す。
「どうした?」
誰かが突っ込まないといつまでも終わらなさそうな樹理の独り言に、シャツに袖を通していた哉が、振り返って聞き返す。
「……朝ごはんがないです」
どうしようと続けながら、樹理ががっくりと両手をついた。
パニックを起こした人間の動作にしてはかなり緩やかな樹理の動きを観察しながら、どうしたものかと考えてみる。
そしてどう考えても、樹理には現状が見えていない。なにも。でなければもっと早くに悲鳴を上げていたはずだ。哉はいつもどおり、下着一枚で寝ていたのだから。絶対に見ていたはずなのに、見えなかったものとして処理されたのか、樹理は無反応だった。
その極みというか、どこか一部分だけが動き出したのか、樹理の朝ごはん発言に枕元におかれた時計を指差した。
「あ、あっ! ああー!!」
信じられません、と一言つぶやいて、樹理がぱたりと突っ伏した。秒針を滑らかな動きで運ぶ見てくれだけのアナログ時計は、短針を十と十一の間に、そして長針を五のあたりに進めている。つまり、今はすでに午前十時二十五分だ。
「もう、こんな時間だなんて」
「朝というより……昼飯だな」
ジーンズに足を通し、ベルトを締めた哉の一言に、何とか体勢を建て直し、起き上がったのもつかの間、ぱったりと羽毛布団という名の海に沈む。現状を現状のまま表現したまでだが、どうも樹理の急所にクリティカルにヒットしたらしい。
「どこかに食べに行けばいい。電話をかけてくるから、とりあえず……着替えて」
「……ハイ」
今後の見通しを伝えると何とか正常な活動能力を取り戻しつつありそうな樹理を寝室に残して、哉がリビングへと出て行った。
少し季節外れの、昨日着ていた服を着て樹理が部屋を出ると、哉が受話器を置くのがみえた。何かメモを取っていたらしく、ペンを片手に哉が振り返った。
「あと少し電話する先があるから、洗面所先に使って」
「ハイ」
頭が大爆発だった。少々櫛を通したくらいでは到底収まりきらないくらいぼっさぼさだ。蛇口をひねって勢いよく水を出し、顔を洗って気合を入れる。
幸いピンもゴムもヘアワックスも洗面台の引き出しにまだあった。とにかく早くと自己最高記録更新かもと思いながら、二つに分けて高めの位置でまとめ、三つ編みをしてピンで留めれば、先ほどまでの広がりをなかったことにできた。
「よし、なんとかなった」
歯を磨いて、もう一度顔を洗って一息つく。そしてまた鏡を見て、あのものすごい頭をみても薄かった哉の反応ってどうなんだろうと思う。
「気にしなさすぎ……」
それとも自分が気にしすぎなのか。
「樹理」
「うひゃ」
ぴょこんと一跳ねして樹理が振り返る。
「あ、や、もう電話、済んだんですか?」
「ああ。樹理も家に掛けておいたほうがいい」
「え? あ、ハイ。そうですね。うん」
家。哉に言われるまですっぱりきっぱり頭の中になかった単語だ。なんとなく事情を察していそうな母はともかく、父は心配しているだろう。
哉と入れ替わるようにリビングに戻って、自宅の電話番号を押す。一つ押すたびに、心拍数が加速する。
三コール目で聞きなれた母の声が聞こえた。
「えっと、ママ?」
『樹理? 帰ってこなかったから聞くまでもないかもしれないけど、どうだったの?』
「あ、うん、氷川さんちに泊めてもらいました」
『そう』
「あの、パパは?」
『いるわよ、横に。代わる?』
後の一言は息を潜めて隣にいたらしい父に掛けられた言葉なのか、あわただしく何かが去っていく気配が電話を通してもわかる。
『あ、逃げたわ』
「……ママ……」
『で、どうするの? 一度帰ってきなさいね。いろいろ話したいし』
「うん、あ」
ふと隣を見ると、身支度を終えた哉が立っている。男性の支度はどうしてこんなに早いのか。
「えーっと、氷川さんに代わります」
『ちょっと、樹理っ』
母のあわてたような声が聞こえたが、父で遊んだ罰だと思うことにして、受話器を渡す。
短い挨拶の後、哉が今日の夕方二人で行くことを伝えて受話器が返された。レスポンスは必要最低限。哉の人生には回り道や余韻という言葉はないらしい。
「というわけです。ハイ」
『らしいわね。ええ。わかったわ、待ってるから』
「うん。じゃあね」
みずみずしい若葉を茂らせた街路樹が流れるように過ぎ去っていく。前にこの車に乗ったときは夜で、よくわからなかったけれど体感速度がとても速い。高速道路なんかを走らせればもっとすごい速度が出る車なのだろうけど、ここは一般道で信号もあり、ほかの車も走っている。休日のせいか比較的車が少ないが、普通の速度のはずなのに、視点が低いせいもあって飛ぶようにという表現がぴったりくるような速さだ。
フロントガラスから見上げれば、抜けるような青空。絶好の洗濯日和だ。こんな日は朝から3回くらい洗濯機を回して、シーツやリネンの類いを干すとなんだか気分がすっきりするのだ。
本当に、もったいない。
一般的な女子高生とはかなり後悔する場所が違うことなど本人は全く意識することなく、ため息より短い息を吐く。
そんな樹理のことなどお構いなしで、車は見るからに高級そうな……樹理でも知っているようなブランドショップが軒を連ねる界隈をゆっくりと進む。
速度が落ちて景色の流れ方が変わったことで、樹理が哉の方へ視線を向けた。ここが目的地なのか? どう見ても食事どころというよりは服飾店舗が中心だ。
銀色のスポーツカーが大きく葉を茂らせた街路樹の下にある路上パーキングに止められた。
「ここ、ですか?」
「ああ」
困惑したような樹理の問いかけに哉がさらりと応えて二人分のシートベルトをはずし、車から降りた。
樹理も降りようとドアに手を掛ける。が、次から次へと通り過ぎる車に、ドアを開けるタイミングが合わない。
結局、見かねた哉がドアを開けてくれなかったらいつまでも降りることができなかっただろう。
「すいません」
緊張すると対人対物を問わずうまく間合いをあわせられないことは自覚しているが、情けない。
申し訳なさそうにしている樹理を見下ろして、哉が嘆息する。
「……車を替えるか……」
「近くに空きがなかったから、ちょっと歩く」
「ハイ」
言葉が終わらないうちにすたすたと歩き出した哉を樹理が小走りで追う。追いながら、ショーウインドウを覗く。ゼロをたくさん並べたタグをつけた服や靴、バッグがきれいにディスプレイされ、きらきらとまぶしい。
本当に少しだけ歩いて、哉が目的の店の前で振り返る。きょろきょろと余所見をしていた樹理は、二店舗ほど後ろだ。
慌てて走ってきた樹理が、哉よりも少し手前で失速した。原因はガラスの向こうでマネキンが来ていたドレスだ。ワンピースと呼ぶには着ていく場所を選ぶであろうその服は、ドレスと呼ぶにふさわしい。
三秒ほど時間をロスして、哉のことを思い出し、やっぱり慌てて走る。
「すいませんっ」
哉は応えずにドアを押す。自動ドアではなく、ドアの枠に花や天使が彫金された観音開きのドアだった。
哉の影になるように続いて入った樹理が、店内を見上げてぽかんと立ち尽くした。
広い店内は通りに面した一角が三階部分までの高さすべてガラス張りになっている。二階へは、中央に優雅な曲線を描いた階段で上れるようになっていて、その上は白い壁だ。
一階では、洋服がこれでもかと、ひらひらとゆれている。どれもこれも十代から二十代前半の女の子の、それもクラシックな余所行きの装いのための洋服だ。
「えー……と……」
「いらっしゃいませ」
樹理の問いかけは、店に負けないくらい優雅な装いと身のこなしの女性に遮られた。
哉と会話を交わした女性が向き直り、にこやかに、けれどもしっかりと樹理の頭からつま先までさっと視線を動かす。
「お嬢様、お好みはどのようなものが?」
聞かれても、そもそもここに何をしに来たのか知らない樹理にはどう応えたらよいのかわからない。救いを求めて哉を見る。
「この夏の新作から合いそうなものを」
「かしこまりました」
訳がわからないまま店の二階に案内され、しみひとつない白いテーブルクロスがかかったテーブルに着くと、母が『とっておき』にしているのと同じ柄の(けれどももっと高価そうな)ティーカップが音もなく目の前に置かれる。
流れるような手つきで紅茶が注がれた。テーブルの中央に砂糖とミルクピッチャーが置かれていたが、白磁のカップの中でたたずむ琥珀の液体は、そんなものを入れるのはもったいないくらい上等な香りがする。
「……氷川さん、ここ……?」
小さな声で恐る恐る尋ねる。どう考えても成人男性がひいきにしている店ではない。というより、哉がこんな店を知っているということ自体が信じがたい。
尋ねられた哉は、出された紅茶を一口飲んで少しだけ口角を上げた。
「出る前にいろいろ電話をしていただろう」
「ハイ」
「理右湖さんの紹介だ」
「はあ」
いったい何の為にこんな店に来たのかと言う意味で問うたのとは、全く違う方向からの応えに樹理があいまいに相槌を打つ。
しかし、いろんな意味で実用的なものしか必要としない雰囲気の神崎家からはこの店は想像しにくい。確かに診療所をしていて、医者である以上それなりの収入があってしかるべきなのだろうが、そんなに贅沢な印象はない。複雑な表情の樹理に、しばらく黙って紅茶を飲んでいた哉がさらりと言った。
「あの人は昔本物のお嬢様だったから」
飲みかけた紅茶をこぼしそうになった。
「とは言っても、この店は彼女が足しげく通っていたころとは場所も変わっているらしい。だからちょっと手間取った」
手間取ったって何がだろう。
脳に神崎家の件に関しては思考停止を言い渡して、とにかく紅茶に集中する。幸いにもとてもおいしい。銘柄には詳しくないが、きっと上質の茶葉を丁寧に淹れている。哉の答えが思いも寄らない方向へミサイルのように突き抜けてしまって、始発点に立ち戻れなくなり、樹理は自分が何を質問したかったのかも思い出せないまま、黙って液体を嚥下することでそのまま突っ伏してしまいたい衝動をこらえた。
ゆっくりと紅茶を飲み、何とか心が落ち着いたところに図ったように先ほどの女性が現れた。
女性の後ろを見て、なんとか落ち着きを取り戻したつもりだったのに、なんだかぐらりと視界が傾く。女性の後ろには色とりどりの服がかかった移動ラックがついてきている。量が半端ではない。
「お嬢様に似合いそうなものを適当に選ばせていただきました。どうぞ、お好みのものがあればご試着ください」
にっこりと、だが有無を言わせぬような圧力に、樹理が立ち上がってふらふらとラックに歩み寄る。そして心の中でつぶやいた。
どれもかわいくて一枚なんて選べないです。と。
何かを選んで試着しないと後にも先にも進めない。とりあえず目に付いた若草色のワンピースと白いレースのボレロを手に、手伝いを断って一人で両手を広げてもまだ余るほど広い試着室に入る。
そっと値札を見る。三枚ほどついたタグの一枚、白いプラスチックのような光沢を持つそれに金箔押しの店名がカリグラフィーの流れるようなアルファベットで綴られていた。樹理のクラスメイトが……と言うか、中でも特上級のお嬢様方がこの店舗の名を何度か口にしているのを聞くともなく耳にしたことがある。友人同士の何気ない会話を装った自慢話は、声を潜めるどころか、みんな聞いてと言わんばかりによく通る。ブランド名もそうだが、さらに別のタグに書かれていたその金額は、そして見たことを後悔させるに余りあるゼロの数だ。
哉は多分、いや絶対お金持ちだ。前回嫌と言うほどその金銭感覚の違いを思い知っている。しかし、値札に書かれた金額を見て何か月分の米が買えるだろうか……とかとっさに計算したくなる自分が悲しい。
何気なく選んだボレロもよく見ると縫い目がないのだ。肩も袖も脇も。機械編みではなく手編みだ。編み目も恐ろしく手が込んでいる。これは高くて当たり前だと思う。
ふんわりとしたかわいい服は好きだ。
この店にある服はほぼすべて、樹理の好みのうちに入る。特にあのショーウインドウに面して飾られた綿菓子みたいなお嬢様然とした服は見ているだけで幸せな気分になれる。正直、クラスに何人かいる本物のお嬢様たちがちょっとだけうらやましかった。
こんなにかわいい(そして高価な)服を着られるなんて本当にうれしい。
しかし。と樹理は気を引き締めた。
その好意に甘えるのは、この一着だけにしておこうと。
「いかがですか?」
ボレロに袖を通したところで、外から女性の声がかかった。なかを見ているかのような絶妙のタイミングだ。先ほどの紅茶を飲み終えた際の声の掛け方といい、洗練された人は何か違う。
「はい、大丈夫です」
「失礼いたします」
カチリと音を立ててドアが開く。
「こちらをどうぞ」
下を見ると、樹理が履いてきた通学用の地味なローファーに替わって白いミドルヒールの靴が置かれている。
学校指定の靴だって、結構高かった。だから大事に手入れして大事に履いていたけれど、確かにこの服にあの靴は似合わないなと、言われたとおり履く。
「どうですか?」
先ほどと同じテーブルについていた哉の所へ戻って立ち止まり、じっと固まっているのは変かなとちょっと小首をかしげた。
「気に入った?」
「ハイ」
それはもう、もちろん。
「じゃあそれと……」
「ダメですっ!」
哉がラックにかかった服に視線を向けると同時に、樹理が両手を振って止める。
突然大きな声を出した樹理に、哉も店員も動きが止まった。やってしまったと顔を真っ赤にしながらも、今度はもう少し控えめな声で言う。
「これだけで十分ですから……」
蚊の鳴くような声と言うのはこのくらいのボリュームか。けれども樹理の声ははっきりと哉に届いた。
「本当にそれだけで?」
問いかけに耳まで赤くした樹理が顔を上下に振っている。
「あれは?」
そう言って斜め下を見下ろす。哉の視線の先にあるドレスは、立っている樹理にも見えるはずだ。
「あ、あんなのはっ……だって、着ていく場所もないし……」
しかし、そんな樹理の言葉に、哉がしばらく考えて、何か思いついたように納得してうなずいた。
「……わかった。着ていく場所があればいいんだな」
「え? は? ハイ?」
樹理から視線を移して、店員に尋ねる。
「表に飾ってある服、彼女に合うものはありますか?」
「こちらのワンピースがぴったりならスカートの丈を少しお直しすれば問題はないと存じます。しばらくお待ちください」
お嬢様はこちらにと他の店員が樹理を試着室に促す。
「よろしければ新しくいたしますが」
樹理を待つ間に二杯目の紅茶が冷めていた。
「いや、もう結構。この服は全部サイズは同じ?」
「いえ、ほとんどが七号ですが、少し五号と九号が。先ほどのワンピースは七号でございます」
立ち上がっていくつか手に取る。ほとんど同じようなデザインに見えるが、少しずつ素材や丈、レースやリボンが違うらしい。
ショーウインドウに見入ってうっとり顔をほころばせていたのに、店に入った瞬間、樹理は戸惑ったような表情になり、口が真一文字に結ばれてしまった。
店に入ると言うことは、買い物をすることを意味する。気に入ったものが店の外から見てあるのに、いざとなると拒絶するような顔になるのはなぜなのか。
樹理に服を。そう考えたのはこの陽気のせいだ。どう考えてもあの服は冬物で、この初夏のような日和には合わない。
しかしさすがにどこに行けば買えるのかわからなかったので、詳しそうな人と言えば理右湖しか浮かばず、電話を掛けて聞いたら、樹理ちゃんならこの店の服が絶対似合うとここだけしか教えてくれなかったのだ。
そして理右湖はこう付け加えた。
『絶対、あの子遠慮してほしくてもいらないって言うに決まってるから。かわいいのがあったら勝手に買ってあげなさい。服はいくらあっても腐らないから大丈夫。着られなくなったらウチに回して。桜と椿に頂戴ね』
最後のあたりはちゃっかりしているが、理右湖の言うとおり、樹理はきっぱりと拒否した。
服を手に取り、サイズを確認して無造作にセレクトした服を店員に渡す。
「こちらのお洋服はお持ち帰りになりますか? よろしければドレスと一緒に後日お届けいたしますが?」
「届けてください」
「かしこまりました。お届け先をお願いします」
万事抜かりないらしい。控えていた店員がさっと必要事項を記入する顧客登録用紙を差し出した。
最初に渡されたのは、上半身胸から腰まで覆う下着と、ワイヤーで形を固定されたアンダースカート、十センチ近くヒールがある白い靴。先ほどは一人で広すぎた試着室には、左腕に針山をつけた女性たちが三人も入っていて少し窮屈なくらいだ。
女性たちはせっせとすその長さを調節しピンで留めて、樹理の身長では少し長すぎた羽根のようにひらひらとしたアシンメトリーのすそがくるぶしくらいの長さに整えられていく。
外から見たとき白く見えた生地は、照明を受けて銀や水色、クリーム色にも見える。胸元の生地には小さなバラの模様が織り込まれていて、こちらも光の加減で模様が浮き上がったり消えたりする。
襟はスクエアに鎖骨が見えるくらいあいていて、ノースリーブだが肩幅が少し広くて、生地が緩やかに波打つように腕の付け根を覆っている。
きらきらと光る水色の石がたくさんついたネックレスを首に掛けられて、二の腕にもところどころに石が入った金の輪を通される。いかがですかと鏡を見ると、着ているものがあまりにも樹理の思う現実から離れていてそこにいるのが自分だと納得するまで少し時間がかかった。
試着室から出て哉と顔をあわせたとき、多分顔が引きつっていたと思う。
「じゃあ直ったら自宅へ」
さらりと哉が女性にそう言った時、気が遠くなりそうだった。倒れたらドレスが汚れるっと何とか踏みとどまったが、このドレスを買う? 本気で?
くらくらと目が回って、その後どうやってドレスを脱いで、先のワンピースに着替えたのかもわからない。気がついたら店の外で、終始いた女性と何名かの店員に見送られていた。
「ひ、氷川さん……」
車を走らせてしばらく経って、樹理が哉の顔をそっと伺うように声をかけた。
「あの、服、ありがとうございました」
「ああ」
「でも、アレは……どうするんですか?」
当面、樹理にはあんなドレスを着る機会はない。誰かの結婚式もなければ、ピアノは高校入学と同時に辞めたので、発表会もない。
と言うより、ほとんど白だったあのドレスは披露宴に着ていくのはマナーに反するし、あんなに広がったスカートでうまく演奏用の椅子にかけてピアノに向かえるのか。
「今月もいくつか招待があったから、でればいい」
「なにに? ですか?」
「パーティー」
…………
え。
「ななななな、なんのですか!?」
「同伴で参加できそうなのは……何かの基金の記念パーティーだったかな。ほかには……」
いくつか? いくつも? 毎月毎月?
「これまで断ってきたけど連休明けにでも連絡すればまだ間に合う」
あっけにとられてうんともすんとも応えない樹理に、怪訝そうに哉が問い重ねる。
「着ていく場所があれば買ってもいいんじゃないのか?」
「……普通、逆だと思うんですけど」
どうしてあの時『着ていく場所』なんていってしまったのだ、自分。確かに場所もないと思ったがそれだけではなくて、ああいったドレスは見ているだけで十分なのだ。実物ではなく雑誌やテレビで見るだけでも満足できる。着るものじゃなくて観賞用といった意味合いが強いものだと思っていることをもっとちゃんと伝えないと哉には絶対に伝わらないのかと、いろんな意味でなんだか脱力してしまった。
車が細い路地に折れて、道が石畳に変わり、伝わる振動も変わった。しばらくも経たないうちに立派な門構えの、一目で老舗とわかるような料亭の前で止まる。すぐに木戸が開けられ、中から作務衣姿の男性が現れ、降りた哉がキーを渡している。
さすがに、そのあたりの食堂で定食ではなかったかと哉の『一段上級』な行き先にきっと哉はそんなところに入ったことがないのだと妙に納得した。なるほど、こんなところにあの服ではみっともなかった。初めからここにつれてくるつもりの哉が、服を買ったのもそのためかと理解する。
初めて自力で車から降りた樹理も、哉に続いて敷居をまたぐ。玉砂利が敷き詰められ、両脇に背の低い笹が植えられている。人の歩幅ほどの間隔で地面に並んでいる、打ち水に濡れた御影石は踏むのを躊躇するほどぴかぴかだ。玄関を入れば磨かれて黒光りする柱、白く平らな漆喰の壁。玄関も廊下も畳が敷かれている。案内されるまま奥へ向かうと、都会の真ん中とは思えないほど静かで風情あふれる中庭があり、池には大きな錦鯉が優雅に泳ぎ、木々の間で小鳥がさえずっている。
そんな庭が眺められる座敷で、買い物をしたために遅めになった昼食をゆっくりと味わう。ここまできたら開き直っておいしいものをおいしくいただいたほうがいい。
このとき樹理が問えば、哉は学生時代によく行っていた、味があるといえばそうなのだが、暖簾の端が擦り切れていて、コンクリートの床が乾いた色をしていたためしがなく、座敷の畳がやけにしっとりしていた、老夫婦が営む焼きそばが当時大盛りで二百円だった店の名を言っただろう。今日この店を選んだ理由は、自分の好みを覚えてくれて、少々融通が利くからで、その条件さえクリアされていればどこでもよかったのだ。
さらに言えば、哉が今履いているジーンズは適度にひざの色が抜けていて、ビンテージと言えば聞こえがいいが、神戸にいたころ仕事の途中通りかかった店先のワゴンの中に積まれていた、三本二千円の古着で、もっと言えばぱっと目に付いたその一本しかいらないと定価払おうとした哉に、店員が『しゃーないなぁ マケとくわ』と勝手に七百円にしてくれた代物だ。
要するに、高かろうが安かろうが、お金だけではなく生活全般に全く頓着しない哉は、自分の金のことはこれっぽっちも気にしないのだ。
運ばれてくる料理はどれも哉が食べられる食材を、丁寧に調理したものだった。お昼のコースになっていて、品数も少なめだったが最後に出てきたわらび餅は、口に入れた瞬間溶けてなくなるような絶品だった。
「とってもおいしかったです。ごちそうさまでした」
店先に回された車に乗って幸せそうにそう言って樹理がにっこりしたあと、ナビが告げる行き先に、形容しがたいような短いうめき声を上げる。
すっかり忘れていた、実家だ。
音を立てて息を吸ったきり止まってしまった樹理に、哉がゆっくりと言い聞かせるように、静かに。
「心配するな。夕べ言ったことにうそはない」
|