|
9 卒業
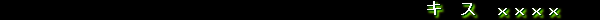
「んっ……も……ダメだって……ばっ!」
第二ボタンから下は全て外されて、難なく背中に回ってきた大きな手がブラのフォックを外してしまう。
「っひんっ……」
両手が拘束力を失ったブラの下から侵入する。柔らかい動きで撫でるように揉まれて、硬くなりかけた先端をつままれて、夏清が悲鳴を上げる。シャツの中に入ってきた井名里の頭。吐息がかかる場所が熱い。無駄なものがない背中に、何度も降りてくるキスにまで反応して、びくびくと体が反り返る。
「こんなトコでっ!! 人が来たらどうするのよぅ…んっ」
声を潜めながら、けれど明確に抗議する。したところで、止まるわけがないことなど分かってはいるのだが。
そのとおりで、全く意に介していないのだろう、片手がわき腹を抜けて、スカートをめくり上げている。
「いや、一回したかったんだよ、ココで」
「だからって今じゃなくていいじゃない」
うつ伏せに乗せられた教卓の上で肘をつきながら、夏清が首を後ろにめぐらせる。
「今でなきゃいつやるよ? あと二時間もしないうちに卒業式だろうが」
「だからってねぇ!! っん! やめっ」
ショーツの中に入ってきた指が柔らかい部分に埋まって動く。片足は教壇につくが、もう片方は床まで数センチのところでつかない。宙ぶらりんになった片足をばたばたと動かしても後ろからのしかかられては身動きできる範囲などタカが知れてしまう。
「もう充分したじゃないっ! 数学準備室とかっ! 屋上とか……」
「でも教室はないだろ?」
「当たり前でしょう!?」
黒板には、下級生が施した卒業を祝う言葉が書かれている。
朝。
答辞を読むため、その最終確認とリハーサルをしなくてはならないので、他の卒業生は九時集合のところを、七時半に学校に着くために夏清は七時前に出かけるつもりでいた。
井名里のほうは当然いつもどおり、八時半までに学校へついていればいいはずなのに、出かけようとした夏清を五分待たせて車に乗せて一緒に登校してしまった。
「昨日帰り遅かったからできなかったし」
どこに行っていたのか、遅くなるから先に寝ていろというメールをよこしたまま、本当に午前を回っても井名里は帰ってこなかったのだ。
「や……もう、こんなトコでしたがるヒトなんか、先生以外いないよ絶対」
「いいだろ? 最後なんだから」
「最後って……んんっ」
「最後だろ? もうお前は絶対ココにはこないんだから、最後にやっとかなきゃ損だって」
指の動きだけでしっかりと潤ったそこから指を抜いて、ショーツを引き下ろし、邪魔になっているグレーのスカートを腰の上に上げる。
「いやぁん」
「あ、コラ降りるな」
「そっちこそ別にスカートめくり上げなくてもいいじゃないっ」
ショーツをつけていても見られたら恥ずかしい場所を剥き出しにされ、空気に肌を撫でられて夏清が身を捩って床に立つ。
「視覚効果だろうが」
「そんな変な効果いらなっ!!」
思わず声が大きくなった夏清の唇に、井名里が噛み付くようなキスをする。
「声でかい」
「………」
向かい合ったのを幸いに、また胸に両手がかぶさる。
「んっふ……」
「夏清、顔上げて」
俯いて声を飲み込もうとする夏清に井名里がささやく。首を振って拒否する夏清の顔を身をかがめて覗き込んで、キスをしながら徐々に上を向かせる。
「ん」
乳房をもてあそびながらキスを繰り返す。絡む舌と、ちゅくちゅくという柔らかくて粘着質な音が耳の奥で響く。
「ふぁ」
ほんの少し唇を離す。追うように小さく出た舌で舐めれば届くほどの距離。
「俺、両手塞がってるから夏清がだして」
抗議を受ける前に唇を重ねる。塞がっている両手は、柔らかい胸をまさぐってこねまわし、先端をつつく。
口で抗議できないので、腕でしばらく抵抗を示していた夏清が観念したように手探りでベルトに手をかけて外す。
早く終わらないと、本当に人が来てしまうかもしれない。
ファスナーを降ろせばベルトの重みで勝手にスラックスの前が開いてしまう。カッターを引きずり出して、なるべく何も考えないようにしてトランクスの中に手を伸ばして、それを出す。
「前と後ろとどっちがいい?」
「………まえでいい」
「なら横から」
「やだっ横ってめちゃめちゃ奥まで来るからっ! ちょっ!? 聞いてよ」
教壇の前の席を足で押して繋げた上に押し倒される。腰から下を無理やりひねられてしっかりと片足を上に拘束される。
「さすがに後始末困るからな」
いいながらポケットからコンドームを取り出していつものように端を咥えて袋を破り、片手で器用につけている。
「あっ! そんなものいつから用意してっくぅ!! ……やんっ」
熱いものがあたったと思った瞬間、それがナカへ挿って来る。体を戻そうとしても片足は掴まれているし、下の脚は挟まれていて全く動けない。
「んんっだめだよっズボン汚れるっ」
「ヘーキ。この後礼服に着替えるから」
汚れることを理由にやめさせようとした目論見はあっさり崩れる。
突き上げられて体が揺れる。どんなにしっかり掴まっていても、不安定な机の上では、余計揺れているような気がする。深く奥まで挿って来てはグラインドする動きに、出る声を唇をかみ締めて殺す。
中途半端にはだけた制服から、ずり上げられたブラとその下にある乳房。平らな腹にかぶさるスカート。無理やりこじ開けるように開かされた脚。その付け根でうごめく自分。
「あー……ヤバ。もうダメだ」
間隔の短い息を漏らしているのはお互い同じだが、どうにもできすぎた『視覚効果』とナカの心地よさに、めまいがしそうだ。
持ち上げた足のひざまである紺のハイソックスに指をかけて引き摺り下ろす。滑らかなふくらはぎに音を立ててキスをして、紅い印をつけていく。蜜にまみれたその場所に指を這わせて敏感な肉芽を探し出す。
「あっ!! んっふ……ぁんっだめっいっ」
井名里のリズムに合わせて動いていた夏清の腰が、勝手にわななくように違う動きを取る。ダイレクトにナカがざわめいて思わず腰を止めそうになるのをわざと動きを早める。
「いい?」
夏清が頷く。
「イきそう?」
「……もぅ入ってきたときからくらくらしたのにっそこ触るの反則っ!!」
うっすらと涙を目じりにためて、夏清がかすれた声で叫ぶ。
「いや、いつもより声出さないから」
「がっまん……してるのっ!! ふぁっ……んっ……」
ひねりあげられるように触られて、夏清の腰が跳ね上がる。
「せんっ……じゃなくてっ……」
「いいよ。ここでそう呼ばれるのも最後だし、先生で」
逃げかけた腰が引き戻される。
「あっん」
深く、最奥に届く。
そのまま奥を突き上げるように何度も押し上げられるような感覚。
「や……もう、せんせ、それ……だめ」
言われなくても、ナカが言葉よりも素直に絶頂のときが近いことを告げる。
喘ぐように半分開いた唇に夏清が無意識に舌を這わせる。
その映像だけで三回くらい大丈夫かもしれない。
本能が全開になって、何も考えずに腰を振る。濡れた紅い唇からこぼれるのは短い悲鳴。
「いっ……イっちゃう……っくっ!! っあん!!」
細い腰が反りあがる。密着するように押し付けられた繋がった部分から、最後に卑猥な音が撒き散らされた。
「どうした?」
「オナカひりひりする。赤くなってるよ」
シャツのボタンを留めながら、最初に教卓に押し付けられたとき擦れた腹部をさすって夏清がつぶやく。
「どれ?」
「見なくていいっ!」
せっかくスカートの中に入れたシャツをまた引っ張り出されそうになった夏清が伸びてきた井名里の手を叩く。
身支度の時間は当然井名里のほうが短い。服を調えて曲がったリボンタイを結びなおしながら夏清がため息をつく。
「なんだかどうにも、自己嫌悪が……こんなトコで……」
「イったことが?」
「やったことがっ!!」
乱れた髪を手で撫でていた夏清が半泣きのような顔で反論する。
「もうホントに、私まだ合格の報告とか、卒業式が終わっても学校に来なくちゃならないのよ?」
「そんなもん別に来なくていいって。どうせ俺には分るんだし」
「いやよ。私が来たいの」
机の位置を戻している井名里の背中に夏清が抗議する。
「………じゃあまたやるか」
「やらないっ! じゃあ来ない!!」
もうこの人と話すのヤダと夏清が地団駄を踏む。
「それならやっぱり最後だろ? コレでおしまい。夏清はもうここには来ない。ここで逢うのは……学校で逢うのは今日が最後」
だろう? と振り向いた井名里が笑う。
「着替えてくる。お前も早く学年主任のところに行けよ」
顎を捕らえられて、掠めるようなキスをされる。
さっさと教室から出て行く井名里の背中を先ほどよりもさらに大きなため息をついて、夏清が見送った。
型どおりの校長の挨拶。型どおりの来賓の挨拶。送辞があって、答辞。
舞台に上がって、もうすでに暗記してしまった縦書きの文章に目を落とす。
型どおり。去年のそれとほとんど変わらない言葉をマイクに向かって喋るだけ。
ふと視線に気付いて見ると草野が笑って右手の人差し指をくるくる回している。早く終われと言うことなのだろう。
それを見て、不意に気が緩む。笑ってしまってから、しまったと思ったときには涙がぼろぼろ落ちてくる。
「あれ?」
戸惑うような自分の声がスピーカを通して聞こえる。どうして泣いているのだろう。
どこまで読んだか分らなくなる。全部覚えていたのに、頭の中が真っ白だ。
突然泣き出した本人もだが、周りはもっと驚いているようで、ざわざわと騒がしくなる。誰も夏清が泣くなどとは思っていなかったのだから当然か。
どうするよ? と草野が井名里を見る。わざとらしく息をついてゆっくりとした動作で井名里が立ち上がってステージの演台の前に立つと同時に、ざわめきがすとんと落ち着く。
制服の袖で顔を拭きながらまだ泣いている夏清を見る。井名里が笑ったのを見たのは、正面にいた夏清だけだ。
「ナニなんでもないところで泣いてんだよ、お前は」
低い声が静まった講堂の中に不思議とよく通って聞こえた。
「だって」
夏清の小さな呟きがマイクを通して拡張される。
「だって、先生、最後最後って、もう、朝から何回もうれしそうに言うし。言われて考えたら、ホントにもうクラスメイトなのにもしかしたら二度と逢えない人だっているかも知れないし。そう思ったら最後ってすごい悲しいでしょ?」
途中何度か鼻水をすするような音をはさんで夏清が続ける。
「そんなのやだ。もっとここにいる。みんなや先生とここにいたい。卒業なんかしたくない。先生、私が卒業しちゃってうれしい?」
もう毎日、学校と言う場所で逢えなくなるのに。大学に進学すれば、今までみたいに四六時中顔を合わせられることはなくなる。
「あたりまえだろうが」
さらりと言い切られて、さらに盛大に涙がこぼれる。
「夏清」
名前を呼ばれて、夏清がびくりと肩を震わせる。こんな場所で苗字ではなく名前で呼ばれて、心臓が突然一拍分倍の量の血を送り出すような音で鳴る。
整髪料をつけてきちんと整った髪を掻いて井名里がどうしたもんかなと苦笑する。
このまま夏清が泣きつづける限り、彼女の希望どおり式は終わらない。
「ちゃんと受けろよ」
言われて、ハイ? と涙で濡れた顔を上げると井名里が礼服の胸ポケットからクルクルと巻かれた紙を取り出して、どうやったのか造花を一緒にくっつけて投げて寄越す。
受けるも何も、正確に胸元に飛んできたそれを夏清が難なく受け止める。
「卒業してうれしくないか? 嬉しいに決まってるだろうが」
憮然とした様子で腕を組む井名里と手の中の紙を交互に見る。造花を留めているのは、細いリング。なだらかな曲線で、メビウスの形に表の金と裏のプラチナが重なり合っている。
造花を外して、指輪を紙から引き抜く。指輪をぎゅっと握りしめて。
開かなくても、これが何なのか分ったけれど。
A3版の薄っぺらい紙に印刷されたこげ茶の文字とワク。
見慣れた、きれいだけれどハネ具合が微妙に歪んだ性格を現している文字。
紙がへこむくらい力いっぱい押し付けられた朱い判。
右側にある証人の欄には、おそらくものすごい達筆なのだろうけど、一筆書きみたいになった井名里数威の名前と、その隣には教科書のお手本みたいに癖のない文字で綴られた、北條の名前。
「お前が卒業しないとどうしようもないんだよ。せっかく昨日地元に帰ってやがったバカのとこまで行ってきた俺の苦労はどうなる」
ため息のように、愚痴を言う井名里を見て、夏清が泣きながら笑う。
「来いよ。こんなところよりもっとイイトコに連れてってやるから」
手を差し伸べる井名里に頷いて、もらったときと同じように丸まってしまった紙をまた指輪で留める。造花を自分のものと一緒に胸元のエンブレムの下にあるポケットに差し込んで息を吸う。思い切り。
「ごめんなさいっ! 続き忘れちゃいました。だからもう、何にも言うことなくなっちゃいました」
ハウリングの一歩手前の音量で夏清が叫んでお辞儀をする。大音量に時間が止まったように誰も動けない。
盛大に活けられた春の花が置かれた演台の横を通って、下にいる井名里に向かって飛び降りる。
「よし。周りがボケてるうちにさっさと逃げるぞ」
降りてきた夏清を抱きしめて井名里が耳元で囁く。夏清が頷くのと同時に、足が地に付く。
手を繋いで、中央にできた道を走って。
誰かが後ろで叫んでいた。
草野の声も聞こえた気がする。
外に通じるドアは、いつの間にか開け放たれていた。さっきまで閉じていたのにと横を見ると実冴が苦笑しながら立っていた。
講堂を出て、三段ある階段を一気に飛び降りる。外にいた下級生たちが、終了の拍手もなしに走って出てきた教師と生徒にびっくりした顔をしていたけれど、無視して振り返らずに駐車場まで走る。
車のドアを開ける時、講堂の方を見ると追いかけてきていたのは生徒指導の先生と、何人か体力のありそうな若い教師。それから、クラスメイトの面々。
「うわ。大騒ぎだよ。先生」
「いいから早く乗れって」
夏清が乗るのと同時にタイヤを派手に軋ませて井名里が車を出す。追っ手を完全に振り切るために後ろの通用門を減速なしで突き抜けて、もう一度タイヤが悲鳴を上げるほど強引に曲がって公道にでる。その音に辺りにいた人たちがこちらを見ている。
「あ、しまった。卒業証書持ってくるの忘れた」
「構うか。今度俺が取ってきてやるよ」
「でも先生、どうするの? このまま失業するかもね」
きっと大騒ぎだろう。明日明後日は土日なので休みだが、月曜日からまた井名里は通常の業務があるはずなのに、どうやって出勤するつもりなんだろう。
「するか。こういうときの国会議員と教育委員会関係のコネだろうがよ」
「……そんな、汚い大人の見本みたいなこと……」
国会議員とはそのまま父親のことを指すのだろうし、教育委員会関係のコネは北條のことだろう。
「今まで遠慮してた分、骨の髄までスネにかじりついてやる」
「先生、それ、もうすぐ二十九になる男の言っていいセリフじゃない。それに先生、別に公立じゃなくても私立とかからお誘いあるでしょ」
生徒にしてみれば横暴なくらい強引な授業だが、実際新城東高校は、県立高校が一斉に行う学力試験をすると県下一で数学の平均点が高い。なんだかんだと言いながら、それなりに生徒は井名里の授業を受けて実力をつけている。
そう言った事実を嗅ぎ付けた私立の進学校から幾度となく誘いを受けては、条件も聞かずに断っている。
「あほう。俺は地道に公務員やってくんだよ。私立なんかに行って行動範囲に余裕が出たらまたいらん波風立つだろうが」
井名里真礼が井名里家と血縁ではなかったと知れたとたんに、井名里の周りが突然騒がしくなった。毎日のように井名里数威の後援会の人間から、跡を継ぐようにと矢のような催促。やっと最近静かになったところなのだ。
「でも、先生ってどうして先生になったの? 私ね、それずーっと前からものすごく疑問だったの」
「ん? 理由? 簡単だ。将来なんになるんだって聞いてきたのが高校教師だったから、じゃあアンタがなれたなら楽勝だから同じのって」
「………カンタンすぎ」
「良かったんだよ別に。仕事なんざなんでも。政治がらみでなければ。お前こそなんで教育学科?」
それこそ他にもあっただろうと井名里が問う。
「え? うーん。やっぱりカンタンかな。先生が先生だったから、私もって思ったの。私がなりたいのは高校じゃなくて小学校だよ」
笑いながら夏清がそう言って、走っていたとき握ってしまって少しよれよれになった丸まった紙を手の上で転がす。
「証人って、大人になってもいるんだ」
「らしい。昨日夏清の分だけでいいだろうと思って響子さんのところに行ったら自分の分は? とか言われてな。慌てたぞ。今日渡すつもりだったから。東京の家に電話かけたら国会で予算審議中のクセに地元に帰ってやがるし」
「先生でも知らないことってあるんだ?」
「あたりまえだ。見るのも書くのも初めてだぞ」
「そりゃそうだね」
ちらりと見ただけだが、なんだかイロイロめんどくさそうな書類だった。
「……これに書いてもらうの、なんか言われた?」
北條はあっさり書いてくれそうだが、井名里数威のほうはどうだったのだろうと、夏清が少し不安そうな顔で井名里を見ながら問う。
「言われた言われた」
「………なんて?」
黄色になりかけた信号の前で減速して止まる。わざとらしいため息をひとつついて井名里が真顔で、耳を伏せた子犬のようにびくびくしながら井名里を見つめ返している夏清を見る。
「進学するのにごたごたしてるのが落ち着いてからでいいから東京の家に飯食いに来いってさ」
にやりと笑って、放っていると大事な書類を握りつぶしそうになっている夏清から、さりげなくそれを取って井名里が自分の胸ポケットにしまう。
「いやならいいけど?」
「行くっ!!」
「言っとくけど今すぐは無理だからな。まだ向こうにいるだろうし」
このまま行こうと言い出しそうな夏清よりも先に井名里がけん制する。
「コレから行くトコはもう決まってるし」
「は? 家に帰る……んじゃ……ない、ね」
言われて初めて気づいたのかいつもと違う風景にきょろきょろと夏清が首をめぐらす。
「どこ行くの?」
「イイトコに連れてってやるって言っただろうが。当てたら教えてやるよ。もう着くけど」
「着くなら先に教えてくれてもいいじゃな……い?……」
目の前にある建物に、夏清が口をサイレントで動かす。
キョーカイ?
晴れ渡った3月の青い空と白い建物のコントラスト。その前にある駐車スペースに車が止まる。
「………だから、言っただろうが。卒業式が終わったら渡すつもりだったって」
あがあがとわけの分からない動きを続ける夏清を車内に残したまま、井名里が降りて助手席のドアを開ける。
「予定よりだいぶ早かったけどあいつら来てるかな」
「ってか早すぎ。あんたらバカっぽいことやらかしたって?」
「バカとか言うな。仕方ないだろうが」
背の高い人物が携帯電話を片手にもってくすくすと笑いながら近づいてくる。
「どーして、人に黙ってこういうことするの?」
何とか立ち直ったらしい夏清が、シートベルトを外して外に立つ。
「ああ。この前の仕返し。お前よりは準備期間は短いぞ」
「………」
「あら、楽しいことの片棒担ぐのは好きよ」
「今日もまたウルトラゴージャスですね……ミカさん……」
腕に下げたブランド物のバッグに電話をしまって艶然と微笑みながら隣に立った人物を見て夏清がつぶやく。
「結婚式に呼ばれた時のコンセプトは『花嫁より目立つ』でしょ?」
「店長はいつでもどこでも誰よりも目立ってないと気がすまないじゃないでしょう。でっかいのがカベになってないでどいてくださいよ。肝心の少女が出せないじゃないですか」
はい邪魔邪魔、と言いながらツインテールの巻き毛頭を井名里とミカの間につっこんで、店員の志真が顔を出し、夏清の腕を掴んで引っ張り出す。
「じゃあ。少女はいただきましたから」
「え? ええっ!?」
誰にも有無を言わさずにそのまま夏清を引きずるように志真が遠ざかる。
「どのくらいかかるんだ?」
「値段? 時間?」
「カネはちゃんと払うって言ってるだろうが。時間だ時間」
「さー……でもしーちゃんも翔子ちゃんも手際はいいはずだから速かったら三十分くらいでできるんじゃない? ちょっと待ってどこ行くの?」
「ドコって、ヒマだし茶店行ってくる」
敷地内から出て行こうとした井名里の襟首を掴んでミカが引きずり戻す。
「まさかそのままでいるつもりじゃないでしょうね」
「いいだろ別に。礼服だし」
担任するクラスが卒業生と言うこともあって、井名里が着ているのは黒のモーニング。
「アンタ何考えてるのよ。どこに黒い新郎がいるの。アンタの分も用意しておいてあげたから着替えなさい」
「オイコラ。頼んでないぞ」
「祝儀よ祝儀。白のエナメルでリボンついた靴、履かせてあげるから」
「いやがらせか、それは」
「結婚式って言うのはね、新郎新婦が見世物になってナンボのもんよ」
引きずられながらそう言い切られて、諦めたように井名里がため息をついた。
「だからどうしてウエディングドレスがミニなの?」
芸能人でもあるまいし。
「あら。だってだって似合うでしょ?」
「やっぱり先生のリクエスト?」
「んーん。これは私の独断と偏見。彼、ウエディングドレスにミニがあるなんて知らないんじゃない? 知ってたら絶対それで注文入ってただろうねぇ」
控え室に入れられて、最初に巻かれたカーラーを取りながら笑って志真が言い切る。
くるくると器用な手つきで巻かれた髪を結い上げてピンを留め、生花を飾る。
「若い子っていいわよねぇ なんにもしなくてもお化粧のノリが違うわよ。目もとの青もうちょっと乗せたほうがいいかな?」
口紅をパレットの上で何色か混ぜて色を作りながら、翔子が夏清の顔を覗き込む。
「これでいいと思うよ。この少女、際立たせなくても目じりはしっかりしてるもん」
「オッケー。はい、上向いて口の力入れて。ん。ってカンジで。そうそう」
言われたとおり夏清が顎を上げて口を結ぶ。翔子が唇のラインに沿ってペンシルを入れて、作った色をブラシにつける。
「じゃ今度はちょっと開いて。そんなバカみたいにあけなくていいから。はいそのまま」
手際よくブラシを走らせて、左右から確認するように眺める。
「よし。我ながらすばらしい出来だね」
「アタマもできた。どう?」
「よいのでないの?」
「………アリガトウゴザイマス」
ふわふわくるくるした髪型の自分が鏡の中からこちらを見ている。びっくりするくらいきれいに化粧されていることも手伝って、それが自分なのかイマイチ確信がもてない。
つけてもらった花が取れない程度に首を動かして、鏡の中の人物が自分自身だと確認していると、ドアがノックされてひょこひょこと実冴のところの双子が顔を出す。
「終わったから入っていいわよ」
入り口に立ったままなかなか入ってこない双子に志真が声をかけるとそっとドアを押して部屋に入ってくる。
てけてけと照れたようなしぐさで夏清の隣までやってきて、二人一緒ににぱりと笑う。
「夏清ちゃんきれー。ねっー」
タイミングもばっちりでそう言って双子が顔をあわせてまた笑う。
「あのねあのね、これ私と慶(けい)ちゃんで選んだの」
ずっと後ろ手に隠していたものを前に出して、双子の女の子、逢がかわいらしいブーケを差し出す。
「僕たちからのおめでとうなの」
「ありがとう」
大きさも色もとりどりの花がアレンジされたブーケを受け取って、一緒になって笑っていると車を止めてきたらしい実冴と公が現れてさして広くない控え室は満員御礼になる。
「あーあ。キレイになっちゃって。さっきまで泣きながら答辞読んでた人とおなじだとは思えないくらい」
「……その記憶、消去してください……」
ここに居る人物の中で唯一あの現場に居合わせていた実冴にそう言われて、夏清が降参と言いたげにがっくり肩を落としてつぶやく。
「あっちも準備できたみたいだし、そろそろ行こうか」
座っていた夏清に、公が手を差し伸べる。
「はい」
公に連れられて入ってきた夏清を見て、ほんの少し驚いた顔をした井名里に一歩ずつ近づいて。
「びっくりした?」
「ちょっと。よかったな、ヘソが見えるようなやつじゃなくて」
「がっ!! 忘れてたんだから思い出させないで」
今朝のことを言われて、夏清がうめく。こそこそと喋っていると、咳払いをされて進めてもいいですかと聞かれた。ぶっつけ本番でどきどきしたけれど、ちゃんとカンペがあって、そのとおりやっていれば何とかなるものだ。
指にある、裏も表もないメビウスの輪。どこまでも永遠に繋がるもの。
瞳を閉じて。
誓いますか? と、改めて問われると、どきりとする。
でも誓うのは神様ではなくて、きっと自分自身と、そして相手に。
全ての始まりのキスを。
2002.3.30fin.
|