|
3
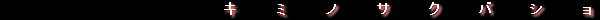
3−1 由紀子の場所
週が明けて火曜日。案の定化学の授業で、この間一緒に行った子達が道彦君に質問攻め。
道彦君も、それなりに覚悟はしてたみたいで、今までの復習のプリントを配りながら、これが終わったら空いた時間は話すから、とにかく静かにって。
みんなすごい早いの。その集中力はどこからくるの? ってくらいすばやくプリントを済ませちゃうのよ。
私は、うーん、個人的にはあんまり聞きたくなかったからのろのろやってたんだけど、やっぱりほら、道彦君の授業だし、化学は結構がんばってやってたから、だらだらしようにも答えなんかすぐわかっちゃうもの。
プリントの答え合わせが終わったのが授業が終わる十分前。遠慮なしで変なことまで聞かれながらも、照れたみたいに笑って彼女の話をする道彦君。
彼女は年上。年までは教えてくれなかったけど。職業はお医者さん、私たちに会った後すぐ病院に呼び出されて仕事に行っちゃったんだって。なんかそれ聞いて、ちょっと、ほっとしてる自分がいていやな感じがした。
久しぶりの梅雨の晴れ間で、私はいないかもしれないって思いながら屋上に向かう。ちなみにカギは、ヘアピンで開けると壊れちゃうこともあるからって、道彦君がこっそり作ってくれた合鍵がポケットにあるの。
「来ないかと思ったよ」
いつもみたいにそーっと屋上に向かう階段を昇ってそーっと鉄製のドアを開けると、真上から道彦君の声。道彦君も同じこと考えてたんだって思ったら、ちょっとうれしくなる。来ないかと思った、ってことは、待っててくれた、ってことだよね?
「晴れたら来るって約束だもの」
はじめの頃はさびが浮いていたはしごも、何度も使ううちにそれなりにきれいになっていくのよね。それを昇って、屋上の屋上に到着。
「はい。お弁当です」
今日は晴れっぽかったから、ちょっと力作なのよ。
「お、ありがとう。んじゃこれと交換ね」
お弁当の包みと、駄菓子屋の紙袋と交換。
「最近まともに飯食ってなかったから、ありがたいねぇ」
「でも先生、日曜に行ってたお店ってすごく有名なとこなんでしょ?」
あとで佐貴ちゃんに聞いたら、地方紙とかでも取り上げられてるくらいおいしいパスタのお店だってぎゃーぎゃーいいながらうらやましがってたもの。
「ははは。実はねーみんなには言ってないんだけど、あの時ケンカしてる最中でさ、味なんて全然わからなかったよ」
「そーなんですか……そんな風に見えませんでした」
「うん、彼女、プライド高い人だからね。知らない人にでもケンカしてるなんて見られたくなかったんだと思うよ」
うん、プライド高そう。女医さんってくらいだから、本当に頭もいいだろうし。
「ソーコとか、先生にはもったいないとか失礼なこと言ってましたよねぇ」
「いや、確かに僕には過ぎた彼女だよ。方や女医、方や女子高の臨時講師で大学の研究員だからね」
そう言って、道彦君は自嘲気味に笑う。そうですか?
「やっぱり、大人って仕事で人を見るんでしょうか?」
「それもあるけど僕の場合は自分の気持ちかな。同棲始めた頃とかは全然思わなかったけど、年を重ねるにつれてつりあいが取れてないって思い始めたんだ」
「先生、同棲してるんですか!?」
「あっしまった。内緒ね。学校で教える立場なのにそんなことしてるってのは……ま、同棲なんてどんな仕事していようがあんまり外聞よくないし」
「じゃあ、結婚とか、するんですか?」
「ストレートだなぁ……それはね、僕は考えてないんだ。今は」
「今は、って事は、いつかはするってことですか?」
彼女がいるって聞いたときよりショックかも。
このあいだの日曜に彼女を見たときよりショックだわ。
そうよね。だってもう、道彦君二十八だもの。結婚くらい、いつだってしようと思えばできるし、あれだけの人なら、あっちから愛想つかされない限り、いっしょにいたほうがいいもの。
「いや、別れようかな、って思ってるんだ」
え?
「同棲始めてもう四年以上経つんだけどね、そろそろダメかなって思うんだ。時間がすれ違うのはその頃から変わらないけど、この頃は、心がすれ違っちゃって、顔合わせたらケンカしてるよ……って、彼女にはっきり言わないで、由紀ちゃんに言ってても仕方ないんだけどね」
私があんまりじーっと見てるもんだから、また道彦君、さっきと同じような笑い方をする。
そんなことないです。
「そんなことないですよ。だってほら、誰かに話を聞いてもらうだけですっきりすることってあるじゃないですか? 足し算とか、声に出して人に聞いたら計算できちゃったり。私に話して、先生の中でごちゃごちゃしたものが整理できるなら、私、いくらでも聞きます」
「ありがとう。ホントに、君はすごいね」
なにがですか?
「きっといろいろあったから、君はそうしていられるんだろうね。今のままずっと、そのまま大人になれたらきっとすごくいい人になれるよ」
「へへへ、そうですか?」
うまそうだなーとか言いながら、道彦君がお弁当を食べているのを見る。
「どうしたの? 食べないの?」
「え? 食べます」
紙袋を開けたら、また別の、もっとかわいい感じの包みが入ってるの。
「なんですか? これ」
「いつもご飯もらってるお礼。もっと早く渡そうと思ってたんだけどここんとこ雨続きで逢えなかったから。良かったよ、今日晴れてくれて。来週からは期末試験だし、もう今学期ここで逢えることもないから。気に入ってもらえるかどうか分からないけど」
「開けていいですか?」
「どうぞ」
どきどきする。誰かから何かをもらうのって、こんなにどきどきしたっけ? 指震えるよ。
「キレイ…かわいー……ありがとう」
きらきらした大きな水色のビーズが、雪の結晶みたいに組んであるバレッタ。
「うれしい。大事にしますね」
太陽に透かすと、屈折した光がこぼれて落ちる。
「そんな大層な……安物だよ。給料安いから」
「ううん、値段じゃないです。だって、これ先生が選んでくれたんでしょ? それだけですごくうれしいです」
きゃーもう、どうしよう。顔の筋肉が溶けちゃった感じ。うれしくて仕方ないの。
笑いっぱなしの私に、道彦君も笑ってお弁当食べてくれる。
それだけで幸せな気持ち。
ああでも、もしフリーになった道彦君が、私のこと好きになってくれたらもっと嬉しいかもしれない。
もう一回大事にバレッタを包んで、ポケットに入れる。
「ほら、パン食べないとお昼終わっちゃうよ」
「はい、いただきます」
いつもとおんなじパンだけど、今日のはもう、すごくおいしかった。
バレッタをもらったのもうれしかったけど、きっと道彦君が彼女と別れる、って話を私にだけしてくれたのも、この気持ちに拍車をかけてる。
人の不幸を喜んじゃいけないと思いつつ、チャンスが増えたのが、かなり、うれしかった。
パンを食べ終わって、私は前から聞きたかった質問を思い出す。
「先生」
「なにー?」
「先生はどうして化学を勉強しようって思ったんですか?」
私よりずっと早くお弁当と、足らない分のパンを食べてコンクリートの上に寝転がっていた道彦君に、聞いてみる。
「ああ、言ってなかったっけ」
よっこいしょ、とジジ臭い掛け声とともに起きあがって、なんだか、思い出し笑いみたいな顔。
「僕の実家ね、静岡の方で温泉旅館やってるんだよ」
「えー? じゃあ先生、温泉継ぐんですか?」
「継がない継がない。ウチ、代々女が継ぐからもう姉が継いでるよ。それになに? 温泉継ぐって……」
「あ、旅館」
「そう、旅館。だからね、親父もじいさんも養子なわけ」
すごいですね……
「親父は小説家してて、それなりに自分の仕事とかもあったんだけど、じいさんはね、もういつもヒマ持て余してる人でさ、小さい頃からいつも僕の世話はじいさんの仕事だったの。まあ僕の上に五人も女の子がいて、やっと生れた男の子だったからそりゃもうじいさんは僕に構ってくれたんだ。
そんな時に、小学校に上がる頃かな、じいさんがさ、手品見せてやるって僕を温泉につれてくんだよ。桶に温泉汲んで、変なまじないみたいなことぶつぶつつぶやいて掻き回したらあっという間に色が変ったんだ。ウチの温泉は無色透明でもちろん普通に掻き回しても色なんか変らない」
「なんでですか?」
「なんでだとおもう?」
「……………わかんないです」
全然分からない。どうして温泉の色が変るんですか?
「うん。俺も全然分からなかったよ。見てないのに由紀ちゃんに分かるわけないさ。でもね、それがすごくおもしろくて、俺もじいさんにどうして? どうして? ってうるさいくらい聞いたんだ。でもじいさんは、あることをしたらそうなることを知ってても、どうしてそうなるのかって言うプロセスとかは全然分からないわけ。しようがないからさ、調べたよ。自分で」
「すっごーい。それで、答えわかったんですか?」
「いや、結局子供じゃ調べるって言っても高が知れてるからね、そのまま分からずじまいでそのことすら忘れかけてたんだ。偶然、高校に入ってからたまたま実験で同じようなことをやったんだ。その時『あの時のアレはこういうことだったのか』って。それでまた、化学に目覚めちゃって、気づいたらこうなってたよ。まぁ、由紀ちゃんの将来の夢より簡単な理由でしょ?」
「そんなことないです。そんな昔から好きだったこと続けてられるって、すごいことですよ。かっこいいです」
「ま、手品にはタネもしかけもあるんだよ。そうだな、二学期にでも実験やる? 簡単な化学反応を応用したマジックだよ」
「やりたいです!」
「危険物を使うわけでもないし、許可も下りるだろうから、じゃあ二学期までに答え探してもいいよ。フライング……インサイダーかなぁこりゃ」
「インサイダー? なんですか? それ? 飲み物?」
「ベタなボケありがとう、あのね、インサイダーって言うのは…株式売買なんかで、自分しか知りえない情報を使って不法に……って……政治経済もがんばってね。新聞も読もう」
がっくりしながら道彦君がそう言う。
すいません……ほんとにそれも分かりません。もうコレしか言えません。
「はい。がんばります」
3−2 引き続き由紀子の場所
「うん。今回も異常なし。っていうより立派な健康優良児」
泌尿器科の秋元先生が、検査の結果を見てにっこり笑って太鼓判。
終業式が終わって、午後から三ヶ月に一回の検査の日。日常生活に支障はないとは言え私は人より一つ腎臓が少ない。だから、一応定期的な検査を受けないと、悪くなってからじゃ遅いから。
「この調子なら、成長期が終わったくらいからなら半年か一年に一回でもいいと思うけど、高校卒業するまでは、このくらいで通ってね」
「はい。ありがとうございました」
お礼を言って、いざ会計へ。
って思ったら、廊下の向こうから来た人の顔を知ってる気がして一秒ほど凝視。
「あら?」
向こうも気づいたみたいで、一緒に歩いていた人に何か言ってから、こちらに向かってくる。えーっと、誰でしたっけ? 自慢じゃないけど人の顔覚えるの得意じゃないのよね。
「こんにちは」
「こんにちは」
えーっと、えーっと。どこかであったことがあるんだけどなぁ
うんうんうなってると、笑われてしまった。
「分からなくてもいいのよ。ちゃんと挨拶したことないもの。根岸由紀子ちゃんでしょ? 私は、一之宮奈留美(いちのみやなるみ)」
すいません。名前聞いても分からないです。
「道彦……遠野君の」
ああっ!!
「先生の彼女!!」
「しっ声大きいって」
「ごめんなさい、つい……」
しかも指差してるし。あわてて手を引っ込めて、平謝り。
「いいけど。今日は? お友達かご家族のお見舞い?」
「いえ、検査です。えっと私、腎臓、一つないから」
「あーそう言えば道彦が言ってたっけ、事故に遭ったって。それで? 大丈夫なの?」
「はい。異常なしです」
「もう終わったの?」
「あ、会計まだです」
「それならいいわね。話でもしない? お茶くらいおごるわよ」
……話って?
「そんな身構えなくても。道彦が学校でどんな感じかとか、そう言う話」
あ。それなら……
こっちよ、といざなわれて迷路みたいな病院の中を連れまわされる。
道彦君の彼女、奈留美さんてすごい足が速いの。一生懸命歩いてもどんどん差ができていく。
「すいません。もうちょっと、ゆっくり……」
「あ、ごめんごめん。早かった?」
「わたし、腎臓のほかに足も……普通に歩く分には、今はもう平気なんですけど、飛んだり跳ねたり走ったりは、できないんです」
「そっか……大変ね」
「そうでもないです。階段も平気になったし」
小学校の頃は、階段の上り下りだけでも休み時間がつぶれちゃうくらいかかってたけど、今は普通にできるから、日常生活は苦にならない。
「すぐだから、こっち」
私が追いつくまで待ってくれて、角を曲がるとすぐに喫茶スペースにたどり着く。
「コーヒー? 紅茶?」
「紅茶おねがいします」
パイプいすに毛が生えたくらいの椅子に座ると、奈留美さんがオーダーを聞いてくれる。
どっちでもよかったんだけど、喫茶店とかのコーヒーって結構濃いから紅茶。
「さってと、あ、タバコ平気?」
「平気です」
一応断ってから、彼女は白衣のポケットを探ってとりだしたタバコに火をつける。
「びっくりした? 道彦は吸わないから」
「あ、はい……じゃなくて、いえ……」
「家では吸わないようにしてるんだけどね、結構ストレス溜まるんだ。医者って」
「家では……ですか?」
「そうよね、聞いてないわよね、同棲してるのよ今。っていっても、ここんとこ私がずっと死にそうな患者何人も抱えてるのと、彼も九月にある学会だか論文発表だかで、あなた達に逢ったあとはほとんど話しもできてないけど」
「そう、なんですか……」
じゃあ、先生はまだ、彼女に別れ話を伝えてないのだろう。
どう答えていいのか分からずにあいまいに笑ってごまかす。
「で、どうよ、彼、ちゃんと先生やってる?」
「えっと、はい。授業も丁寧だし、質問したらちゃんと答えてくれるから、すごく人気ありますよ。実習とかも細かく指示してくれて分かりやすいんです」
「へぇ」
「生活してる中で化学ってどんな風にかかわってるかとか、そういうことも。うちって家政科だから料理とか、醗酵したり、腐ったり、混ぜておいたら違うものになったりっていうの、そういうことの質問でも、先生即答できなくても次の授業までには絶対調べてきてくれるんです」
「すごいわね」
「そうなんです! すごいんですよ。二学期も自分が化学に興味を持った始まりの実験もしてくれるって約束してくれたんです! あ、これ内緒だったんだ。まいっか。学校の人じゃないし。だから先生、すごい今もう人気ナンバーワンなんですよ! あ。すいません」
しまった、道彦君のこと話してるとついうかれて彼女相手に何ハナイキ荒くして話してるんでしょうか、私ってば。
「いいのよ。私もね、結構教師って彼の天職じゃないかと思うんだけど、本人は嫌みたいなのよね。ずっと研究ばっかりしてる人でしょう? やっぱり研究は続けたいみたいで、私が言っても全然聞かないのよね。今年一年でやめるってそればっかり」
「そうなんですかー」
やっぱり道彦君、初めての授業のときの自己紹介で言ってた通り、一年で辞めちゃうつもりなんだ……
「あなたからもね、機会があったら言ってよ。続けろって」
「はぁ」
でもなんで、そうよ、私は確かにこの間見たけど、あのときの私ってその他大勢のうちの一人だったのよ? どうして奈留美さん、私のこと知ってるんだろう?
「でも、なんで私に……ですか?」
「ああ、だって、道彦が生徒のこと名前つきで話したの、あなたが最初で最後だもの。昔逢った事もあるんでしょう?」
「はい……」
「日曜にあなた達が騒いでるとき聞いたのよ。誰が彼の言う『由紀ちゃん』なのって」
「でもすごいですよね、たったそれだけで覚えちゃうなんて」
「ま、職業がら顔くらいは覚えられるようにしとかなくちゃならないしね」
じゃあ私、絶対お医者様にはなれないわ。
運ばれてきたアイスティーを無意味にかきまわして、ごくごく飲む。
はー
奈留美さんは、二本目のタバコに火をつけて、ホットコーヒーを飲んでいる。
この時点で、大人の女と私の差は歴然って感じだわ。
ため息のつき方だってかっこいいのよ?
「やっぱり、男ってのはあなたみたいな子を好きになるもんなのかしらね」
「は?」
「気にしないで。独り言だから。さてと、そろそろ仕事に戻るわ。それじゃあね」
腕時計を覗いてから、コーヒーを飲み干し、オーダー票を取って奈留美さんが席を立つ。
「え、あ……ごちそうさまでした」
「どういたしまして」
私も慌てて席を立って、おごってもらったお礼を言う。彼女は一度振りかえってそう言うと、会計を済まして颯爽と病院に戻って行った。
3−3 道彦の場所
疲れた。
自分の実験の準備と学校の期末試験が重なって、その上成績までつけなくてはならないのだ。文字通り寝るヒマもなかった……
当然部屋にも帰っていないので、もう十日以上奈留美に逢ってない。コレっていつだったかに僕が発表のためにハワイに行った時以来かもしれない。
体を引きずって部屋に帰ると電気がついていた。
帰る家に電気がついてるのって、なぜだかほっとする。
「ただいまー……」
そのまま玄関に倒れ込むようにして、靴を脱いで中に入る。
「お帰り。今日は帰って来たんだ」
「うーん。ごめん。やっと一区切りついた……疲れ……た……」
冷蔵庫を開けて、麦茶の一気のみ。はー生きかえるなぁ
「ごめん、重い……」
お茶をしまうために前かがみになった背中に、ずーんと奈留美が乗ってくる。彼女がこういうダイレクトな表現をする時は、大抵酔っている。
「だってーひさしぶりでしょー? 逢うの。一緒に住んでるのに」
「だから、ごめんって」
「いーっつだって、研究、研究。そうよね、こんなかわい気のない女より、思い通りになったり、ならなかったりする研究の結果の方が面白いわよねぇ」
「はいはい。酔ってるならもう寝なよ。明日も仕事でしょ?」
だらだらと、くっついてくる奈留美を離そうとすれば、余計にべったり張りつく。
「なーるーみーさーん?」
「もう動けない」
「はいはいはい。ベッドでいい?」
「いー」
痩せて見えるけれど、実際十時間の手術にだって耐えることができる筋力と、重い患者を起こしたりする体力の詰まった体は、実は重い。
声に出すとおっさんみたいだからといわれるので心の中でどっこいしょ、と気合を入れて、立ちあがる。
もともとこの部屋は、奈留美の部屋。ダイニングキッチンと、和室と洋室が一つずつ。
その洋室が奈留美、和室に僕が寝ている。お互い学術系の本がバカほどあるので、どんどん部屋が狭くなっているのが現状だ。久しぶりに入った奈留美の部屋は、薬品臭を含んだ彼女のにおいが満ちている。
ベッドの脇まで積み上げられた本を崩さないようにしながら、なんとか彼女を寝させる。こりゃあ別れ話どころじゃないわ。
「ねーみちひこー」
「なに?」
ドサクサにまぎれて、首に細い腕が回される。
「きょーね、由紀子ちゃんに逢ったよ」
「は? どこで?」
「どこでって、病院に決まってるでしょー検査だってさ」
「ふぅん」
「すごいよねー彼女、カルテ見たけどさー体中、事故の傷や手術の痕、あるのねー」
「なっ! 医者でもそれはしたらダメだろ?」
「べっつにーいつでも見れるし、カルテなんて。私、コレでも外科医なのよー?」
クスクスと笑いながら、奈留美が腕に力をこめる。体重をかけて首を引かれれば、疲れた体が悲鳴を上げる。
唇がふれる。
アルコールの混じった吐息がふれる。
「っ! 奈留美!!」
力づくで腕を引き離して、呪縛から逃れる。
奈留美が、頭を掻きながら、起きあがって、笑い出す。
「何がおかしいんだ?」
笑い声がどんどん加速する。
「何がおかしいって聞いてるだろうッ!!」
「おかしいわよ。笑わなきゃやってらんないじゃない!! じゃああなたはおかしくないの!? 一緒に四年も暮らしてきた彼女とキスするのより、バイトみたいにやってる学校の、たった一人の生徒のことの方を大事にしてるのよ?」
その言葉に、返す言葉が見つからない。
ただ黙ってしまった僕に、たたみかけるように奈留美が怒鳴る。
「ほんとに、どうして男って、ああ言う子が好きなの? 弱々しくて、はかなげで、そのくせいつも男にこびるみたいにバカっぽく笑ってて。あんな子より、ずっと私のほうがいい女じゃん。だれかれ構わず気があるようなそぶりするような子なのよ? 私のこと庇ってね、みたいに他の男にだって言ってるに決まってるじゃな……」
吐き捨てるようにさらに言い募ろうとした奈留美が、はっとして僕を見上げる。自分でもわかる、体中からじりじりと、冷気のようなものが湧き出している感じ。これが、本当の怒りなんだろうか?
「何よ。怖い顔して」
「彼女は……由紀ちゃんはそんな子じゃない。確かに奈留美は頭もいいし強いかもしれない。でもあの子は、家族をなくして体も傷だらけで、それでも前向きに生きて行こうって必死にがんばってる。何も知らない君が、あの子の事をそんな風に言うのは、許せないよ」
「じゃああなたはあの子の何を知ってるの? あの子はあなたの何を知ってるの? 四年も一緒に住んでた私のほうが、あなたのことよく知ってるに決まってると思ってたわ!」
噛みつくように、すがりつくように、奈留美が僕の胸ぐらを掴む。安物のTシャツから、嫌な音がする。
「でも、でもどうして? 私、どうしてあなたが化学やってるかなんて知らなかった。けどあの子には話したんでしょう!?」
「それは、彼女に聞かれたからだよ。奈留美はそんなこと一度も聞いたことなかっただろう?」
「四年も一緒に暮らしてるのに、聞かれなきゃ言えなかったの?」
だから……と奈留美の肩に手をかける。言いかけた言葉が消えた。彼女の肩ってこんなに細かったか?
いつも堂々としていて、自信に満ちた女性。僕なんかいなくても十分一人でやっていける、いや、僕がくっついてても平気でいられる人。いつのまにか僕の中にできていた強い奈留美の幻想。
「教師を定職にすれば落ちついて、私とのことちゃんと考えてくれると思ってた。だから天職じゃないってふざけたみたいに言ってた」
絶対に泣かない人だと、勝手に思っていた。
すがるようにあげられた顔に、伝う涙の筋。
「時間が経てば経つほど、分かってきたの。あなたがいないとダメなの。あなたでないとダメなの。お願い……そばにいてよ。前みたいに、抱いてよ」
抱き付こうとする彼女の肩を引き離す。
傷ついた表情を隠さずに、彼女が目を見開く。
「ごめん……僕は、時間が経てば、経つほど、心が……離れていったよ」
「じゃあ、どうしたらいいの?」
分からない。
奈留美が望む未来は、僕の中には描けない。
「もう、戻れないの? 昔みたいに、好きだよって、愛してるって、結婚しようって……! もう言ってくれないの!?」
「あの時、君は嫌だって言ったじゃないか!! それを今更……」
「しょうがないじゃない! 気持ちなんか変わるわよ。いつだって同じじゃないもの」
「だったらわかるだろう!? 僕の気持ちだって変わっていくんだ!!」
変わらないものなんかない。いつだってどんどん変化していく。それが、形のない人の心ならなおさら。
「あの子と逢ったから? あの子に逢わなかったら変わらなかった? 先生にならなかったらそのままだった?」
「関係ないよ。もっとずっと前から、こんな生活やめようと思ってた。けど、ついずるずる、今まで来てた。もうやめよう。最近、ケンカ以外で僕達会話してたか? 逢えばいつも口論になってどちらかが黙り込んでたじゃないか。こんなこと続けてても、お互い、いいことないよ」
奈留美が泣いている。
最低だ。もっとちゃんと話し合って、お互い納得してわかれようと思っていたのに。
「もう、出ていくよ」
「そんな、住むとこどうするのよ?」
「大学の寮が……来年建て替えるんだ。だけど管理人さんに聞いたら、今年いっぱいくらいなら、置いてもらえるって」
「なんだ。もう、決めてるんだ。なんにも言わないで……」
不意に、電子音が鳴り響く。いつも二人のあいだに無作法に割り込むポケベルの音。
奈留美がポケットからそれを取り出して、ベルトにつないだチェーンを力かかせに引き千切り、床にたたきつける。跳ねかえり、壁にあたったそれは、画面にひびを作っても、律儀に鳴りつづけている。
しばらく、動きが凍ったように、ただ二人、じっとその音を聞きつづける。
あきらめたのか、ポケベルが鳴り止む。
と同時に、今度は奈留美の電話が鳴り出した。
せかすように鳴り続ける電話。
のろのろと立ちあがる奈留美。
部屋を出て、ダイニングにある電話を取って、聞かなくても分かる。病院からの呼び出し。
「……ええ、わかった。少し時間がかかるかも……いい? できるだけ急ぐわ。いつものヤツ入れといて、ええ。それで様子見て……」
明るいダイニングで、うつむいたまま受話器に向かって薬剤の名前を羅列している。いつも整えられた髪もばらばらになって、顔にかかるように覆っているので、その表情が見えなかった。
電話を切り、奈留美が頭を振る。
何かを振り払うように。
「奈留美」
彼女の泣いて腫れた瞳が、ゆっくりとこちらに。
「荷物、すぐに取りに来るから」
視線を合わせることができずに、目をそらす。
やっとそれだけ言って、部屋を出る。
閉めたドアの向こうから、奈留美の、何か叫ぶような声が、聞こえた気がした。
|