|
幸せのありか 5
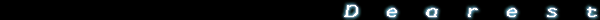
「副社長、ご気分が優れないのでしたら、今日はもうお帰りになりますか?」
篠田にそう問いかけられて、哉は自分がぼーっと中空を見ていたことに気付く。この二日、ほとんど仕事らしい仕事が出来なかった。重要な会議が無かったことがせめてもの救いだ。
「え? ああ……いや……そうだな」
未決済の書類は文字通り山になっている。作らなくてはならない計画書も報告書も。
ここにいても、いたずらに回りを振りまわすだけだ。哉が残っている限り、篠田や他の秘書たちも帰る事ができない。
立ち上がって後ろを向く。曇った夜空と灰色の街並。
初めのころ立ったときも、こんなものは要らないと思った。今も要らないと思う。こんなものを、場所を手に入れるために生きているわけではないと。
だったらなにがほしいの? と心の中で誰かが聞いてきたが、その答えはひどく曖昧で哉は自分自身に答えることができない。
「帰るか」
コートは速人の診療所に置いてきてしまった。新しいコートを買うまでも無い。どうせ家から車、車から会社までの距離しかない。
スラックスのポケットに入れた携帯電話の着信履歴を確認する。今日一日で何度この画面を見たことだろう? 着信を知らせる表示はやっぱり出ていなくて、ため息をついて哉は副社長室を出た。
「今日も、昨日の道を通ってくれ」
車に乗りこんでそう言った哉に篠田は何も問わなかった。黙って頷いて車を出してくれた。
細い路地を危なげなく大きな車で通り抜けていく。
「止めますか?」
昨日哉が止めてくれといいかけた場所の手前でそう聞かれた。
「いや、いい。そのまま行ってくれ」
止まってどうするのだ? 大丈夫かと見舞に行くのか? そもそもの元凶が? どんな顔をして?
ずるずると柔らかい皮張りの後部シートに寝転がる。車の窓から診療所の屋根だけがさかさまに見えて、過ぎていった。
家に帰って真っ先に電話の留守電を確認する。昨日は何も無かったが、今日は赤いランプが点滅していた。祈るような気持ちで再生ボタンを押すと理右湖の声が聞こえてきた。
目を覚まして、一番はじめに見たものは天井に張られたアイドルの顔だった。驚いて声も出なかった。きょろきょろとあたりを見まわすとその場所は自宅の樹理の部屋と同じくらいの広さで、窓には淡いピンクのカーテンがかかっていて、ベッドの横にある机にはぬいぐるみが所狭しと並んでいる。どう見ても勉強をするためのスペースではない。
起きあがって、腕に点滴の針が刺さっているのに気づいた。
ここはどこだろう。どうして自分がこんな所にいるのか全然分からない。
自分は哉のところにいて、そして、哉が酔って帰ってきて……そして……
なにをされたのか思い出して、まだ下腹部に鈍い痛みがあるような気がした。
縛られて、抱かれた。
痛くて、辛かった。
あちこちに噛み付かれたことよりも、哉がうわごとのように繰り返す言葉のほうが。
お前が悪いのだ、と。情けなどかけなければ良かった、と。
哉がこんなに酒を飲まずにいられない理由が自分だとわかって、悲しくて辛かった。
だから哉の好きにすればいいと思った。それで彼の気が晴れるのなら、構わなかった。
恐怖心はすぐに消えた。
諦めたのとは違うけれど、それに似た感情が樹理の心の中にいっぱいに広がった。
哉なら、構わなかった。
むしろ、彼に抱かれることをいつからかずっと待っていたような気がする。
必要とされるのなら、どんな形でも良かった。
いつもいつも、その背中を追って。
いつもいつも、この二ヶ月彼だけを見て。
いつのまにか、好きになっていた。
長さも太さもちょうどいいバランスをした指も、その先の整った爪の形も、無駄のないしぐさも、そっけない態度も、綺麗な文字も、伸びすぎた前髪も、背中も、声も、食事のしかたも、ぞんざいな靴の脱ぎ方も、全部好きになっていた。何を考えているのか全然わからない人だと思ったけれど、一緒にいれば分かった。彼は誰にも何も求めていないだけだと。自分自身のことにさえも驚くほど無関心な人なのだと。この想いは彼にとって必要ではないのだと言うことも分かっていた。
自分はただ、彼の負担でしかないのだ。最初は気まぐれだったのかもしれない。彼の仕事を増やしているのは父の会社で、そうさせたのは自分だ。
分かっていても悲しかった。思い知らされて、とても悲しくて、苦しかった。
でも、この気持ちが要らないとは思わない。こんな想いはきっと最初で最後だと思う。悲しい結末は分かっていても、それを受けとめなくてはならない。
せめて最後だけ、笑って別れることができるなら、それでいいと思う。
腕にまだ残った縛られた痕を見る。触ってももう痛くなかった。この痕が消えなければいいのにと思う。ずっと残ればいい。夢でも幻でもなかったと言う証拠に。
なのに何もかもが初めての体は、心ほど反応しなかった。つまらなさそうに、いや、つまらない時に哉はいつも鼻で笑うように息を漏らす。それが聞こえたとき、自分はそんなことでさえ彼を満足させられないのかと泣きそうになった。
その後すぐに、下腹部に焼けるような熱。からんという、ビンが転がるような音に、何をされたのかすぐにわかった。焼けつくような痛みの後、そんなものとは全く別の次元の痛みに体が裂けたかと思った。
けれどそれもアルコールが回ってしまえば我慢できないものではなくなって、ただ揺さぶられながら意識が遠のくのが分かった。
次に気付いた時、哉が腕の拘束をはずしているところだった。口に入れられたタオルも取られる。噛むものがなくなったら、とたんに奥歯がカチカチと鳴り出した。
止めようとしても止まらなくてどうしようもなくて。
何度もごめんなさいと言うより他になかった。ぎゅっと目を閉じて泣かないようにこらえるので精一杯だった。
哉の腕が伸びてくるのが分かって反射的に殴られると思って身を固めるとそっと起こされた。
すぐに肩に、ひやりとした感触。背広の裏地が汗ばんだ背中にぺたりと貼りついた。
哉が疲れきったような声で体を洗ってこいというのが聞こえた。
その声のどこにも、満足したような響きがなくてまた泣きたくなった。目の前からいなくなれといわれてなんとか立ちあがって言われた通り風呂場に向かった。
そこから先は、もう何も覚えていなかった。
違う。一つだけ覚えている。
夢かもしれなかったけれど名前を呼ばれた気がした。
もう一度呼んでほしくて、暗い所をさ迷って声がしたほうに、樹理は帰って来た。
けれどここには哉はいない。やっぱり、夢だったのだろうと思うと少し寂しかった。
「あ! 起きてる! お母さーん、樹理ちゃん目ぇ覚ましたよー!!」
不意にふすまが開いて、セーラー服の少女が入って来て、そう叫びながらまた出ていってしまった。
あの、と声をかける間もなく。
すぐにばたばたという複数の足音が聞こえて、開いたふすまから頭が三つ。
「あらほんとだ。良かったわ。大丈夫? 昨日丸一日と今日半日、寝てたのよ?」
にっこりと笑って、三十代の半ばくらいの白衣の女性が樹理の腕から点滴の針を抜いた。
「あの……」
「んー?」
「ここ、どこ、ですか?」
「ああ、ここはね、診療所。入院できるような施設はないから、ウチの娘の部屋よ。ベッドのほうが看護はしやすいからね。私の名前は神崎理右湖。そっちにいるのが娘の桜(さくら)と椿(つばき)。そしてあなたは行野樹理、オッケー?」
「ハイ……」
名前を呼ばれて、先ほど入ってきたショートボブの少女とその下のベリーショートの少女がぺこりと頭を下げてくれたので、樹理もつられて頭を下げた。
「起きあがれるなら一緒にご飯を食べましょう。桜、椿、用意してきて」
ハーイと言う声が綺麗にハモって、またばたばたと廊下を走って行ってしまう。
「どう?大丈夫?」
「はい」
「じゃあご飯食べて、元気になりましょう」
人好きのする笑みを浮かべた理右湖に、ほんの少し心が軽くなった気がした。
あんかけのチャーハンと中華スープ。野菜餃子。
神崎家の昼食はいつもの倍やかましくて時間がかかった。
桜も椿も樹理に構いたくて仕方なかったらしい。
眠っている樹理は本当にお人形のようで、彼女達は用もないのに何度も寝ているところを見に行っていた。綺麗なお姉さんは起きても綺麗でしかもその瞳がとてもやさしくて、桜も椿も一瞬で樹理のことが好きになった。にっこりと笑って綺麗な声で名前を呼んでほしくて、どうにかして自分のほうに樹理の興味を引きたくてたまらないのだ。
「お前等もうちょっと静かに食え!! 静かに!!」
耐えきれなくなった速人が叱っても二人の娘たちはへこたれることなく樹理ちゃん樹理ちゃんと病みあがりの人間にべたべたとくっついてあれもこれもと樹理の皿に盛っていく。樹理に食事を摂らせることについては速人も反対しないで見ている。
「そうそう、樹理ちゃんたくさん食べないとだめよ? ダイエットとかしてるの?」
「いえ……しようと思ってもいつも失敗してるから……最近は特にしてないです」
「じゃあご飯、ちゃんと食べてるの?」
理右湖に問われて、答えられなかった。最近は、確かに意識してダイエットしようとは思わなかったけれど家では味見に毛が生えたくらいしか食べていない。学食もミニうどんとかおにぎりだけでお腹がいっぱいになるのでちゃんと食べていないことは事実だ。
「今日のご飯、おいしかった?」
「はい。すごくおいしかったです」
本当に、おいしかった。久しぶりに、ご飯がおいしいと感じた。誰かが作ってくれたものを誰かと、こんな風に食べるだけで、何倍も料理がおいしくなるのだということを忘れかけていた。
学校でも、通学時間が増えたことと、家事をすることで放課後はすぐに帰ってしまうようになった樹理はもともと少なかった友人とも疎遠になってしまった。誘っても断る樹理をだれも遊びに誘わなくなった。テレビを見ることもなくなったので、話題について行けなくなった。三学期が始まった時には昼休みも一人になってしまって学校でも必要最低限の挨拶や伝言くらいしかしゃべることはなくなった。誰かにこんな風に構ってもらったのは、本当に久しぶりだった。
「そう? 良かった」
理右湖がふわりと微笑んだ。誰かにこんな風に笑いかけてもらったのは、どのくらい前だっただろう。話の間にいつ切り込もうかと、うずうずしながら狙っていた桜と椿が『お母さんの料理はいっつもおいしいよ』『おべんとうもすごいんだよ』とまたぎゃあぎゃあと騒ぎ出す。
「……ちゃんとご飯、食べてるかなぁ」
箸を置いた樹理が、小さな声でつぶやくのを速人は聞き逃さなかったらしい。
「育ち盛りがあんな偏食に付き合う必要なんかない。大体金持ちのくせに肉が鳥しか食えないなんてどうかしてる。だからアイツが一番チビなんだよ」
それだけ言うと、娘二人の余りのやかましさに速人は早々に食事を切り上げて表の診療所に逃げてしまった。その背中を見送りながら理右湖が男ってだらしがないわねぇと笑っていた。
「神崎さんって確かに背が高いけど……」
チビ。と言われても、哉の身長は百七十は越えているだろう。確かにこの家のかもいで頭を打ちそうな速人に比べたら小さいかもしれないけれど百五十しか身長のない樹理からしてみたら哉だって充分背が高いと思う。ただし横幅が足らないので、実際より小さく見えるのは事実だけれど。
「そうねぇ、速人君の基準じゃこの家のかもいで頭打たなかったらチビになるんじゃないかしら。ここのかもい、すごく低いでしょ? 当たらないって分かってても身を屈めてるだけ。速人君も百八十はないよ? と言うより哉君はいつも速人君よりバカでかいのと並んでいるから、どうしても小さく見えるんじゃないの?」
そう言えばあっちのバカはなにしてるのかしらねぇと独り言をつぶやきながら、理右湖が速人の使っていた食器を片付けている。
二人の少女につられるままに久しぶりに満腹までご飯を食べた樹理が苦笑してもう食べられないからと断っても二人とも残念そうにしている。
「ほら、椿はサッカーの練習があるんでしょう? 桜も遊びに行くんじゃなかったの? 遅れるわよ」
お茶を運んできた理右湖にそう言われて時計を見てやっぱりぎゃあぎゃあとわめきながら二人が出ていった。椿はユニフォームに、桜も制服から私服に着替えて食卓に現れてまだ帰らないよねと樹理に聞いてきた。どうしたらいいか分からなくて理右湖に助けを求めるように視線を向けると理右湖が笑って、今日はまだ帰らないから大丈夫と二人を送り出す。
柱にかかったカレンダーと寝ていたという日数と自分の記憶を照らし合わせて今日が月曜日だと言うことを確認する。
「ごめんなさいね、うるさくって。ちょっとそのまま待ってて、速人君呼んでくるから」
三人分のお茶を置くと理右湖が診療所の方へ消えて、すぐに帰って来た。その後に速人が低いかもいに手をかけて屈んで越えながらやってくる。
「具合は?」
「はい。もう全然」
ひいていた風邪も治っていた。咽の痛みも、全然ない。
「そうか」
たったそれだけで会話が途切れてしまう。何を言っていいのか分からなくてどうしようかと思っていたら理右湖が口を開いた。
「あのね、樹理ちゃん……」
理右湖が言いにくそうにそこで言葉を切った。この二人は樹理が何をされたのか分かっている。治療をしてくれたのはこの人達だ。
「あのバカのことは気にしなくていい。自分の家に帰りたかったら帰っていいそうだ。何も気にせずに帰っていいといっていたぞ」
「あの……バカ……?」
「哉だ哉!! 昔から変なヤツだったけどこんなことするとは思わなかったぞ。その上一回も見舞いにも来やしねぇ」
哉が見舞いに来ないのは、あたりまえだと思う。哉が毎日とても忙しく仕事をしていることを知っていた。見舞いなど来れるわけがない。
そして彼の仕事を増やしているのは自分であり、父の会社であることを。
「あの………」
哉のことを言おうとして、気付く。一度も彼のことを呼んだ事がなかった。どう言おうか迷った後、結局。
「………氷川さんと……」
「同級生だ! 歳は二十七! 俺もあいつも違う意味で見えないだろうけどな」
「にじゅう、なな?」
華奢で、どちらかと言うと童顔の哉と、医者としての貫禄とまではいかなくても、自信を持って生きていることをうかがわせる目の前の速人は五歳くらい年が違うといわれても納得してしまいそうだが同級生だと言われたらそう見えなくもない気がする。とはいえ樹理はずっと哉の年齢はもっと若いと思っていた。
「あら、哉君はバカの日生れだからまだ二十六よ? 速人君、中高と寮で同室だったんだからそのくらい覚えといてあげないと」
バカの日……それはつまり四月一日を指すのだろう。誰がそうしたのかは分からないが、なぜかその日までが『早生れ』になって、ほとんど一年程歳の違う子達と一緒にされてしまう日だ。
「ヤローの誕生日覚えてどうすんだよ」
イライラした様子で速人が答える。その時、嫌なことでもあったのだろうか?
「あらだって、その次の日はもう一人のバカの生れた日じゃない。丸一年違うけどセットよセット。で、速人君がお子様の日。あなた達そろって覚えやすい日に生れたもんよねぇ」
なぜか懐かしそうにそう言う理右湖に、速人がそりゃよかったですねと棒読みで返している。
中学生のころからあの調子だったのだろうか? 問うことは出来そうだったが、おそらくそのとおりだろうと思って樹理はあえて聞かなかった。
しかし、速人が二十七だとしたら、今いた子供達は? 上の桜は制服を着ていたので中学生だし、下の椿も小学校高学年だろう。
わけがわからなくなった樹理が理右湖を見る。聞きたいことが分かったのか理右湖が微笑んで言った。
「あー……うん、速人君の言ってるのはほんとよ。あの子達は私の連れ子だから」
「ごめんなさい……」
謝る樹理に構わないわよと笑って、それよりどうするのと聞かれた。
「あの、氷川さん、帰れって、言いましたか?」
おずおずと速人にそう尋ねると、怪訝そうな顔をした後、首を横に振った。
「いや。お前さんが帰りたかったら邪魔しないって感じだったな」
「じゃあ、家には帰りません」
樹理の答えに大人二人が言葉を無くした。
「ちょっ……あのね、樹理ちゃん、自分が何言ってるか分かってる? 何されたか覚えてる?」
「はい。分かってますし、覚えてます」
「だったら……」
更に言い募ろうとした理右湖に樹理がゆっくり首を横に振った。
薄く、けれどはっきりと微笑んだ樹理の顔をみて、大体察しがついたのだろう。
「……分かったわ」
「理右湖さん!!」
速人が立ちあがる。絶対に反対だと、意地でも樹理を家に帰すべきだと全身で訴えながら。
「今から電話をかける。明日中に哉くんが迎えに来たらそっちに行っていいわ。でも来なかったら、家に帰りなさい。いいわね?」
樹理は頷いた。
確かにそうだ。樹理が哉のそばに居たいと思っても哉はもう樹理のことなんて要らないかもしれない。
哉に決めてほしかった。
必要だと、言ってほしかった。
留守電の内容は極めて簡潔だった。
明日中に退院させるので、もしも樹理を連れて帰りたいのなら着替えを持って来るように。
速人によって問答無用で樹理は家に帰されると思っていたし、本人もそれを望むだろうと思っていた。けれど、電話の理右湖は、選択権を哉に残した。
哉が哉の意志で、樹理を必要とするのなら来いと。それは暗に、来なければ樹理は自由に家に帰ることができるのだと言うことを指していることは、気づかないフリをすることにした。
樹理はどう思っているのか、不安が残らないと言えば嘘になる。本当は帰りたいのに、哉の意思に従おうとしているだけなのかもしれない。と言うより、多分そうなのだろうと思う。けれど、帰してやらなくてはと思う反面、もう一度逢いたいと、心から願う自分がいた。
いざ逢って、また拒絶されたらと思うときりきり胃が軋む。
何度も留守電を再生して内容を確かめたあと和室に入ってクロゼットを開ける。
掛けてあったフリースのワンピースとグレーのハイネックの薄手のセーター、コートを取り出す。
他に何か要るものはないかと、クロゼットについた引出しをあけて、そのまま動きが止まった。腕にかけていた樹理の服が滑り落ちた。
そこにあったのは、メモの束。
大切そうに、折ったり丸めたりせずにかわいらしいプラスティックのクリップで留められた、哉が樹理に伝言をしたメモの束。
ちゃんと覚えていなかったけれど、おそらく全てあるのだろう。その下にカードキーとピンク色のベルベットがかかったスケジュール帳。
見てはいけないと思っても、手は止まらなかった。メモを引出しに返してちいさな手帳を取る。
毎年中身だけはずして使うようになっている手帳は、なぜか去年の分から、樹理がここに来てからの分が捨てられずに前のほうに残っていた。
ウイークリーになった部分には女子高校生らしい丸い文字でびっしりとメモが取られていた。
作った料理、哉の帰りの時間、置いてあったメモの復唱、哉が寝不足が続いたことを覚えている頃は、顔色の悪さと食事の工夫。
次々とページをめくる。
一日とて空白の日はない。
哉に休みがなかったように、樹理にも休みはなかった。クリスマスも正月も成人の日があった三連休も。哉は当たり前のように仕事をしていたけれど、樹理は同じように、一度も家に帰りたいとも疲れたとも言わずに毎日毎日……
こんな生活を続けていたら風邪だってひくだろう。
毎日仕事が中心で張り詰めた空気の中でそれなりに充実して暮らしていた哉と違って彼女には学校があり、試験があって冬休みがあったはずなのだ。なのにこの二ヶ月、樹理は一言も文句を言わずに朝食を作って、家の中を綺麗に保ち、風呂を沸かして夕食を作り、毎日哉の帰りを待っていた。樹理の全てのライフサイクルが、哉に合わせられていた。
一日五分くらいで、まともに顔さえ合わせない日だってあったのに、哉のことがかかれていない日は一日だってなかった。
三日前の日付までは。
真っ白になったスケジュールに、突然気になって、ごっそりとページをめくる。
最後の日が。
樹理が何を書いているのか、何も書いていないのか。どこからか突き上げるような衝動を力にして、今年の十一月にやってくる最後の日を。
開いたそこには。
その日には。
シャープペンシルで何かを一度書いて、塗りつぶしたあと消しゴムで消したような跡だけがあった。
ため息をついて、哉は手帳を閉じた。
そこに書かれていた文字は、読めなかった。
手帳を元に戻して樹理の服をたたみ、和室にあった紙袋に入れた。ついでに借りていた速人の服も入れてしまう。
あの日のまま触れていない料理がラップのかかったまま、まだダイニングのテーブルの上にのっているはずだ。
食べられるのなら食べてしまおう。レンジに突っ込んで暖めなおせばなんとかなるかもしれない。
そしてとっとと寝て、明日の朝迎えに行こう。
|