|
恋におちたら 3
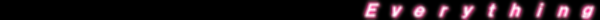
三日続いた休みが終わると、今度は平日が三日続く。当然樹理は学校へ行くが、哉は休みだ。と言うより、休まざるを得ない。
初日を除いて哉はほぼ家にいて、書斎に飾ってあるとしか思えないくらい使われた形跡のないパソコンを立ち上げて、一日中何かガチャガチャやっていた。
その間、樹理は家事と読書と勉強にいそしんでいた。基本的に二人とも家でのんびりしているほうが性にあっているのだ。
「じゃあ、いってきます」
「ああ」
前と同じだけれど、今日は返事が返ってきた。些細なことがうれしくて心がうきうきするものだと思いながら、樹理が家を出る。電車に揺られて二回乗り継ぎをして、学校最寄の駅を出たところで、けたたましい足音が二人分、後ろから猛烈なスピードで迫ってきた。
「樹理お姉さまっ おはようございますっ!」
「おはようございますっ!!」
左右から、かわいらしい声が聞こえて、猛ダッシュを感じさせないくらい軽やかに歩調をあわせてくる少女が二人。身長は樹理も含めて三人ほとんど変わらない。
「おはよう、真里菜さん、翠さん」
右には、さらさらと流れる黒髪をつむじの辺りでポニーテールにした少女が、左には樹理よりなおくるくるふわふわとした、お日様に透けるくらい明るい色の髪を両耳の上の辺りでツインテールにした少女がニコニコ笑っている。
「あの、二人とも、わざわざ待って下さらなくても……」
「わざわざではませんわ」
「ご一緒させていただくのはおいやですか? それなら……」
右がどうしてそんなことを言うのだろうと、左は少し悲しそうに首をかしげている。
「いやじゃないのよ。おしゃべりできるのはうれしいから」
なんとなくしゅんとしおれてしまった二人に、慌てて樹理が首を振る。
「でも、やっぱり私とあなた方では……何と言うかその、釣り合いが取れないというか……」
ごにょごにょと歯切れの悪い事を言う樹理に、左右ともに同じように花もこぼれんばかりの笑顔で答える。
「そんなことありませんわ」
「私たち、樹理お姉さまと仲良くなりたいだけですもの」
ねえ? とお互い微笑みあっている。だからそれが問題なのよ、と喉元まで迫(せり)あがってきた言葉を、何とか樹理は飲み込んだ。
右側の少女は方長谷真里菜(かたばせまりな)、左側の少女は柴田翠(しばたみどり)。どちらもものすごい美少女で、そしてものすごいお家柄のお嬢様だ。
真里菜の祖父は大手銀行の頭取で、祖母はテレビで料理番組を持っているほどの著名な料理研究家、そして母はたいていの人なら顔と名前を一致させることができるほど、テレビによく映っている女優だ。
対する翠は、祖母がその道では大変有名な日本舞踊の宗家だ。翠自身もすでに名取らしい。二人とも幼稚舎からこの学校で学び、この春高等部へ進学してきたそれこそ生粋のお嬢様である。
樹理の記憶では、この二人と出会ったのは入学式の当日。樹理は新入学生の胸ポケットに薔薇を挿してあげるのが仕事だった。薔薇も造花ではなく生花で、時折とがった葉があって指先を傷つける恐れのあるその作業は、あまり人気がない。と言うより、なり手が全くない。それより、パンフレットを配ったり、道案内をしたりと手の汚れないスマートな仕事がたくさんあるからだ。
そんな仕事をほぼ一人で、確実に指に小さな切り傷を作りながら、やってくる一人一人を笑顔で迎えいれていた樹理に、一年の中でもすば抜けて目立つ二人が突然ステレオのように両側から、
「「お姉さまってお呼びしてもいいですか?」」
と、尋ねてきたのだ。
その勢いによくわからないまま了承してしまったのが運のつきだった。
一風変わった「しきたり」のあるこの学校でも、さすがに通常は下級生たちは上級生を「先輩」と呼ぶ。しかし中には例外があって、例えばクラブ活動などをしていて関係がとても親密な場合などは、親しみを込めて「お姉さま」と呼ぶ。複数「お姉さま」がいる場合は、下の名前をつけて例えば「樹理お姉さま」になる。上級生たちはそう呼んでくれる下級生たちを名前にさん付けで呼ぶ。
高等部からの入学の上、これといった部活動をしていない樹理には、当然これまで「お姉さま」と呼ぶべき上級生はいなかったし、呼んでくれる下級生もいなかった。
だから、この言葉の重さを全く理解していなかった上に、なんとこの少女たちはこれまでそういった環境にありながら、自分たちは「お姉さま」と呼ばれることはあっても一度も誰かを呼んだことはないのだと同じように幼稚舎から進んできた同級生から聞いても、まだ事の重大さに気づけなかった。
学校でも目立つ存在だった二人に「お姉さま」と呼んでほしいと思っていた生徒は、同級生である三年生はもとより、二年生にも、樹理が思っていたより大量に存在した。ある人は遠まわしに、ある人は大胆に、どうやって彼女たちにそう呼ばせたのか探り出そうと樹理の周りはこのひと月やかましくてしょうがない。
しかし、そんなこと樹理自身が知りたい。わからないのであいまいに答えると、もったいぶっていると言われるし、はっきり私にもわからないと正直に答えても知っていて教えないと言われるのだ。一体どんな答えなら満足してくれるのだろう。
「どうかなさったのですか?」
「え? あ、ごめんなさい。考え事をしていて」
翠に声をかけられて、ぼんやりと物思いにふけっていた樹理が慌てて笑顔で応える。この少女たちに聞いても、決まって「仲良くなりたかったから」と言う答えだ。そしてそれをこれまた正直に言うと、それだけのことであの子達が「お姉さま」を決めるわけがないと、それこそ決め付けられてしまうのだ。
いっそ二人を私が丸め込みましたと言えば納得してくれるのだろうか。してもらっても困るけれど。
「お姉さま、今日はこの前のお弁当のお礼に、うちからおばあ様がつくってくれたお弁当が届くので、楽しみになさってね」
真里菜がにっこり言い放つ。彼女の家は、今見える小山になった学園の向こう側だ。戦後空襲で焼けてしまった校舎を建て直す際、学び舎は広いほうがいいと彼女の祖父の父が学校に土地を寄付したらしい。もともとの土地もそれより前の代の方長谷家の当主の持ち物で、この学校の創始者の縁戚だ。高等部からは見えないが、中等部の校舎からはグラウンドをはさんで木立の向こうに立派な洋館が見える。そこが真里菜の自宅だ。高等部にだって、車で五分くらいの距離だろう。
「ありがとう、楽しみだわ」
微笑を鏡に受けて返すように樹理が表情を作る。ああやっと校門を抜けたと思っても、生徒の昇降口は、まだ見えてこなかった。
同じように校舎を目指す少女たちの目が、あの人があの二人の……と語りながら樹理を見ている。
本当に、どうしてこの子達は自分を、この平凡な自分を「お姉さま」と認定したのか。
考えても樹理には全くわからなかった。
「いってきます」
そう言って家を出た樹理を見送ってパソコンのニュースサイトとメールをチェックして午前中を過ごし、哉も外出した。目的は散髪だ。
いい時代になったもので、本は自宅でほとんど買える。国内の新書、文庫はもちろん、昔は大手書店で注文しなければ手に入れられなかった洋書から、ビジネス雑誌に至っては在庫さえあればだが、バックナンバーも豊富にそろっている。紙というものはかさばる上に重い。運ぶ手間を考えたら、キーを打って注文するだけで届けてもらえるのは大変ありがたい。
ただ、やはり散髪だけは自分で出向かなければ難しいようだ。こちらも忙しい身だが、それなりに有名どころだと相手も同じである。
それでも、昔何度も練習台にされていただけのことはあって、名乗ったら二つ返事だった。
相手が告げた店名と電話番号を教えられたナビは、東京の一等地へと哉を案内した。近くの駐車場に車を止めて、買い物客とも観光客とも取れる人々の間をマイペースに進んでいく。
目的の店のガラスのドアを押すと、大勢のスタッフがそれぞれのタイミングでいらっしゃいませと声を上げる。その数はざっと見渡しただけでも十名を超えている。
「ようこそ。ご予約ですか?」
「ええ」
「ご指名は?」
「緒方さん……緒方未来さんです」
名を告げると、カウンタの向こうの女性がほんの少し目を見張る。
「店長ですね。少々お待ちください」
後ろを振り返り、誰かに目で合図を送っている。すると客の髪を切っていた長身の男性が小声で客に断ってカウンタの向こうの女性と代わった。
「氷川さまでございますね。申し訳ありません、ただいま店長は私用中でして、しばらくお待ちいただきたいと伝言を預かっております。……十分もかからないと思いますが、よろしければお飲み物をお持ちしますので、あちらの席でお待ちいただけないでしょうか?」
男性が片手で指したのは、通りに面した場所にしつらえられたカフェテリアのようなブースだ。もちろん店内で、通りとはガラスで仕切られている。
「かまいません。待たせてもらいます」
「ありがとうございます。お飲み物は?」
「紅茶を。葉の種類はお任せします」
「かしこまりました」
応対は男性が全てしたが、ここからは初めの女性に代わった。すぐに紅茶がポットで運ばれ、茶菓子までついている。
ゆっくりと二杯目の紅茶を飲んでいると、奥からなにやらあわただしい雰囲気が移動してくる。私用と聞いた瞬間見当はついたが、想像通りの人物がそこに現れた。
「うっわー 哉ちゃんひっさしぶりー」
底抜けに陽気で間抜けなせりふを吐いたのは、茶色い髪を後ろで縛った美青年だ。背はそんなに高くないのだが、頭が小さくて手足もほどほどに長く、均整が取れている。よく通った鼻筋に、くっきりと二重の大きな瞳は猫のようで、細すぎない程度に鋭角なあご。何か塗っているのかと思えるほどしっとりとした唇は、いたずらっぽい笑みの形だ。
カットを待つ客や、毛染めやパーマの間にくつろいでいる客たちが、みんなぽかんとその美青年を見つめている。
「お久しぶりです、次能(つぐのう)先輩」
「そして相変わらずそっけないなー」
目を合わそうとしない哉に全く動じることなく、きれいな顔をこれ以上ないくらい上機嫌な形につくって笑いながら同じテーブルにつく。
何も言わなくても彼の好みを知っているらしい店員が、てんこ盛りのアイスに滴り落ちるほどのチョコソースをかけ、季節のフルーツをありったけ乗るだけ乗せてみました、という態のガラスの器でんとテーブルに置く。これだけのものを今さっき用意したとは思えないので、彼が入店したときから作り始めていたのかもしれない。
ちらりと目の端に映った器がどう見ても特大の金魚鉢にしか見えなかったが、あえて追求しない。
「ほへでひま、ふふひゃひょーらんだって?」
それで今、副社長なんだって? と、デザート用ではありえないサイズの……サラダを取り分ける為のスプーンですくえるだけすくったアイスたちを口に入れ(そして口の端から茶色いソースを垂らしながら)彼が哉に問いかける。
「ええ。何の因果か」
「ほんらの、おひゃのひんがでひょー」
容赦ないくらい口にアイスを放り込みながらも、果敢にしゃべり続けようとする青年に、哉はまだ手をつけていなかった茶菓子を差し出しす。そんなの、親の因果でしょう、と言っていることはわかるが、聞き苦しいことこの上ない。
「……待ちます」
「ん」
哉が譲ったクッキーを受け取り頷いて、青年はそれをバキバキと砕いてチョコソースの上に撒き散らし、アイスと混ぜて食べることに専念しはじめる。その行動を見て、そう言えば彼は、クッキーやスナック菓子、せんべいなど、乾いた食べ物が食べられないのだと思い出す。
ほかに待っている客たちが異様なものを見るような目でこちらをちらちらと覗っている。自分はともかく目の前のこの人は確かに異様なので、いろんな意味で早く片付いてほしい。
そんな哉の願いを知ってか知らずか、紅茶を飲み終わる前に、彼は甘そうな塊を無に帰した。
「あー おいしかった。ごめーん、マンゴージュース、できればバケツで」
「できないって、都織(とおる)」
苦笑しながらおしぼりを持ってきて、問答無用でその無茶をいう口をふさいだのは、この店の店長、緒方未来その人だった。
「ごめんね、氷川君。おまたせして。理由はこれ」
「いえ」
「忙しいんでしょ? よければすぐにカットするけど?」
「ええ……」
できれば今すぐに頼みたいところだが、目の前でせっせと口を拭いている都織をちらりと見て、席を立っていいものか考える。
「えー ずるいよ未来。哉ちゃんとは僕が先に話しする約束だったのに」
「隣で話せばいいでしょ。氷川君だって暇じゃないんだよ?」
「うそ。暇じゃなかったら平日の昼間にこんなとこいないでしょー」
「都織、自分を基準に考えない」
駄々っ子のような言い方に、未来がたしなめるように言う。
「いえ、今は時間がありますから。本社がこの連休明けまで入れないので」
「えっ? じゃあ明日とあさっても暇?」
「読みたい本が今日の夕方には届くので、暇ではなくなります」
「ちぇーっ」
暇ならば引きずりまわそうと言う魂胆は見え見えすぎてうそっぽい。つまらなさそうな舌打ちも、声で表現するくらいに。
「申し訳ないけど二人とも。僕はそんなに暇じゃないんだ。話があるなら隣を空けるから都織がきたらいいでしょ」
「もう洗わない?」
もう一度店の奥のカットスペースに来いといわれて都織がおびえたまねをして頭を抱えている。
「さすがにね、シャンプーは一日一回でいいから」
「ならいいや。行こっか、哉ちゃん」
にっこりと笑ったその顔は、アイスやチョコソースがついていなくても十分に甘かった。
カット用の椅子をくるくる回しながら楽しそうに笑っているのは、次能都織(つぐのうとおる)。哉のひとつ上の先輩で、哉の親友を執行部長に任命したその人だ。
哉の親友も、やることなすこと非常識ではあったが、多分この人も別の意味で負けていなかったと思い出す。
高校時代はもとより、大学に入ってからも哉たちは時々都織の異母兄にあたると言う後ろではさみを操る緒方未来の練習台になってきた。練習台とはいえ、未来は本当に腕のたつ美容師だったし、ただでしてもらえるのならありがたいくらいだったのだが、ただより高いものはないの例えどおり、このやかましい人がオマケについてくるのだ。
「ほーんとにねぇ びっくりしたよぅ 哉ちゃんが副社長! 大学入った辺りから徐々にしゃべるようになってたとはいえ、人の上に立てるくらい意思表示が可能になったなんてお兄様ってばびっくりよ」
くるくる回りながらそういった後、止まって、運ばれてきた普通のグラスに入ったマンゴージュースからストローを抜き取って直にグラスに口をつけておいしそうに一気飲みして、やっぱりバケツで飲みたいと量の少なさに不満を漏らしている。
「可能ですよ。物心ついたときにはトップに立つことを教え込まれて育ちましたからね、あなたと同じく」
「うわー 嫌味まで言うようになった。成長したねというべきか、前のほうがかわいかったのにって残念がるべきか、どっちにしようかな」
先ほどとは逆に回りながら、言葉とは裏腹に楽しそうだ。
「先輩こそどうなんですか? 観念して事業を継いだら? その顔ならコマーシャルだって自分で出られるでしょう」
「顔がいいのは事実だから素直にほめ言葉と受け取っておこう。でもウチはまだ母上がバリバリ現役だからねぇ 僕の入る隙はナシ。それに顔さらしたら面倒だし。いろいろ」
都織の母は一代でエステサロンを立ち上げ、今や全国展開の最大手まで成長させた超やり手の女性事業家だ。もちろん、コマーシャルは顔もスタイルも知名度も抜群の女優を使って全国ネットで流れている。
最後のほうの少しトーンを落とした言いかたに、哉も思い当り、さすがに相手のペースに従いすぎたかと口をつぐむ。が、相手はそうではなかった。なにやら思いついたらしく、もともと星が浮いたようなきれいな瞳をさらにきらきらと瞬かせて夢を見るような口調でうっとりとのたまわった。
「……ああ……でも芸能界入ったら好葉(このは)ちゃんともっと一緒にいる時間が増えるかなぁ」
「増えない。むしろ減る。確実に減る。やめときなさい、都織」
しゃべらずにはさみを動かしていた未来が断言する。
「名案かもって思ったのにー」
口を尖らせてひざを抱えるのは、女子高生ではなくもうすぐ三十になろうかと言う男のしぐさではないが、都織には妙に似合っている。
「そう言えば、奥さんとお嬢さんはお元気で?」
「元気よー リナなんかもう高一だもんね。月日の経つのは早いよねー 哉ちゃん最後に会ったのいつくらい?」
「高校の三年のときなので、お嬢さんはまだ五つか六つだったと思いますよ」
そう、この人はそのとき大学一回生だったが、すでに子持ちだった。と言うより、彼が十三歳の時に生まれた娘で、相手もまだ十七か十八歳だったはずだ。
先日樹理の母親が言っていた順序が逆の最高に極端な例でなおかつ結婚も今もってしていない。当然、相手は今も生家の苗字を名乗っている。娘も当然そちらの苗字だ。
「もうそろそろ結婚は?」
「んー 好葉ちゃんは有名人だからねぇ 今更入籍はちょっと無理。哉ちゃんがしたらしてみてもいいかも。よかったら合同で」
「氷川君、この脳みその使い方を心底間違った方向にしか向かわせない都織に妙なこと言わない。君の結婚式に本気で乱入して主役の座を奪い取るくらい平気だからね、都織は」
やり取りを黙って聞きながらはさみを使っていた未来が苦笑しながら言う。
「やだなー 哉ちゃんのオカアサマ怖いから、僕そんなことしないよぅ って言うか、哉ちゃんこそ結婚は? お見合い山のように来るでしょう?」
「相手にしている暇がありません、それこそ」
「んなこと言ってたらもらい遅れるよー 適当なとこでえらんどかなきゃ ババ抜きみたいなもんなんだからさ、早くカードを引かないと」
先に引けば確率は低くなるが、時々ババにあたることもあるのだ。兄の場合は自業自得だが、哉はいい例だと思っている。
「ご心配なく。イレギュラーなのを別の山から探し出しましたから」
前髪をカットする為に目を閉じている哉がこともなげに言う。
「あら? まあ。そうですか。見てみたいなぁ 見せてー って言うか、見に行っていい?」
「見学はお断りしますが……来週末のチャリティ団体のパーティーに出る予定です。見たければどうぞ」
「わーい、行く行く。ウチの子達も連れて行こうっと」
そしてまたうれしそうに、都織は鏡をはめ込んだ側のカベを蹴り、椅子を盛大にくるくると回して、べちゃっと落ちた。顔面から。
「氷川君、髪洗うからこっちへ」
「ええ」
哉はため息をひとつ残して洗髪のスタッフに案内されて去っていった。
「ひどい。あんだけしゃべられるようになったんだから、大丈夫? の、一言だってあってもいいのにぃ」
真っ赤な鼻を押さえながら都織が起き上がる。さすがに美形はこんなときでもその穴から何も垂らさないらしい。
「自業自得でしょう。それよりほら、バケツはないけど都織のマイ金魚鉢に入れたの持ってきてくれたよ、マンゴージュース」
黄色がかったオレンジ色の液体をなみなみとたたえた特大の金魚鉢が乗ったワゴンを見て、彼の機嫌はすぐに元に戻った。
|