|
恋におちたら 6
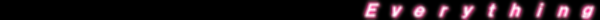
「で?」
うららかな日差しが木々の間からこぼれている。レンガ敷きのテラスにある白いプラスチック製の机の上にはめいめいの昼食プレートが置かれている。
場所は通称第一学食。大学部の学食だが、中高生も利用してもいい。第二学食と呼ばれる中高等部のメニューとそこまで変わらないが、全体的にこちらのほうがおいしいのだ。ただし、高等部からは歩いて五分以上の場所にあるので制服姿の生徒は滅多にいない。
「え?」
今日のパスタセットのぺペロンチーノを上品にフォークでまとめて口に運ぼうとした樹理が、かなり低い音域で発声された真里菜の短い問いかけにびくりと動きを止める。
「教えてほしいんですけどっ! どーっして、お姉さまがあの人と一緒にいたんですかっ!? ってか、いっつもあんな感じ? くっついてないとダメな感じ!?」
「リナ、おびえてる、おびえてる」
Aランチの豚肉のソテーを切る為のナイフとフォークを振り回している真里菜を、大学部のきれいなお姉さんたちが遠巻きに見ている。
「まずは、そうね。いつから!? いつ出会ったの!?」
「え……っと。去年十一月、半ば……くらいかな。初めて会ったのは」
「って! まだ半年!! まだ出会って半年ですかっ!?」
「ええ、そう」
そう言われてみれば、まだ半年なのだ。出会ってから。
「あ、でも正式にお付き合いを始めたのはこの間よ。ゴールデンウイークが始まったくらい」
「それ! めっちゃ最近っ!! そんな最近つきあった人あんなトコに連れてくか!?」
真里菜は、尊大にしゃべりながらも、流れるようにきれいな作法でナイフとフォークを操って、豚肉を口に運んでいる。対する樹理は、一口目を食べることに失敗してからフォークの動きが止まっている。
「どうやってどこで!?」
「んー 父の、仕事の関係で。私の父の会社、氷川の協力工場をしているから」
真里菜がずいずいと体をこちらに寄せてくる。静かに食べているフリをしている翠も、耳が樹理の一言も聞き逃すまいとこちらを向いている。
言えない。というか、言ってはいけない。ある意味、こちらから押しかけて一緒に住んでいるなんて。
「んで、ドコがよくて? あの人の」
「それは……うーん。えーっと。あの、その、ドコが……いいかって。言われても……言わなきゃダメ?」
「ダメ」
何か具体的に答えなくてはと考えても、頭の中に浮かぶのは取り留めのないことばかりだ。
「そう言われても、納得してもらえそうなコレっていうのがあんまり……思いつかないのだけれど」
「ない?」
済まなさそうに頷く樹理に、真里菜が唸る。その唸っている真里菜に、翠が笑いながら言う。
「本モノの恋愛に決定でファイナルアンサー?」
「……ま、まだっ!」
「あのね、お姉さま。都織ちゃんが言うには、ドコドコがスキ! とか言えちゃうのはまだホンモノの恋愛の前なんだって。ほんとにスキならドコもかしこも……なんていうか、あばたもえくぼとか、蓼食う虫も好き好きっていうか、他人から見たら不可解な部分が不可解だとわかった上でひっくるめて好きなはずだから、言いようがないものなんだって」
翠がBランチのサバ煮込みを食べながら解説してくれる。
「へー……そうなんだ。うん、そうかも。氷川さんってね、あんまりしゃべらないし……実はまだ良くわかんないの」
「そんなのとどうして付き合ってんの!?」
「……さあ?」
「さあじゃないでしょう もう」
「リナちゃんは氷川さんのこと知ってるの?」
「知ってるよー 高校生くらいの頃から大学生くらいの頃まで知ってる。都織ちゃんの友達の中でもヘン度数が高いグループの、一番変な人だよ。だから良く覚えてるの」
「ヘン度数……確かにちょっと計り知れないところがあるのは否定はできないけど……割と普通だよ? あの時はなんだかものすごく疲れてたみたいだからあんな感じだったけど、いつもはもっとドライな人だよ」
「ああ、だめだよほら、リナが変って言うくらいだから相当だと思うけど変な人だって否定しないのに普通の範囲内とか矛盾したこと言ってるあたりラブマジックってかイリュージョンな感じ。ま、このお姉さまならそう言うのもありえないけどありえてるかな」
「……どういう意味なのかな、翠ちゃん……」
さすがに何か含んだような翠の言い方に、樹理がにっこり笑って切り返す。
「だって、かわいい女の子は大抵みんな恋する女の子だもーん。さっき出会いからの経過聞いても、ボク達が目をつけたときはバリバリの片思い路線突っ走り中くらいじゃない? ま、結果オーライ両思い。で、あとはどっちが告ったか教えてくれたらうれしいなぁ」
「…………おしえません」
顔を真っ赤にして無意味にフォークにパスタを絡めている樹理を見て、真里菜と翠が目を合わせてニヤリと笑う。
「「お姉さまからだ」」
「あった。多分この人だよ、苗字違うけど絶対。理右湖さんも同じ年のに載ってるから」
放課後の図書室で、三人頭をつき合わせて卒業アルバムに片っ端から目を通し、やっとのことで実冴を発見した。多少この前より若くて当時の流行なのか、眉毛が太かったり髪形がかなり昔の雰囲気だが、あんまり変わっていない。むしろ今のほうが若々しい感じだ。
「ホントに卒業生だったんだ」
疑っていたわけではないが、見るなといわれたら見たくなるのが心情だ。
目当てのものを発見して鑑賞したので、大量に棚から引っ張り出した卒業アルバムたちを返却用のカートに戻して図書室を出る。昇降口へ向かう階段を下りながら真里菜が興味津々と言った顔をして樹理に聞いてきた。
「で、テキはどんなカンジですか?」
「なんか仕掛けてきました?」
藤原呉緒のことをどうしてこの二人が知っているのかと思えば、ラウンジで実冴から二人が来る前の出来事を聞かされたのだそうだ。
「別に……変わらない感じでクラスからは浮いてるよ」
これは嘘だ。今まで挨拶くらいは返してくれていたクラスメイトまで、今日は樹理に総スカンだった。
おまけに休み時間のたびにひそひそとささやきう声が聞こえて、ちらちらとこちらを窺うような視線も感じた。てっきり人目もはばからず罵倒されると思っていたので、これは意外だった。けれど長く続けられると、表立って攻撃されるより堪えそうだ。
「あーあ。どうして二年も違うんだろ。同級生なら今からでも同じクラスになったのになぁ」
「お姉さま、もう一回一年からやらない? 私たちと」
「もう一回はちょっと……それに大丈夫よ。あんまり心配………」
樹理の通う学校の生徒用昇降口は広い。そして天井が二階まで吹き抜けになっていてなぜだか見下ろせるよう内テラスがついている。並ぶ下駄箱はいまどきアルミ製ではなく木製という骨董品だ。もう全く生徒の姿のない昇降口で、一年と三年はちょうど端と端になるので少し大きな声で話しながら樹理は自分のロッカーの扉を開けて、止まった。
「どうしたの?」
通学用のローファーに履き替えた二人が固まったままの樹理の頭越しにロッカーを覗いて。
「あ、靴がないや」
「姑息ー!」
三人でありそうな場所を(主にゴミ箱を)探した結果、学食に設置されたジュースの自販機横に置かれたゴミ箱の中に突っ込まれていた。
「卑怯っ 陰険っ ろくでなしっ! あンのバカ女ー! 呪われてしまえー!!」
「自分では呪わないんだね、リナ……」
ティッシュで靴の汚れを拭く樹理の横で、吠えている真里菜に翠が突っ込みを入れている。
「まあまあ。上履きは持って帰るし、私、教科書とかも置いてないし、多分もう大丈夫よ?」
そう言われても不服気な顔をしたままの二人と、いつもどおり駅前で別れた。
「ふーくーしゃーちょーおおおおおお」
管理人のいるエントランスで泣かれたので部屋に上げたらやっぱり情けない声を上げて瀬崎が玄関でがっくりとくず折れる。彼も社内のテストに上位で合格した、一応未来を約束されたエリートコース、幹部候補生で、いつもは髪型もこまめに散髪しているのか今風に整えて、パリっとしたスーツをきちんと着こなす好青年だ。しかし、目の前にいるのはなんだかもう絞りきられた雑巾よりしわの入ったスーツを引っ掛け、そり残した無精ひげにセットもしようがないくらいひどくぱさついた髪、そして極めつけは落ち窪んだ眼窩。間近で見ると以前とは別人のようにやつれているのがわかる。
「助けてください、俺、死にそうです。ってかむしろ死にたい」
哉に促されてヨロヨロとリビングまでやってきた瀬崎がソファに沈む。
「俺がいなくてもどうにでもなるだろう?」
「なりませんよ。なるわけないじゃないですかっ! 副社長も篠田室長もいないのにっ 大体どうして天上で辞表なんか出すんですかー!? もう、うわさがうわさを呼んで今社内すごいんですよ? なんだか次々に辞表出しちゃうやつがいて収拾つかないッス。それも候補生がっ 俺も二人の片棒担いでると思われてて居心地悪いなんてもんじゃないしっ! 何でいなくなったかなんてこれっぽっちも知らないのにみんなからは何でも知ってると思われてるしっ! 毎朝会社休みてぇーって思っても、帰れないから泊り込みで目が覚めたら職場だから無理だし。いや、いないとまたうわさに拍車がかかりそうだしっ!!」
出されたグラスの氷まで飲み干す勢いでコップの水を一息であけて、ダンっとテーブルに置く。
「なんだ。噂って」
「副社長と篠田室長が新しい会社起こすって。んで、優秀なのヘッドハンティングしてるって。声かけられる前に身軽になろうってバカがわんさか出たんですよ!!」
「お前は?」
「んなこと信じるわけないじゃないですかっ 篠田室長の命令で副社長には連休明けからバリバリ働いてもらう予定だったんですから。それにー………」
空のグラスの氷を見つめて瀬崎が言いよどむ。
「俺、副社長が辞めるときは隠遁生活に入るに決まってるって思ってたし」
瀬崎がちらりと哉を見て『当たってるでしょう?』と目で尋ねている。
「とりあえずたまった有給使ったことにして帰ってきてくださいよぅ コレ、天上の議事録ッス。サッパリ書いてないですよ。副社長が辞表出したことなんて」
分厚い資料が入った封筒を渡して、瀬崎が立ち上がる。
「副社長が来るって言うまで通い続けますからそのつもりでっ! 余生を送るには早すぎますからねっ!! 決済の仕事持ってくるから目ぇ通してくださいよ!?」
やけくそなのかえらく強気な発言を残して瀬崎が帰っていった。そして、本当にその次の日から毎日毎日、哉のマンションにやってきては、山のような決済資料を広げてたまりにたまった愚痴をこぼして帰っていくようになった。
たった三日間、それだけでも針の筵の上にいるのはつらい。移動教室が変更になったことも教えてもらえないし、体育の授業の後は制服の裏にチョークの粉がはたかれていたり、教科書やノートが切られていたりするのだ。そして今週二回目の体育のあと、とうとう。
「キー!! インケンっ! ムーカーツークッー!!」
「どうどうどう」
放課後の被服室で鼻息も荒く歩き回る真里菜と、馬でもなだめるかのように声をかける翠、そしてジャージ姿でちくちく針を動かしている樹理。
女子高だからか、クラブ室はあっても更衣室はない。体育の授業の着替えは全て教室でする。そしてその体育が終わって教室に戻るとスカートのひだの部分が何箇所か五センチばかりざっくりと切られていた。
「まあ、えっと、見えないところだったし、先生が端かがり用のピケを貸してくださったから大丈夫だよ?」
「なんでそんなのほほんと!」
「……だって、それこそうろたえたら思う壺よ? そのうち飽きるわ」
「だんだんエスカレートしてきてるじゃん!! ヤツらが飽きる前にお姉さまきっと上から落ちてきた植木鉢とかに頭カチ割られるからっ!」
「うわー その意見賛成。階段から突き落とされるもありかな。トイレで上から水が降ってくるとか、そう言う段階を経て」
落ち着かなくウロウロしている真里菜が、やられる前に何か罠にはめる方法がないかとぶつぶつ物騒なことをつぶやいている。
「………まさかそんな。二人にお願いなんだけど、明日から体育のとき服とかいろいろ預かっててもらえたらうれしいんだけど」
「お安い御用!! ってか何で気づかなかったんだろう、私のバカー」
そのままカベに額を打ち付けそうなジェスチャーをしながら真里菜が叫んでいる。翠にだけ縫えたので着替えてくると伝えて準備室で着替えて、まだ何か激しく落ち込んでいる様子の真里菜を励まして、学校を後にした。
その翌日は比較的平穏だった。移動教室がなかったため、仕掛けるタイミングがなかったのか、樹理も持ち物も無事だった。
授業を終えて昇降口へ向かう。授業が一年生よりひとコマ多かった樹理が一人で昇降口に向かっていた。二人とは実冴がいたずらをしたという銅像のあたりで待ち合わせている。
樹理は月曜の下校時に通学用のローファーがゴミ箱に突っ込まれたときから面倒だし荷物にもなるが持ち歩くようになっていた。なので、下駄箱を開けることはない。
けれど、自分の名前が入っている下駄箱から何かが引っかかってフタが少し開き、はみ出しているのを見て、ため息をつきながら一番上段の、目線より少し上のその扉を開けた。
一瞬視界が真っ白になる。とっさに目をつぶっても中に何かが入った。気管にも引っかかる。これはなんだろう。
頭から真っ白になってゴホゴホとむせ返る樹理に、昇降口にいた同級生から忍び笑いがもれる。
目が潤むのは悲しいからじゃない。目にゴミが入ったせいだ。そう自分に言い聞かせながら頭や肩、服にかかったものを払い落とす。
「あら、行野さん。なんだかいつもよりきれいになったんじゃなくて?」
きっと吹き抜けの二階から一部始終を見ていたのだろう呉緒が、楽しそうに笑いながら階段を下りてきた。
これまではこそこそとやっていたが、樹理が全く動じないので吹っ切れたのか。もともと、黙っていられるような性格にも見えない。本当はこうやって派手に仕掛けたかったに違いない。
「灰かぶりはつぎはぎだらけの服を着ておとなしくおうちで掃除でもしていればいいのよ。あなたのおうちにはお手伝いさんなんかいないでしょう? 炊事に洗濯に掃除。そんなことしなくちゃいけないなんて、信じられないわ」
呉緒の言葉に、取り巻きたちが同調して何か言っている。
「シンデレラはそうね、もともと良家のお嬢様だったのだし、王子様と結婚してもめでたしめでたし、きっとお妃様になってもその勤めを立派に果たせただろうけれど、あなたは違うでしょう? 前にも言ったけれど、ガラスの靴が足にぴったり合ったって、環境が違う人間が一緒になったって幸せになんかなれないのよ?
氷川さんのおうちの方はあなたのことなんかこれっぽっちも認めないとおっしゃってるそうよ? やっぱりお互い似合う相手というのがいるの。分不相応だったと思うのなら、私に誓ってくださらない? もう二度と高望みなんかしませんって。それから……あなたとっても目障りなの。もっと程度にあう学校に転校なさってよ」
「いいえ。誓ったりなんかしない。転校もしないわ」
ぐいと顔を上げる。きっと灰でぐしゃぐしゃだ。けれど背筋を伸ばして口角を上げる。
「あなたに何を言われようと、されようと、もう私は私に嘘をついたりしないって決めたから。どうしてあなたなんかに誓わなきゃならないの? どうしてあなたから逃げるようなまねをしなくてはならないの? 大体、私がここからいなくなったって、彼はあなたを選んだりしないわ。絶対に。こんな低俗で子供じみたいじめや嫌がらせしかできないくせに。そっちのほうがよっぽど醜くて卑し……っ!」
言い終わる前に鬼のような形相でつかつかと近づいてきた呉緒にこめかみの辺りの髪を一掴かまれた。呉緒のほうが十センチ以上樹理より背が高い。力任せに引き上げられ、その勢いに樹理がよろける。
「まだ自分の立場がわかっていないみたいね!? 私にそんな口を利いたことを後悔させてあげるわ!」
そして耳元でぶちぶちといやな音が聞こえて、唐突に、引かれていた痛みが消えた。頬がくすぐったい。
灰まみれの床に、樹理がぺたんと座り込んだ。視界の端に、自分の茶色い髪先が揺れている。それもとても短い位置で。ついたひざ先に、ゆるく波打った髪の毛が散らばっている。
「次はそのくらいじゃ済まないと思いなさいっ!」
ばたばたと職員室のほうから大人が走ってくる足音が聞こえてきて、呉緒が捨て台詞のように言い残し、取り巻きたちと外へ逃げていった。
「お姉さまっ! だいじょう……っ!」
昇降口から血相を変えて逃げていく呉緒を見たのだろう、真里菜と翠が同じように慌てながら走って来てくれた。何人かの先生も駆けつけてくる。さすがの騒ぎに誰かが呼びにいってくれたらしい。
言葉もなく涙も止まってしまった樹理を、汚れるのも厭わずに二人が両側から抱きしめてくれた。
さすがに毎日毎日、延々滔々と愚痴を聞かされれば、自分は何もしていなくても解消されない疲れがたまってくる。さらに決定権が哉にあった重要案件を山のように抱えてやってくるのだ。なんだか本社に出社して仕事をしていた頃より肩が凝って、哉は読書をやめて首をぐりぐり回した。
時計を見るともう七時を過ぎていた。樹理が帰ってこない。あのやかましい友人たちと遊ぶときは、前もって帰宅時間を告げるのに。
携帯電話にかけてみるかと立ち上がったとき、玄関のドアが開く音が聞こえた。
「………」
いつもならそこで一回、樹理はただいまというのに、今日は何も聞こえてこない。そして居間まで来て哉の顔を見てただいま帰りましたと律儀にもう一度言うのに、哉の事にも気づかない様子でうつむいたままソファの後ろを歩いていく。
「どうした?」
「……えっ!? あ、あれ? 私、もう家の中? ごめんなさい、ただいま……」
「どうしたんだ? 制服は?」
幽霊のようにふらふらとうつむいて部屋に入ってきた樹理が、哉の言葉に顔を上げた。通学のときはいつも制服なのに、なぜか学校指定と思しき白が基調のジャージを着ている。
「え……あの、帰りに、汚してしまって。クリーニングに……」
哉を見ようとしないで泳いでいる目はごまかしようがないくらい赤いし、服装だけでなく全体的に朝出て行ったときと感じが違う。ざっと見て、出かけるときは髪を下ろしていたのに、左耳の上を片方だけバレッタで留めている。その下の髪の毛がひと束、不自然に短い位置で揺れている。
「これは?」
「なんでもないですっ!」
バレッタに触れようとした哉の手をはじくように、かばうようにすばやく樹理が手を上げた。とてもなんでもないような仕草ではない。
「……あのっ 遅くなってごめんなさい。リナちゃんや翠ちゃんと一緒にいて……電話を掛けるのを忘れて……あ、ごはん、用意します。ちょっと待って……っ! ダメっ!!」
言いながら後ずさりで逃げようとする樹理の手をつかんで、バレッタを無理やりはずす。耳たぶより少し上のあたりで散切りにされて短くなった髪が零れ落ちる。慌てて押さえてももう遅い。
「髪を、切られたのか?」
「……っ 大丈夫。平気。髪なんか、また、生えてくるもの。伸びるもの。だからっ だからっ!!!」
哉を見上げる大きな瞳から堰を切った涙が後から後からあふれ出る。泣きじゃくる声がくぐもって聞こえると思ったら、いつの間にか抱きしめていた。樹理の腕が体に絡みつく。何の迷いもなく力の限りしがみつくように。
「どうして何も言わなかったんだ」
泣きながら途切れ途切れにこれまでの経緯を樹理が話す。樹理を責めるつもりはなくても、つい言葉はきつくなる。
「……ごめんなさい」
樹理がシャワーを浴びている間にマンション前のコンビニで買って来たおにぎりや惣菜が、ほとんど手をつけられないままテーブルの上に残っている。
「もう、高校生だし、ウチは割とお上品な生徒が多いし、私が相手をしなかったら、すぐに終わると思ったんです。それに……」
うつむいて言いよどんだ後、無意識なのだろうが短くなってしまった髪を触っている。言葉を捜すような沈黙に、先を促すことなく哉が黙って続きを待っていると小さな、けれども必死な声で樹理がかき集めた言葉をつむぎだす。
「それに私……私、強くなりたかった。このくらいのことで泣いたりなんかしたくなかった……」
樹理が顔を上げた。何度も泣いて、それでも枯れない涙をためた茶色い瞳が揺れている。
「私、もう逃げるのはいやなんです。前……ここを出たとき、あの時からずっと、ずーっと私、後悔し続けたんです。あの時、確かにお父さんの会社のことや、氷川さんの仕事のことや、いろいろ考えて、ここを出るのが一番いいことなんだって、そんな風な安定を私も望んでるって思ってたけど、そんなの嘘だった。私、ここにいたかった。帰りたくなんてなかった……
だけどわからなくて。私自身も、私の考えてることのどれがホントなのか。氷川さんが私のことどう考えてるのか。だから、答えを出す前に逃げたんです。そして、一番いやな後悔だけ残ったんです。
この前、氷川さんが、仕事を辞めたことを誰かのせいにしたくないって言ってるのを聞いて、私も、私の選択を他のもののせいにしたくないって思ったんです。
私はここにいたい。氷川さんとずっと一緒にいたい。そのために何をしなくちゃいけないか考えないといけないんです。氷川さんの隣にいても、誰にも文句を言わせないような人間になろうって、決めたんです。だから、私はこんなことで負けたりしない。あんな人にちょっとくらい何かされたからって、簡単に逃げたくない。
自分で立ち向かわなくちゃダメだって思って。今すぐは無理でも、少しずつでも私も強くなろうと思って。でもさすがに、コレはちょっと、かなり、悔しい」
短い髪に視線を移して、樹理が口を曲げる。
「だってここの毛先、特別だったから」
ポツリとそうつぶやいて、暫し間があった後、樹理がちらりと一瞬哉を見て、目の回りだけでなく顔全体赤くしてわたわたと慌て、キョロキョロ机の上を見回して食べかけのおにぎりを見つけて食べだした。
「……樹理」
「はひ?」
「いや、食べたらもう寝ろ」
一心不乱という風でおにぎりを食べている樹理を見てため息交じりに哉が言うと、素直にハイと応えて、おにぎりを急いで全部食べて、そそくさと歯を磨き、小股で走って和室へ向かう。
「今日はあっち」
障子をあけかけた樹理の腕を取って、そのまま寝室のベッドの上に放り込む。
「……こんな日は一人で寝ないほうがいい。先に寝ていろ。しばらくしたら行く。それから……」
広いベッドの上で何とか起き上がり、ちょこんと正座するように座りなおした樹理が、ほんの少し首をかしげる。その仕草を見て、ため息が漏れるのはなぜなのか。
答えは簡単だ。思わず吸い込みすぎた空気を抜く為だ。息を吐きながら居間へ続く開けっ放しのドアの方へ向く。
「……毛先くらいいくらでも食ってやる」
寝室から立ち去る哉の背中に樹理の声が小さく届く。
「あの、ありがとう」
今まで本当に藤原呉緒のことなど気にも留めていなかったのだから仕方ないこととは言え、こんなことになってから遅いのだが、思い出したのだ。今年の新年の出来事を。あの時はまだ哉はまだそこまで注目されていなかった。事業の建て直しは始めたばかりで、成功するか失敗するか回りは遠巻きに見ているだけだった。
ほとんどの出席者は妻を連れてきている中で、派手な振袖をきた外国人コンパニオンがいるとは思っていたのだ。全く彼女に興味のなかった哉は、彼女が藤原頭取の娘だと言うことさえ意に留めていなかった。
しかし、まだ高校生で、しかも樹理と同学年とは。彼女はもっと年上だと思っていたのだ。少なくとも二十歳以下には見えなかった。
その後、十分くらい藤原に他愛のない話を振られて適当に応えていた。その間、彼女は哉の隣でにこにこと笑い、さりげなく腕に触れたりしていた。ボディタッチは親密さを表現するのに一番いい行動だ。そのためか、後から来る人々に「若い人同士はいい」とか「なかなかお似合いで」など声をかけられたのを覚えている。
べたべたと触られるのは気持ち悪いし、外国製なのか慣れない香水か化粧品のにおいが鼻についた。しなしなと体をくねらせてこびるような流し目を送られ、どうやって逃げようか思案していた哉に、少し遅れてやってきた政治家に挨拶をと篠田が呼びにきてくれたのだが、今考えるとあれは藤原親子を引き離す口実だったのだろう。
惣菜を買って来た袋に戻して冷蔵庫に突っ込んだ後、どうしたものかと考えていたら家の電話が鳴り出した。
『もしもし? 氷川さんですか? 行野です。樹理の母の。私も仕事をしていて今さっき帰ってきて……留守電に学校から電話が入ってて、先生に電話をしたら樹理が学校で……なにかその、少し前からいじめに遭ってたって……今日……髪を切られたとか聞いて……あの、樹理は? 携帯電話にかけても繋がらなくて。もう帰ってますか?』
「少し前に帰ってきて、今さっき寝ました」
「……寝た?」
「ええ、ぼーっとしながら帰ってきて、様子がおかしいので聞いたら……聞いても言おうとしなかったんですが……左耳の辺りをざっくりと切られています。カッターか何かだったみたいで、耳にもかすったらしくて切れていないものの少し赤い痕が。あと何センチかずれていたら……」
樹理は髪のことで頭がいっぱいだったのか、耳の痕には気づいていない様子だったが、もう少しずれていたら顔も切れていたかもしれない。
全部言わなくてもわかったらしく、受話器の向こうで樹理の母が息を飲む音が聞こえた。
『そんな……どうして。いいところのお嬢さんが大勢通っている学校でしょう? どうしてそんな怖いことをする生徒が……』
「いいところのお嬢様がみんなマトモだとは限らないということですが、申し訳ありません。おそらく僕のせいです」
『え?』
「いえ。教師は犯人のことをなにか言っていましたか?」
『それが……現場を見たわけではないからどの生徒かは言えないって……とにかく明日私、学校に行こうと思って』
そうだろう。藤原呉緒の父は寄付者名簿の中でも上位にいるはずだ。そんな娘がなにかやっても、学校ぐるみでもみ消すに決まっている。
いつからだ? あのパーティーから一週間。髪を切られるほどまでにエスカレートするような執拗ないじめを受けていたなんて、全く気づかなかった。
そう言えばあの後から、すこしぼんやりと何か考えているような顔をしていることが多くなっていたとは思っていたが……
『樹理は……樹理は誰にされたか言ったんですか?』
「ええ。同級生の藤原呉緒という子です。樹理さんが目を覚ましたら……明日の朝にでも家に電話するように伝えます」
『ええ、お願いします』
受話器を置いて、樹理の鞄から携帯電話を取り出す。発信の履歴は、自分とあの二人の電話番号ばかりだ。一番新しい真里菜の電話番号を選んでかける。
『お姉さま!? よかった繋がって。今ね、未来ちゃんの店にいてっ……えーっと知り合いのやってるカットサロンにいるんだけど、お姉さまの髪に合いそうなエクステが何種類かあるから、学校休んで明日朝イチで絶対来てっ! あ、開店は九時なんだけど早めにあけてくれるって、だから八時前に……』
「すまない。樹理じゃない」
『え!? えええっ!? お姉さま、家に帰らないであなたのとこにいるのっ!? あれ? なんであなたがお姉さまの電話でかけてるの? ダメダメダメっ! 親しき仲にも礼儀ありですっ 恋人でも携帯電話は見ちゃダメっ』
「樹理はもう寝た。だから聞きたいことがある。樹理に嫌がらせをしていたのは藤原呉緒だけか?」
『一緒になってやってた取り巻きいっぱいいるけど首謀者はそうだと思う。って! 寝た!? お姉さまがそこで寝てる!? なんでっ!? どうして?? ちょっとアンタ私のお姉さまになにしてんのよー!!!』
「明日朝九時に緒方さんの店だな」
電話の向こうで真里菜がギャーギャー叫んでいる。あまりのやかましさに電話を切って、樹理はお前のじゃないと思いつつ、ついでに電源を落とす。
それにしても。
樹理は自分で何とかしたいといっていたが、おそらく樹理一人ではどうしようもないだろう。
この落とし前はどうやってつけようか。
樹理の携帯電話を元通り鞄に仕舞い、自分の携帯電話を取り出す。あのパーティーの日ふざけて入れられた絶対に使わないだろうと思っていた番号がこんなに早く役に立つとは思ってもいなかったが、まだリダイヤルに残るその相手に電話を掛ける。
「もしもし? ええ、僕です。実はちょっと頼みたいことがあるんですが……」
これまでの経緯と用件を簡潔に伝えると、受話器の向こうで一拍の思考の間を空けて、おそらくろくでもないことを思いついたのであろう相手が楽しそうに言った。
「そう言うことなら、派手にやっていいかしら?」
「ええ。できるだけ」
「おーねーぇーさぁまー!!!」
ガラスのドアを開けるとひと目で泣いていたとわかるくらい眼の周りを真っ赤に腫らした真里菜が予想通り自分も学校を放り出して待ち構えていて、突撃隊長よろしく突っ込んでくる。
「ごめんなさい、ごめんなさいっ 私たち中で待ってたら良かったのにっ そしたらこんなことならなかったのにっ ほんとのホントにごめっ」
「リナちゃん、そんな風に思わないで? 私、リナちゃんと翠ちゃんがいてくれて本当に助かってたのよ? ほら、髪だって直るように考えてくれたし。そう言うの、とってもうれしいよ? ね? もう泣かないで」
「ダメ。絶対ダメ。髪は女の子の命だもん。ボクも細いネコっ毛だからわかるもん。手入れとかすごい大変だもん。すぐ枝毛できるし、切れるし。お姉さまくらい伸ばすの、ちまちま切りながらだとすっごい時間かかるの知ってるもん。それをこんな風にする権利、あの女になんかないよっ エクステで隠せても、また元通りになるまで何年かかるかわかんないじゃん」
樹理にしがみついて泣いている真里菜の後ろから翠が、やっぱり泣きながらやってきて樹理の髪の毛先を触る。
「もう、めちゃくちゃ悔しい。コテンパンにのしてやろうかしらあの女っ!」
「合気道有段のリナに本気でやられたらさすがにヤバいかもだからやめてね」
紅茶のカップとポットを盆に載せて、未来が店の奥から出てくる。
「こんにちは。君が樹理ちゃん? 僕は緒方未来です。ここは僕の店。ちなみに都織の兄だよ。片方だけど」
にこにこ笑いながらいつの間にか勝手に哉が座っているテーブルにカップを並べてお茶を淹れている。
「びっくりしたよ。昨日この二人が泣きながら店に来て用件も言わずにまた盛大にわんわん泣いてくれて。君の事聞き出すまで小一時間かかったよ」
どうぞと促されて、哉の右隣の席に着く。机の上には四客のティーセットがあり、まだ鼻を鳴らしながら泣いている二人も席に着いた。
「早速なんだけど、二人から聞いてこんなのかなって用意してたエクステあわせていいかな? あ、気にしないで飲んでて」
「あ、ハイ。よろしくお願いします」
そばにあったワゴンから子供の小指ほどの太さに束ねられた色、太さ、波打ち方の違う様々な種類の髪の房が一列についたものを取り出し、樹理のうしろからあてている。
「んー……やっぱりちょっとちがうなぁ。一週間くらいかかるけど、同じ質の付け毛作ってもらおうか? 何本かサンプルもらったら発注するよ」
どうする? と未来が哉に顔を向ける。小さく頷いたのを見て明るい声で未来が決定してしまう。
「よし、じゃあちょっと目立たないようにセットしようか、樹理ちゃんお茶持ってこっちに来てくれる? 真木野さーん、いいとこ来た。手伝ってー」
慌てて返事をした樹理を待たずに未来がすたすた店の奥に行って、出勤直後のスタッフを捕まえて何か指示している。樹理は半分以上残っている紅茶のカップを手に慌てて未来を追った。
カット用のいすに座って、淡いブルーのケープをかけられる。
「分け目を少し変えて切られた部分は耳の後ろに流してピンで留めたらほとんどわからなくなると思うよ」
言いながらスプレーで水を吹き、上の髪をクリップで留めて短い部分にワックスをつけて後ろに流し、ピンで留める。再び上の髪を戻して、前髪との分け目でいくつかピンをとめて逆の流れを作り、耳のあたりをカバーすれば不恰好に短くなった部分は全く気にならなくなった。
「毛先整えるのは次にしようか。前髪だけ少し切っとく?」
「ハイ、お願いします」
「もうずっと長いの? 髪」
「小さい頃から長かったです。小学四年のときに一度ショートカットにしてみて。短かったのはそのときくらいでそれから伸ばしてます。やっぱり短いと似合わなくて」
「そうだねぇ この髪質だと短いとセットしにくいよね」
「それはもう。毎日バクハツしてました。縛ってまとめられるくらいになるまでもう大変で。人からも長いほうが似合うって言われたし」
「あはははは。それって男の子に? 同級生? あ、その顔は年上だ」
楽しそうに笑う未来を鏡越しに見ると、一緒に映る自分の顔もちょっとだけ赤くなっている。
「それは氷川君には言わないほうがいいかもしれないなぁ」
前髪をはさんだ左手が器用に動いて、梳きバサミがそれを追ってジャキジャキと前髪をカットしていく。
「恋する男はみんな独占欲の固まりだからね。あの氷川君だって例外にあらず。っていうか、彼みたいのは人一倍って感じだねー ハイできたっ 申し訳ないけど来週中はこのヘアスタイルで。エクステつけちゃえばそれからはもうどんな髪型にしてもわからなくなるよ」
「はい……アリガトウございます」
「ドウいたしまして」
複雑そうな顔をしながら礼を言う樹理に、ばさりとケープをはずして、未来が鏡越しに笑って応えた。
ほとんどにらみつけるように見つめられながら、哉は全く気にせずに紅茶を飲んでいた。
沈黙の均衡。言いたいことがあるのなら言えばいいのに、と思っていたら、目の前の少女が真一文字に結んだ口を開いた。
「つかぬ事をお伺いするんですけど、もしかしてお姉さまがそちらに泊まるのはもしかしてっ 初めてではない? とか?」
白いテーブルの上の両手を握りこぶしにして、真里菜が一気にそこまで言ってから、その手を頭に持って行ってぎゃーっと叫ぶ。
「違うくてっ じゃなくて! うわあぁ ダメだ、やっぱり私このヒト苦手。翠、あとよろしく」
「いや、よろしくされたくないんだけど。あくまでリナの想像だし」
「うそっ!? 夕べ同意してくれたじゃない。お姉さまのあの曖昧な答えとかカンガミてとか難しいこといいながら! ひどい、私ひとりのせいにするのね!! 私のこと捨てる気!?」
「捨てる捨てないで言うと、捨てる気」
飄々と紅茶を飲む翠に、逆毛を立てんばかりの様子の真里菜が食って掛かり、あっさりと切り返されている。
「ばかーっ ひきょうものーっ」
「おばかはどっちさ、直球ど真ん中ストレートでどうするの。どっちかっていうとボール球振らせてファウル返されるのを狙おうよ、次からは」
「次があると思う!?」
「あははー ないか。ボクとしてはさすがにそこら辺は危ない橋っぽいしナシの線ってことで、無言の答えがファイナルアンサーなカンジで受け取りたいんですけど。ボクはともかくリナは口軽いし」
「軽くないってば。やるときはお口チャックできる子よ? 私はっ」
小さな口を一文字にして横に手を動かしながらジェスチャーする真里菜を、四つの目が疑わしそうに見つめる。
「んもうっ なんなのよ翠までっ 私たちの大好きなお姉さまを窮地に立たせるようなマネするわけないでしょう!?」
二人の視線に真里菜がテーブルを叩きながら抗議する。
「キミのほうはともかく」
紅茶を一口飲んで、哉が真里菜を見て。
「キミのほうは俺としてはちょっと困る。だってキミは男の子だろう?」
視線を翠のほうへ動かす。
「ちょっとまって! あなたなんで気づいたの!? こう言っちゃなんだけど翠は五歳のときからずーっと女の子で通してきてるしある意味私より女の子度が高いのよ!?」
言い当てられてびっくりしている翠に代わって真里菜が小さな声で、けれども口調は怒鳴っているときのそれで返している。それじゃあ大当たりって言ってる様なもんだよ、もうちょっとごまかしてと思いながらも、とっさのことに反応できなかった翠がため息をついた。
「気づいたわけじゃない。知ってるんだ。キミの母親の瑠璃華(るりか)さんのことも。俺は十二になるまでキミのおばあ様に日本舞踊を習ってたから」
カップを持ったままの手を口元に運び、また一口飲んで、哉はカップをソーサーに戻した。
「キミが生まれたのは俺がやめた後だったけれど、年に数回ある師範の演舞会には招待状をもらっていたから何度か顔を出したことがある。そのときまだ一歳になるかならないかのキミを瑠璃華さんに息子だと紹介されたよ。名前はミドリじゃなくて、音読みでスイ」
哉の口元が、そのときのやり取りを思い出して二人が気づかない程度に少し上がる。瑠璃華がまだ歩けない息子を見せて、哉に息子の名前を言った後、付け加えた言葉。あなたに似ているでしょうと。
彼女が子供の頃から決められた婚約者と結婚したのは二年前で、それよりも少し前に子供の遊びのように、なし崩しに始まった関係は終わっていた。だから、多分彼女が言いたかったのは名前の響きが似ているということなのだと理解した。
「その後、あの事件があったあとは俺も招待を受けなくなったし、会ってはいないけれど。キミは好きでそうしているのか? 一人称がボクなのは、夢と現(うつつ)がわからなくなった瑠璃華さんへのささやかな抵抗?」
それから二・三年後、瑠璃華の夫は逮捕された。児童虐待と暴行障害。もともと彼女は彼女の夫を男性として受け入れることができていなかったのだ。いつも一緒に育った人物を、兄という認識以上には愛せなかった。そしてさらに、彼女は自分の息子も愛せなかった。柴田の流派は男性型の舞踊もあるが、基本的に女子が継承する。跡取りは男の子では意味がないと思っていたのかも知れない。それらの理由の全てに齟齬があったのかは知れないが、徐々に狂いだした歯車は被害の矛先を幼い子供と弱い女性に向かわせて、最悪の結果を生んだ。体と精神に大きな傷を負った彼女が自分が生んだのは娘だと思い込んでいると聞いたのはいつだっただろう。
「何にも知らないくせに……悪いのは全部あの男で、母様は被害者だ。何にも悪くない。最近はそうでもなくなったけど、ボクはあのあと大人の男の人が怖くなって、普通に暮らせなくなった。だからおばあ様が今の学校に入れてくれたんだ。言っとくけど、ボクはこのボクをやめるつもりはないからね。おあいにく様」
視線をそらしたまま、翠が自分に言い聞かせるようにつぶやいた。本当に、悪いのは一人きりなのだろうか。そう思っても、今更どうすることもできない。翠はやめないというが、あと二年もすれば性別をごまかしきれなくなる可能性だってあるのだ。
「どうするの? お姉さまに言う?」
さめたような笑みを口元に湛えて、翠が言う。
「キミたちは樹理の友達なんだろう」
質問を質問で返されて、翠が少し不機嫌そうな顔になった。
「なら、樹理に話したいと思ったときに話してやってくれ。先の質問も、樹理が話したくなったら話すだろう」
一瞬の間のあと、ぽんと真里菜が手を打った。
「あ、やっぱりこの二人ってっ ふがっ!」
真里菜の口をふさいだ翠が微笑みながらも怖い形相で、十センチと離れていない場所からにらみつける。目の前の男は危険だ。できるだけ係わり合いにならないほうがいいと翠の本能が告げている。この軽い口からでた失言のせいで古傷をえぐられた身にもなってみろと言いたいのだろう。
「お口縫おうか? リナ?」
三人のいるテーブルに戻ると、なぜか真里菜と翠が腕相撲の真っ最中だった
二人とも華奢だからか、勝負は拮抗していた。が、徐々に翠が押していく。負けじと真里菜が空いた手でテーブルをつかんで腕力以外の力を込めて押し返し、ついに翠が力尽きて負けた。
「リナ、卑怯」
「おほほ。勝ちは勝ちよ」
「何の勝負なの?」
腕相撲に集中していたらしい二人が樹理の声に始めて近くにいたのに気づいたのか、こちらを振り返る。
「お姉さまに十の質問をする係り決め」
「十も質問するの?」
「いや、言葉のあや。今のトコ一つだし、聞きたいこと」
げんなりとした表情の翠に聞かれて、真里菜が応える。
「なあに?」
「………いや、ここではちょっと。またの機会にお願いします」
そわそわと視線をさまよわせながら翠が言う。少し首をかしげながらも、樹理はそれ以上聞き質さなかった。そこへ片づけをスタッフに任せたらしい未来が現れる。
「緒方さん、次能先輩は?」
「都織? あれは午前中に起きてくるのはかなり稀だねぇ 大体午前三時に寝て正午前かな、起きるの。いると騒がしいけどいないとなんか物足りないんだよね。今はそうでもないみたいだけど。何か用事? それなら昼過ぎにでも携帯にかけてみて」
「わかりました。朝早くからお世話になりました」
立ち上がる哉に、未来がどういたしましてと応えている。その横で真里菜が樹理の腕を引っ張った。
「お姉さま、今日はどうするの? このまま休み?」
「ううん。三時に学校に行くことになっているの。今回の件で、話をしに。母がとにかく一言物申したいって」
「うわあ、加勢いる?」
「いるときにはお願いね。今日はまぁ……母に任せるわ」
「ラジャ」
おでこに人差し指と中指だけを立てた形で敬礼して真里菜が笑う。その横で翠が少しだけ不安そうな顔をしている。
「ウチのおばあ様、高等部の学校長とお友達だからホントのホントに頼って? 約束だからね」
「うん。ありがとう」
マンションの部屋に帰ってすぐ、インターフォンがエントランスからの来客を伝えて鳴り響く。
哉が少しだけ苦笑いをしながら受話器に向かい、短い応答のあと切れた。
「あの、お客様ですか?」
「ああ」
「何かお出ししましょうか? って言っても、コーヒーはないんですけど」
家では哉はほとんど日本茶だ。自分が時々飲む為にティーパックの紅茶があるくらいで。
「いつものお茶か紅茶……どっちにしましょうか?」
「いつものでいいだろ」
「わかりました」
樹理が言い終わるのとほぼ同時に、今度はドアフォンが鳴る。ハイハイと言った風で哉が立ち上がり、玄関を開けに向かう。
「居留守ですか!? まだ五日目なのに居留守使っちゃいますか!? 俺のことなんてもうどうでもいいってことですかっ!?」
翠の言い方を借りるなら、どうでもいいってことだなと思いながら、入ってくるなりめそめそし始める瀬崎をリビングに通す。
「居留守じゃない。さっき帰ってきたんだ」
「えええ。俺、ずーっとエントランスにいたのに。あ、駐車場かっ ああ、ホントに今日はなんか服装が違う。うわあ、すいません疑ったりして」
「いや。で、今日の用件は?」
「あ、ハイ、あっああっ!」
来客用と哉の湯飲みを載せた盆を持ってやってきた樹理を見て、瀬崎がまた大きな声を上げて立ち上がった。
「いいから、座れ」
「どうぞ?」
「は、どうもっ」
立った勢いと同じくらいの慌てぶりで席に再び着き、茶を置いて去っていく樹理を体をひねらせて見送っている。
「で」
哉がわざと音を立てて湯飲みを置いて、ギリギリ限界まで巻いたように後ろを見ている瀬崎を呼び戻す。
「今日はなんだ?」
「はっ!? え? あっ! こちらですっ」
びょんっと巻き戻って、抱えてきたビジネスバッグから付箋がじゃらじゃらとついた分厚いファイルを引っ張り出す。
「この契約、こんな感じでいいか確認お願いします。こっちの書類は中国の工場の分。国内はこちらです。それからこの工作マシンの部品の中国へ向けての輸出の件と輸出規制品目の一覧です」
次から次へとよくまあ詰め込んできたなとあきれるくらいの書類が出てくる。
「はぁ 俺としては早く副社長に来てもらってこんな手間省きたいんですけど」
「うるさい。大体こっちは辞めた身だ。くるから仕方なく手伝ってるだけなのに文句を言うな」
「うそだぁ コレ絶対全部副社長の仕事だし。代わりに隅々まで読んで不明瞭なトコにちゃんと付箋つけて赤ペン引いてる俺の尽力、労ってくださいよ」
添削よろしく真っ赤になっている書類を取り上げて瀬崎が力説する。
「下読みは当たり前の仕事だろう。労う必要はあるのか?」
「いや、それじゃなくてここまでの道のりとか」
「社のハイヤー使ってるやつが言うか?」
「うわ。バレてるし。あ、そう言えば篠田室長から連絡入りました。もう少しだからなんとかやれって。あれってもう少しで戻るって事なんでしょうか?」
「さあ? こっちには何の連絡もないが?」
「ええー じゃあ違うのかなぁ あー お茶がおいしー ここ、いつも水しかでなかったからなぁ それも水道水。いくら東京の水道水がおいしくなったって言っても切ないっすよ、水道水」
お茶を一気に飲んで一息つき、瀬崎がいやみったらしく水道水を連呼する。
「いやならいいぞ、何も出さない」
「あ、ウェルカム水道水。もうなんでもいいっす、飲めるなら。この紙プラス、ミネラルウォーターとか、考えるだけで重いし」
「お代わり淹れましょうか?」
「いただきますっ!!」
リビングとキッチンはダイニングテーブルを挟んでいるとはいえ、カウンター越しに見える。つまり声も聞こえる。なんだか妙なテンションの瀬崎に少し笑いながら樹理が急須を持ってやってきた。
「ありがとうございます」
瀬崎の湯飲みと哉の湯飲みに茶を注いで、ごゆっくりと言い残して樹理が去っていく。
「ええっと、あの、彼女、誰っすか? 昨日までいなかったですよね?」
「知ってるくせに聞くな。今日も俺のほかには誰も見なかったことにしておけ。下手に報告したらまた厄介ごと押し付けられるぞ」
「うへえ。でもこれ以上ってアリなのかな」
先ほどより少し熱いお茶をすすりながら、瀬崎が一人ごちた。
全ての書類にざっと目を通して、二ヵ所ほど訂正が必要な部分にはオレンジのラインマーカーで印をつける。
返された書類を大事そうに鞄にしまって、樹理が気を利かせて買ってきた茶菓子を勧められるまま断りもせず三つも食べ、四杯目のお茶を飲み干して瀬崎が立ち上がった。
「あ、すいません、トイレ借りていいっすか?」
「玄関向かって左のドア」
「ハイ。ありがとうございますっ」
礼を言うと、瀬崎が鞄を置いたままそそくさとリビングを抜けていった。
「あ、お帰りですか? 良かったらこれ、もうすぐお昼だしどうぞ。ちょっと待っててください、袋に入れます。帰りの車の中で食べてください」
やってくる瀬崎を見て、樹理がキッチンから廊下に出てくる。その手に持ったパックの中のおにぎりや玉子焼きなどの定番のお弁当おかずを見て、瀬崎の顔が明るくなる。
「うわぁ ありがとうございます! 今ちょっとトイレ借ります。お茶、美味かったので飲みすぎました」
言ったとおり手は洗ったのかと思えるほどのすばやさで瀬崎が帰ってくる。弁当を入れた紙袋を受け取らず、唇に人差し指を当てて静かにとジェスチャーしたあと身をかがめて小さな声ですばやく樹理にささやく。
「あの人を仕事に復帰させてくれませんか?」
「え?」
「戻ってきてほしいって思ってるのは俺だけじゃないです。今ここに来てるのも、上の差し金ですよ。多分、あの人が抜けて困ってるのは俺たちよりも上層部だと思います。なんていうか、あの人はもう氷川のカリスマになりつつあるんですよ。結構有名人っていうか。仕事に戻らせることができたら、あなたに対する風向きもちょっと変わってくるんじゃないかなってのは、まぁ 俺の希望的観測ですけど。
あなたにしか、できないと思うんです。お願いします、樹理さん、副社長を説得してください」
そこまで早口でまくし立てて、あっけにとられている樹理の手から紙袋を受け取り、すぐに明らかにトーンの違う大きな声でしゃべりだす。
「あああー 誰かの手作りなんて久しぶりすぎて涙が出るっ ホントにありがとうっ!!」
本当に目を潤ませて紙袋の中を覗き込んでいる瀬崎の足元に黒いビジネスバッグが蹴りこまれた。
「用が済んだならとっとと帰れ」
仁王立ち状態の哉に、瀬崎はうへえとまた呻いて、何度も樹理に礼を言いながら玄関のドアの向こうに去っていった。
午後三時の日差しは、夏に近づいてきたとはいえまだまだ春の名残を残している。来客用の玄関に母親の姿を見つけて、樹理が手を振って駆け寄った。
「ごめんなさい、電車が少し遅れて」
通学用の補助バッグから布袋に入れていた上履きを取り出し、履いてきたローファーを仕舞いながら、樹理が言う。
「私もさっき着いたところよ。樹理、あなた靴持ち歩いてるの?」
「うん。荷物になるけどなくなるよりはマシだもの。初歩的って言うか、子供っぽいっていうか、ありきたりなところかな」
「……本当だったのね……いじめを受けてるって。髪は? どこを切られたの?」
「このあたり、かな。再来週にはエクステっていう付け毛をつけてもらってわからなくなる予定。だから大丈夫だよ」
左耳のあたりに手を添えて、樹理が笑う。
「あなたの大丈夫はアテにならないから……」
「って言うか、まだ一週間だよ。中学三年のときの徹底無視状態に比べたら、突っかかってきてくれるだけマシかも」
色素の薄い天然パーマの頭や、おっとりした性格も手伝って、上級生や同級生から何かしらの言いがかりをつけられるのは常だった。けれど小学校からずっと一緒の仲良しグループがあって、彼女たちが樹理をかばってくれていたので、それまではひどいいじめなどは経験したことがなかった。
けれど中学三年生の一年間、樹理はそれまで仲の良かった友達から一斉にハブられた。理由はこの学校を受験することが知られたからだ。ごく庶民的な風土の残る下町に近い地域の学区では、都内では珍しく公立中学への入学率が高く、また公立高校への進学者も多かった。
樹理のいたグループも、同じ高校を受験しようねと言っていたのだ。そんな中で三年になって突然超有名なお嬢様学校に行くことにした樹理に、周りの反応は冷ややかだった。おかげで受験勉強がはかどったのだと自分に言い聞かせたけれど、寂しかったのは忘れられなし、そんなトラウマから同級生に親しい友人を作れなかったのだ。
「……まだマシってあなたね……そう言えば氷川さんは?」
指定された学校長室に向かって二人並んで歩きながら、あっけらかんとした様子の樹理に母親がため息を漏らす。
「家で待ってるって」
そう言って樹理がにっこり笑う。
「だからね、大丈夫だよ、ママ、あ、ココだよ」
母が娘の笑顔につられるように、あきれ交じりの微笑を浮かべたあと、ノックをして声をかけ、返事を待ってドアを開ける。
立派な応接セットにはすでに学校長と女性担任がついていた。促されるままに二人の前に座ると、担任が学校長と自分たち双方になんだか要領を得ない説明をぐだぐだと始める。
担任は知っているはずだ。この週頭から、クラスが微妙な空気に包まれていることを。呉緒は彼女が受け持つ生活科学の授業でも、今まで歯牙にもかけてこなかった樹理のことを、これ見よがしにこき下ろしてくれていたのだから。
それにいちいち頷く学校長もまた知っているのだ。呉緒が今回の件の主犯だと言うことを。けれどもそれを自分たちの口からはいえないのだろう。はっきりと呉緒にいじめられましたと伝えたところで、最善策がとられるとも思えない雰囲気だ。
そのくらい、呉緒は……呉緒の父はこの学園に対して影響力を持っているということなのだろう。
端(はな)から期待をしていなかったので、コレといってこの対応に裏切られた感はない。
「……ですからその、この学校に通うのがつらいようでしたら、こちらのほうではいつでも系列の姉妹校もございますし、そちらでしたら転入出の手続きも簡単で……」
「あの、先生」
身も実(じつ)もないことをしゃべり続けてやっと本音を漏らした担任をさえぎったのは樹理の母だった。
「樹理をいじめていた方を擁護したいのはわかりました。で、これからどうしてくださるのですか? ここくらい良い学校なら、こんなこともないだろうと思っていましたのに、こんなことになるのは残念です。確かにこちらは相手様ほどこの学校に貢献しているとは言いがたいですが、それでも授業料や規定口数の寄付を収めて、大事な娘を通わせているんですよ? それをまあ簡単に転校だなんて」
至極もっともな意見に、担任が学校長に助けを求めるように視線を動かす。
「別に相手のお嬢様に頭を下げさせろとか、そんなことを言いに来たわけではないんです。なるべく穏便に元に戻していただければそれで結構。とにかく、月曜からは普通に通えるようご配慮ください」
毅然とした態度で前を向いてそう言い、もう相手をしたくないとでも言いたげな態度の母を見て、三年前を思い出す。
あの時も母は何度も学校に掛け合ってくれた。けれど状態は改善されなかった。元友達たちの親も交えて話し合ったが、親同士が熱を上げて口論になり、挙句の果てに散々な嫌味を言われて終わった。
あのときの担任も目の前の担任と同じく、なんだかんだと理由をつけて逃げようとしていた。ありありと、もう一年そこそこで卒業なんだから我慢しろという態度が見えて、劇的な改善を期待していたわけではないつもりだったのに、やっぱり少しがっかりした。
そこでドアがノックされ、事務員の女性が現れて、学校長になにやら耳打ちをした。ちらりと樹理たちを見て、失礼と小さく断った後、学校長が事務員とともに部屋を出て行く。
残された担任が、なんとも居心地悪そうに身じろきをした。
「先生。私はなにも悪いことをしていません。学年は違いますがやっと親しい友人もできましたし、来週からもこれまでと同じように学校に通うつもりです」
琉伊に言われたとおり練習しているのだ。こういうときに使わなくてどうするのか。にっこりと口角をあげて軽く微笑んで見せる。大体、系列の姉妹校と言えば、かろうじて関東圏と思われるのでも鎌倉と箱根ではないか。どうしてそんなところに飛ばされなければならないのだ。
平行線を脱しえない会話が途切れ、それと同じくして、廊下の方が騒がしくなる。
何事だろうと腰を浮かせて振り返ったそのとき、ドアがノックもなく開けられ、もともときつい眦(まなじり)をさらに吊り上げて、肩を怒らせた藤原呉緒が入ってきた。
送っていこうかという申し出に、樹理が首を横に振って、昨日泣いたのが嘘のようにすっきりとした顔で行ってきますと家を出るのを見送くる。そしていつものシャチを枕に寝転がって読みかけの本のページを開いたとき、インターフォンが来客を告げる。また瀬崎が来たのかと、半ばあきれながら受話器をとると、薄青いモニタの向こうには来週には来るだろうと思っていた人物が供らしき若い男性と一緒に立っていた。
予想外のすばやさに少し驚きながらも、エントランスを開けて招きいれ、さすがに水ではまずいかなと彼らが上がってくる間少しだけ考えて冷蔵庫を開けると、紅茶とかかれたテープの貼られた保冷容器が目に入る。
おそらく、水道水を連呼していた瀬崎の為に淹れたのだろう。冷蔵庫の脇にある食器棚には、いつでも使えるように奥から前に場所を移動しているガラスのグラス。
あまりにも整いすぎた環境に再びどうしようかと考えていると、ドアフォンが鳴った。
ドアを開けるとダークグレーの背広をきっちりと着こなした藤原と、その後ろに控えるように座ったような目をした男性が立っている。
「どうぞ」
無言のまま会釈して家に上がり、そのままお互い言葉もなくリビングに入る。
「で、どのようなご用件で?」
先にソファに座り、手振りで掛けるように促す。どんな用件で来たのかなどわかっているが、あくまでも鷹揚に、相手よりも高い位置をキープする。
問いかけに判別の難しい半分ため息のような返事をして哉の前のソファに座ったのは藤原だけだ。そして彼が掛けるのと同時に後ろに立ったままの男がすっと老舗和菓子店の紙袋を藤原に渡す。
「ありきたりな手土産で申し訳ないのですが……」
ガラスのテーブルの上にそれを置いて、一拍の間の後、藤原が小さく咳払いをして続ける。
「本日は、当行にお預けいただいていた氷川様の預金のことで……」
いつも年長者の余裕を持って話しかけてくる藤原がなんとも歯切れの悪い言い方をする。
「だけじゃないでしょう? 僕が首謀者だということがこんなに早く伝わるとは思ってもいませんでしたが。といっても、僕も今回の全容は知らないんですが。あの人に任せてるので」
「ならば今すぐ止めていただきたい。あなたはちょっとした遊びくらいのつもりかもしれないが、ことが公になったら取り付け騒ぎに発展しかねない状況になりつつあるんですよ?」
「ちょっとした遊び? そうですね。その程度のことかもしれない」
藤原の言葉に、哉が薄く嘲う。
「一体何のためにこんなことをしてくれたんですか……今日一日……いや午前中だけの半日でうちは個人の純預け入れ高が前日比の四十八%まで落ちたんですよ? 借り入れ高は十五%減だ。他にも金融商品からの撤退の申し入れやら大口顧客が朝からそろって資産を引き上げにかかってくれて、行員たちはなにが起こったかと慌てふためいていますよ」
「月曜の朝にはニュースになっているかもしれませんね」
「氷川君っ!」
しれっとした態度を崩さない哉に、藤原が腰を浮かせかける。
「何のために? 大事なもののためにですよ」
ソファの背もたれに身を預けて、哉が少しだけ胸をそらす。
「藤原さん、誰とどういう取引をしたのか知りませんが、僕があなたの娘と結婚することはありませんよ? あなたの娘が樹理にしていることをあなたが知らないとは言わせません。時間に対して行動がエスカレートするのが早すぎる。おそらくあなたが昨日辺りに、あの子に免罪符を渡したのでしょう? どんなことをしてもかばうから、樹理をとにかく排斥するように」
逃れられないよう藤原の目を視線で捕まえる。
「あなたが子供たちのちょっと遊び、その延長で少しやりすぎただけだというのなら、僕のこの遊びもそんな程度ですよ」
「な、なにを証拠に……大体娘のことと銀行のことは関係ないことでしょう!?」
「証拠? そんなものありませんよ。そうですとも、あなたにとっては、この件は関係ないことだから。でも僕にとっては同じくらい大事なことなんですよ。少なくともそう……あなたの銀行での立場と世間体以上には」
あくまでも笑みを崩さずに哉が畳み掛け、立ち上がってカウンタテーブルに置いていた携帯電話を取り、藤原を見つめる。
「来週頭に娘さんをどこか別のところへ転校させてくれるのなら、いろいろと考えてみてもいいんですが、このままだとついうっかり、あの人のアドレスをなくしてしまいそうで」
ぴっぴと軽い電子音が、張り詰めた空気のせいなのか心なしか大きく響く。
「……なにも、娘を転校させなくても……! 今回のことはこちらに非があったと認めますよ。そして二度とちょっかいをかけたり、近づかないよういい含めましょう。娘と一緒にいたくないというのならそちらが動いていただけたらいいだけの話ではないですか」
「あなたが止めろといったところで止めるような人には見えませんでしたからね。売られた喧嘩を受け流し続けるのは結構神経を使うんですよ。僕としてもあなたの娘をもう二度と見たくもない、というのも理由の一つですね。どうしてこっちが折れなくてはならないのか理由を簡潔に教えていただけませんか?」
携帯電話をいじりながら、哉が再びソファに座る。
娘か銀行か。藤原は哉の父ほど極端ではないにしろ、どちらかというとそちらよりの考え方の人間だ。樹理の父親のように、娘をとったりはしない。大体、本当に娘がかわいいのなら、そんなことはさせないはずだ。考えているようなフリをしているが、頭の中ではもうすでに答えは出ているはずだ。
「……わかりました。転校させましょう」
長いため息のあと、藤原が答えを出した。
「だから今すぐ資産を元に戻してくださるようお相手にご連絡をお願いしますよ」
「イヤです」
唇の端だけで笑顔を作って哉が即答する。
「そちらが手続きを終えられるのを見届けてからですよ。今から向かえばまだ事務処理は間に合うでしょう? 学校も銀行も」
携帯電話をパタンと閉じて立ち上がる。もしかしたら樹理を追い越してしまうかもしれないなと思いながら。
「一体どういう了見ですの!?」
構内履きでなかったら、きっとツカツカという靴底の音が響きそうな足取りで、呉緒が近づいてくる。どうもこうも、さっぱりわからない樹理が戸惑いながら担任を見るが、彼女にもわからないらしく、樹理以上に混乱している様子だ。
「たった今お父様が来て、私を転校させるとかおっしゃるんだけど、あなたなにをしたの!?」
ぽかんとした顔で座っている樹理の胸元のリボンをつかんで力任せに引き、立ち上がらせて呉緒が怒鳴る。
「ここからいなくなるのはあなたのはずでしょう!? こんなことをしてただで済むと思ってるの!?」
呉緒の右手が高々と上げられそして振り下ろされた。
大きな音がした割に、あまり痛くないのは感覚がマヒしているからだろうか。叩いて気が済んだのか、締め上げられていたリボンからも手が離れた。
しばらくしてから、左頬がじんわりと熱くなってくる。
「卑怯な子。私を消してとでも氷川さんにでも頼……!?」
気がついたら体が動いていた。先ほどと同じような音が響いた。手のひらが叩かれた頬よりも痛い。
「なっ!」
再びリボンをつかもうと伸びてきた呉緒の手を払う。きれいに飾られた付け爪が樹理の手の甲を引っかいて剥がれ落ちる。こちらも負けじと呉緒のリボンをつかみにかかる。取っ組み合いというか、掴み合いというのか。
もみ合いの末、気づいたら呉緒に馬乗りに圧し掛かられていた。呉緒の左手が喉を圧迫して声が出ない。その手をどかそうと両手でつかんでもびくともしない。いつの間にか、呉緒の右手にカッターナイフが握られている。それも事務用の小さなものではなく、もち手がオレンジ色の大きな刃がついたものだ。あの時これに髪を切られたのか。担任か母か。誰かの悲鳴が聞こえる。
「あなたなんかっ 消えてしまいなさいっ!」
今度こそダメかもと目を閉じる。一体なにがどうなっているのかわからないが、呉緒が常識を見失うような出来事が起きたのだろう。なんと言っていた? 呉緒のほうが転校させられる?
「見た目はお上品な割にはしつけがなってないな」
なかなか降りてこない凶刃に、おそるおそる目を開けると、呉緒の後ろからその右手を哉がつかんでいた。哉のほうを振り返っているので見えないが、呉緒は驚いた顔をしているのだろう。首を押さえていた手からも力が抜けている。
「氷川さんじゃありませんの……? あの、どうしてこちらに?」
状況を把握しているのかいないのか、呉緒の声が先ほどより三オクターブほど高くなった。
その問いかけに応えず、哉が樹理の上にいる呉緒を横に引き摺り下ろし、その手からカッターナイフを取り上げる。
ようやく動けるようになったのか、担任と母が樹理を助け起こしてくれた。
「全く。この期に及んで」
ざっくりと五センチばかり出ている刃を見て哉がつぶやくように言った。
「あの、それは別に……ちょっとした小道具というか、本当に傷をつけようとか、そう言うことではなくて……」
凶器を取り上げられて、呉緒がしどろもどろ弁解をしている。
「そう言うことではなくて? じゃあまたこういう事をしようと?」
言うや否やの速さで、哉が呉緒の髪をひっぱって、カッターナイフを下から上へ引き上げるように動かした。ジャリジャリという音の後、ばっさりと呉緒の黒髪が切り落とされて床に散らばった。それも一度だけではない。ジャリ、ジャリっと音がするたびに、長い髪が床に落ちる。
あまりの出来事に呉緒が固まっていたのは五秒ほどの間だが、その間に彼女の右側の髪は、あらかた切り落とされてしまっていた。それも、かなり短く。ほとんど地肌が見えるほどのところもある。
細く小さい悲鳴が呉緒の口から漏れた。へなへなとひざから力が抜けるように呉緒が座り込む。哉以外の誰もが声もなくただ呆然としながらその光景を見ていた。
哉はカッターナイフの刃を出したり収めたりと弄(もてあそ)びながら、涙もなく見上げる呉緒に冷たく笑いながら怖いことを言う。
「ハムラビ法典を知っているか? 目には目をというあれだけれど、それは厳密には違うんだ。同階級なら同じ罰で済むが、例えば奴隷が貴族の目を傷つけたなら、その罪は命を持って贖わなければならない。さすがに今の日本の法律では無理だからな。それくらいで許してやろう」
ジャキジャキっとカッターナイフの刃を柄の中にしまい、ソファに投げて手についたほこりを払うような仕草をしたあと、その手を樹理に伸ばす。
「用は済んだな。帰ろうか、樹理」
|